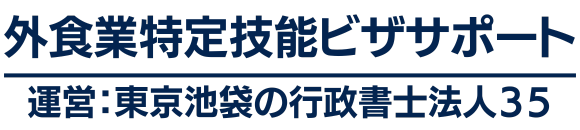登録支援機関の義務的支援その②「出入国時の送迎」とは?|特定技能外国人
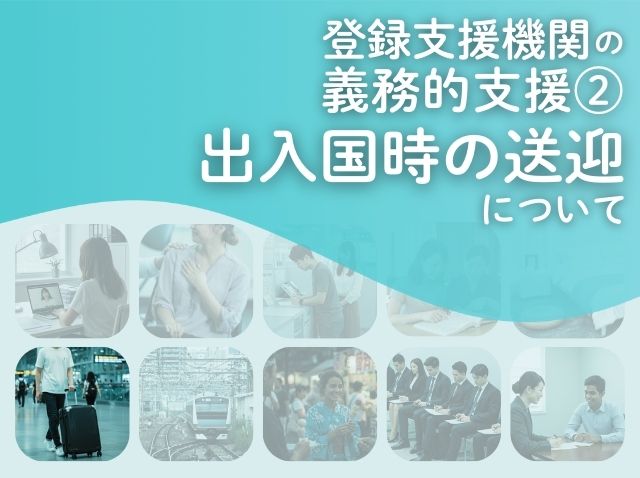
特定技能外国人を受け入れる際、「出入国時の送迎」が義務的支援である事実はご存知でしょうか。
初めて外国人材を採用する企業様や、特定技能制度の運用にまだ慣れていない人事担当者様は、「具体的に何をどこまでするべきか?」「法律上の決まりは?」「送迎費用は会社が持つのか?」「注意すべき点は何か?」など、多くの疑問をお持ちのことでしょう。
特定技能の支援業務は多岐にわたるため、空港や港での対応に戸惑う場面もあるかもしれません。本記事では、特定技能制度における重要な義務の一つ「出入国時の送迎」に焦点を当てます。具体的な実施方法、費用負担のルール、担当者が押さえるべき注意点、そして送迎義務を怠った場合のリスクまで、網羅的に解説。この記事を通じて、送迎に関する疑問を解消し、自信を持って外国人材を迎え入れ、送り出す準備を整えていただければ幸いです。
目次
- なぜ送迎は義務?特定技能「出入国送迎」の重要性
- 「入国時の送迎」どこからどこまで?
- 「出国時の送迎」どこまで見送る?
- 送迎担当はどう決める?自社でやるか登録支援機関に任せるか
- 送迎費用は誰が払う?「100%企業負担」の原則
- 送迎義務違反のリスクについて
- Q&A:出入国時送迎の疑問を解消
- まとめ
なぜ送迎は義務?特定技能「出入国時送迎」の重要性
まず、なぜ特定技能外国人の出入国時の送迎が、企業の「義務」とされているのでしょうか。背景にある目的の理解は、送迎業務へ適切に取り組む上で非常に重要です。単なる移動の手伝いではない、送迎の法的な位置づけと本質的な意味を見ていきましょう。
送迎義務を定めた規定とは?(関連省令・運用要領)
特定技能外国人の出入国時における送迎義務は、規定で明確に定められています。
具体的には、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令、さらには出入国在留管理庁が示す「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」に根拠規定が存在します。受入れ企業(特定技能所属機関)または委託を受けた登録支援機関が実施すべき支援の一つとして規定されています。企業は、法令に基づき特定技能外国人に対する支援計画を作成する際、出入国時の送迎に関する内容を盛り込む必要があります。
なぜ送迎が必要なのか?外国人材の安心確保と失踪防止という目的
法律で送迎が義務付けられている理由は、主に以下の点に集約されます。
- 第一に、初めて日本に来る、あるいは不慣れな手続きを行う外国人材の不安を和らげ、安全を確保するためです。空港や港での複雑な手続き、住居までの移動は、本人だけでは困難なケースが多いと考えられます。企業担当者や支援機関のスタッフが同行することで、安心して日本での第一歩を踏み出す手助けとなるでしょう。
- 第二の目的は、円滑な出入国手続きのサポートです。特に出国時には保安検査場への入場まで確認するよう求められており、特定技能外国人の確実な出国を担保し、不法残留(オーバーステイ)や失踪を防ぐ重要な措置と位置づけられます。制度の信頼性を保つ上でも欠かせない対応と言えるでしょう。
- 加えて、最初の接点となる送迎を丁寧に行う行為は、企業と外国人材との良好な信頼関係を築く大切な機会にもなります。
法的な位置づけと目的について、ご理解いただけたでしょうか。次に、実際の入国時において、具体的にどのような送迎対応が求められるのか詳しく見ていきましょう。
【入国時の送迎】どこからどこまで?具体的な流れと注意すべき点

特定技能外国人の入国時における送迎義務について、より具体的に見ていきましょう。
「どこからどこまで」送迎する必要があるのか、空港や港ではどのように対応すればよいのか、そして移動手段はどう選ぶべきか。初めての受け入れでもスムーズに対応できるよう、具体的な流れと注意点を解説します。
入国時の送迎範囲:「到着空港・港」から「新生活の拠点(事業所or住居)」まで
まず、入国時の送迎でカバーすべき範囲を確認します。
法律で定められているのは、特定技能外国人が飛行機や船から降り、上陸手続きを終えて出てくる港または空港の到着ロビー付近から、日本での生活を始める拠点、つまり勤務先の事業所または用意された住居までの区間です。該当区間の移動を、受入れ企業または委託を受けた登録支援機関が責任を持ってサポートする必要があります。
空港・港で確実に合流するには?待ち合わせ場所や出迎えのコツ
広い空港や港で、初めて来日する外国人とスムーズに合流するには、事前の準備と当日の工夫が欠かせません。最も重要なのは、待ち合わせ場所を具体的に指定する作業です。
「○○空港第1ターミナルの到着ロビーA出口前」「国際線到着階のインフォメーションカウンター横」のように、誰にでも分かる明確な場所を選び、事前に本人へ伝達しておきましょう。送迎担当者の服装の特徴や、会社名を書いたプラカードを持つ旨などを伝えておくと、相手も見つけやすくなります。到着ロビーに出てきた本人と会えたら、パスポートなどで本人確認を確実に行うことも忘れないようにしましょう。
移動手段はどうする?車両・公共交通機関の選び方と移動中の配慮
空港・港から事業所や住居までの移動手段には、いくつかの選択肢があります。
社用車や担当者の自家用車を利用する方法も可能です。車両での送迎は旅客運送事業には該当しないため、通常、第二種運転免許は不要とされていますが、安全運転には最大限配慮すべきです。電車やバス、タクシーといった公共交通機関を利用する手段も認められています。
どの方法を選ぶにしても、事前に経路や所要時間、費用を確認し、適切に手配することが大切になります。移動中は、大きな荷物の運搬を手伝ったり、簡単な会話で緊張をほぐしたりするなど、外国人材の負担を軽減する配慮も求められるでしょう。
【注意】在留資格変更(技能実習→特定技能)の場合、入国時送迎は不要?
ここで一つ注意点に触れておきます。
もし受け入れる特定技能外国人が、技能実習2号など他の在留資格で既に日本に滞在しており、国内で特定技能1号へ在留資格を変更した場合はどうでしょうか。海外からの「入国」にはあたらないため、空港・港から住居等への送迎義務は発生しない、というのが答えです。ただし「義務ではない」という意味合いであり、企業が任意で移動のサポートを行ったり、交通費を負担したりする行為はもちろん問題ありません。
入国時の具体的な流れと注意点はイメージできたでしょうか。次は、意外と見落としがちな「出国時」の送迎について、その範囲と重要なポイントを詳しく解説していきます。
【出国時の送迎】どこまで見送る?義務の範囲と最重要ポイント
特定技能外国人のサポートは、入国時だけではありません。
雇用期間が満了し、母国へ帰国する際の「出国時の送迎」も、法律で定められた企業の重要な義務となります。では、出国時にはどこからどこまでサポートし、何に注意すべきでしょうか。特に見落としがちな最重要ポイントを含め、詳しく解説します。
出国時の送迎範囲:「生活拠点」から「出発空港・港」まで
まず、出国時の送迎が必要となる範囲を確認しましょう。対象区間は、特定技能外国人が生活している住居、または最終勤務日を終えた事業所などから、出国便が出発する空港または港までです。
入国時と同様に、この移動サポートを企業または登録支援機関が提供する必要があります。
保安検査場までの同行・入場確認はなぜ必須?(不法残留防止)
出国時の送迎で最も注意すべき、そして必ず実行しなければならないのが「保安検査場への入場確認」です。
単に空港や港に送り届けるだけでは、義務を果たしたことにはなりません。担当者は必ず、特定技能外国人が保安検査場の中へ確実に入場する様子を見届ける必要があります。なぜ入場確認まで求められるのでしょうか。理由は、不法残留(オーバーステイ)や失踪を確実に防止するためです。本人が間違いなく出国手続きに向かった事実を企業側が確認する、制度の信頼性に関わる重要なプロセスと位置づけられています。
【注意】休暇などでの「一時帰国」、送迎は義務ではない?
入国時と同様、出国時にも注意点が存在します。
特定技能外国人が長期休暇などを利用して一時的に母国へ帰るケースです。こうした「一時帰国」の際の空港等への送迎は、義務的支援には含まれません。あくまで、特定技能としての雇用契約が終了し、完全に帰国する場合などが義務の対象となります。もちろん、一時帰国であっても任意で送迎サポートを提供するのは問題ありません。
入国時と出国時、それぞれの送迎義務の内容をご理解いただけたかと思います。次に、この送迎業務を「誰が担当するのか」、自社で行う場合と外部に委託する場合について、それぞれのポイントを見ていきましょう。
送迎担当はどう決める?自社でやるか、登録支援機関に任せるか

さて、特定技能外国人の出入国時の送迎を、具体的に誰が担当するのでしょうか。受入れ企業が自社の担当者で行うべきなのか、それとも専門の機関に任せるべきなのか。多くの企業様が悩むポイントです。ここでは、自社で対応する場合と、登録支援機関へ委託する場合、それぞれの選択肢と検討すべき点について解説します。
基本は自社対応:担当者選定や複数名・深夜早朝対応のポイント
まず原則として、特定技能外国人への支援義務は、受入れ企業(特定技能所属機関)自身にあります。
したがって、出入国時の送迎も自社で行うのが基本です。自社で対応する場合、担当者を誰にするか検討が必要でしょう。必ずしも高い語学力が求められるわけではありませんが、身振り手振りや簡単な英語、翻訳アプリなどを活用し、外国人材とコミュニケーションを取ろうとする姿勢は大切です。複数名を同時に受け入れる際の体制や、深夜・早朝のフライトにどう対応するかなど、具体的な運用ルールを事前に決めておく作業が、スムーズな実施の鍵となります。
外部委託の選択:登録支援機関に任せるメリット・デメリット
自社での対応が難しい、あるいはより専門的なサポートを望む場合、国の登録を受けた「登録支援機関」に支援業務の全て(送迎を含む)を委託する選択肢があります。登録支援機関は外国人支援の専門家であり、委託するメリットは少なくありません。例えば、煩雑な送迎業務から解放され人事担当者が本来の業務に集中できる点、支援のノウハウや多言語対応の知見を活用できる点、そして法令を遵守した適切な支援が期待できる点などが考えられます。一方で、デメリットとしては、当然ながら委託費用が発生します。また、支援状況を把握するために、登録支援機関との定期的な情報共有や連携が不可欠となります。
登録支援機関へ委託する際の契約・費用・法的注意点
登録支援機関へ送迎を含む支援業務を委託すると決めた場合、いくつかの手続きと注意点があります。まず、委託する支援機関との間で、支援内容や費用などを定めた委託契約を正式に締結しなければなりません。
そして、委託契約に基づき、特定技能外国人の支援計画にも委託する旨を記載する必要があります。重要な点として、支援を委託した場合でも、送迎にかかる実費(交通費など)を含む支援費用全体の負担義務は、原則として受入れ企業側にあることを覚えておきましょう。登録支援機関に費用を請求される形が一般的です。加えて、登録支援機関が送迎を適切に行える体制か(例:車両送迎を行う場合の法的要件を満たしているか等)を確認し、信頼できる機関を選ぶ視点も大切です。
送迎の実施体制について、自社対応と委託のそれぞれの特徴をご理解いただけたでしょうか。次に、どちらの体制を選ぶにしても共通して重要となる、送迎の「費用負担」のルールと、実施にあたって押さえておくべき「重要ポイント」について詳しく解説します。
送迎の費用負担ルールと、実施時に押さえるべき重要ポイント
特定技能外国人の出入国時送迎を適切に行うためには、費用負担のルールを正しく理解し、実施にあたっての重要ポイントを押さえておく作業が不可欠です。ここでは、担当者として必ず知っておくべき費用負担の原則と、送迎をスムーズに進めるための具体的な準備・注意点、そして記録の重要性について解説します。
送迎費用は誰が払う?「100%企業負担」の原則と本人請求NGの理由
まず最も重要な費用負担のルールから確認します。
出入国時の送迎にかかる費用、例えば交通費(電車代、バス代、高速代、タクシー代など)、車両を使用した場合のガソリン代、必要に応じた担当者の人件費などは、全て受入れ企業(特定技能所属機関)が負担しなければなりません。法律で定められた大原則です。絶対にやってはいけないのは、送迎費用を特定技能外国人本人に請求したり、給与から天引きしたり、あるいは名目を変えて間接的に負担させたりする行為。
費用負担は企業の義務であり、本人に負担させる行為は法令違反となりますので、十分な注意が必要です。
送迎前の必須準備:フライト確認から緊急連絡体制までのチェックリスト
送迎当日をスムーズに迎えるためには、事前の準備が鍵となります。
まず、利用する飛行機や船の便名、正確な到着・出発時刻、利用ターミナルなどのフライト(または船舶)情報を再確認しましょう。次に、日本到着後すぐに本人と連絡が取れる手段(例:日本で使えるSIMカードの手配やWi-Fiルーターの貸与、緊急連絡先など)を確保しておくのも重要です。空港・港から目的地までの移動経路、所要時間、概算費用も事前に調べておきます。万が一の遅延やトラブルに備え、緊急時の連絡体制を社内および本人との間で確立しておく必要もあるでしょう。
さらに、当日の本人確認をスムーズに行うための資料や、必要に応じて多言語での簡単な案内表示などを用意しておくと、より丁寧な対応が実現します。
送迎当日の注意点:遅延対応、文化・言語への配慮、トラブル対策
万全の準備をしても、当日は予期せぬ事態が発生するかもしれません。
例えば、フライトの大幅な遅延や欠航、あるいは本人と連絡が取れなくなるといったトラブルです。不測の事態に備え、事前に対応手順を決めておくと、慌てず冷静に対処できるはずです。また、送迎は外国人材と最初に接する重要な機会。
相手の出身国の文化や宗教的な習慣(挨拶の方法、食事のタブーなど)に可能な範囲で配慮する姿勢が、良好な関係構築につながるでしょう。言葉の壁に対しては、スマートフォンの翻訳アプリを活用したり、簡単な日本語や英語でゆっくり話したりするなど、コミュニケーションを図ろうとする努力が大切です。必要であれば、通訳の手配も検討すべきです。
なぜ記録が必要なのか?送迎実施状況の記録・保管義務について
最後に、忘れがちなのが支援記録の作成と保管です。
特定技能外国人への義務的支援(送迎を含む)を実施した場合、実施内容を記録し、一定期間保管する義務が法律で定められています。
「いつ、誰が、誰に対して、どのような送迎支援を行ったか」を具体的に記録に残さなければなりません。
作成した記録は、出入国在留管理庁への定期的な報告や、立入検査などで提示を求められる可能性があります。適切な支援が行われている証明のためにも、日々の記録を怠らないようにしましょう。
費用負担のルール、事前の準備、当日の注意点、そして記録の重要性をご理解いただけたでしょうか。これらのルールや注意点を守らなかった場合、企業にはどのようなリスクがあるのでしょうか。
次に、送迎義務を怠った場合の具体的な影響について解説します。
送迎義務違反のリスク:指導・受入れ停止・信用失墜の可能性
「忙しくて手が回らない」「費用がかさむ」といった理由で、もし特定技能外国人の出入国時送迎を適切に行わなかった場合、企業にはどのようなリスクが待ち受けているのでしょうか。
軽い気持ちで義務を怠ると、想像以上に深刻な事態を招く場合があります。ここでは、送迎義務違反がもたらす具体的なリスクについて解説します。
リスク①:出入国在留管理庁からの指導や改善命令
出入国時の送迎を含む義務的支援が適切に行われていない事実が発覚した場合、まず考えられるのが、出入国在留管理庁(入管)からの行政指導です。
具体的には、支援体制の問題点を指摘され、改善を求める「指導」や、より強制力を持つ「改善命令」が出される可能性があります。企業に対して法令遵守を促すための行政的なアクションと言えます。
リスク②:最悪の場合、特定技能外国人の受入れ停止処分
入管からの指導や改善命令に従わない場合、あるいは違反内容が悪質であると判断された場合、さらに重いペナルティが科される恐れがあります。
最も深刻な処分の一つが、「特定技能外国人の受入れ停止」。一定期間、あるいは無期限で新たな特定技能外国人を受け入れることができなくなるかもしれません。外国人材を重要な戦力と考えている企業にとっては、事業継続にも関わる大きな打撃となり得るでしょう。
リスク③:法令違反による企業イメージダウン・社会的信用の失墜
行政処分に加えて、企業が負うリスクは社会的な側面にも及びます。
法令違反の事実が外部に知られれば、企業の評判は大きく傷つく結果を招きます。
「外国人労働者を大切にしない企業」「法律を守らない企業」といったネガティブなイメージが定着し、社会的信用を失う事態につながりかねません。信用の失墜は、採用活動の難化や、取引先との関係悪化など、事業運営の様々な面に悪影響を及ぼす危険性があります。
【補足】やむを得ず送迎できない場合の代替措置(情報提供義務)
原則として送迎義務は必ず果たさなければなりませんが、予期せぬ天災や極めて特殊な事情により、どうしても物理的に送迎が実施できない状況も、ゼロとは言い切れません。
万が一の事態に備え、運用要領では、代替措置として外国人本人が自力で目的地までたどり着けるよう、詳細な情報を提供することが「望ましい」とされています。具体的には、利用可能な交通手段、乗り換えを含む詳細な経路、所要時間、費用の目安、そして緊急時に確実に連絡が取れる連絡先などを、本人が理解できる方法で確実に伝達しておく必要があります。ただし、あくまで例外的な状況への備えであり、送迎義務が免除されるわけではない点に留意しなければなりません。
送迎義務違反がもたらすリスクの重大性をご理解いただけたでしょうか。法令を遵守し、適切な対応を心がけることが何より重要です。さて、ここまで解説してきましたが、実際の運用場面ではさらに細かい疑問が出てくるかもしれません。
次に、担当者の方が抱えがちな具体的な疑問について、Q&A形式でお答えしていきます。
Q&A:担当者が抱えがちな「出入国時送迎」の疑問を解消
ここまで特定技能外国人の出入国時送迎について、基本的なルールや注意点を解説してきました。しかし、実際の運用を考えると、「こんな場合はどうなるの?」といった、さらに細かい疑問が浮かんでくるかもしれません。ここでは、人事担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。
Q. 送迎に使う車は?社用車でも大丈夫?二種免許は必要?
A. 送迎には、会社の社用車や担当者の自家用車を使用しても問題ありません。
特定技能外国人への送迎は、運賃を受け取る旅客自動車運送事業にはあたらないため、原則として運転手が第二種運転免許を持っている必要はないと解されます。ただし、当然ながら安全運転には最大限の注意を払いましょう。
Q. 深夜便や早朝便でも、必ず送迎しないといけないの?
A. はい、送迎義務に時間帯の例外はありません。
特定技能外国人が到着する便、または出発する便が深夜や早朝であっても、原則として送迎を行う必要があります。担当者の負担も考慮し、自社で対応するのか、登録支援機関に委託するのか、あらかじめ体制を整えておくのが重要です。
Q. 複数人が同じ便で到着した場合、まとめて送迎してもいい?
A. はい、複数名を一度に送迎する行為自体は可能です。
ただし、使用する車両の定員を必ず守り、一人ひとりの荷物量や体調などにも配慮した対応が求められます。個々の外国人に対して適切な支援が行き届くよう注意が必要です。
Q. 外国人本人の家族が一緒に入国する場合、家族の送迎も義務?
A. いいえ、義務的支援としての送迎対象は、特定技能外国人本人のみです。
もし、本人が家族(配偶者や子など)を帯同して入国する場合でも、帯同家族に対する送迎は法律上の義務ではありません。もちろん、企業が任意的支援として家族も含めてサポートする対応は可能です。
Q. 支援計画書には、送迎についてどこまで詳しく書く必要がある?
A. 1号特定技能外国人支援計画書には、「出入国する際の送迎を実施する」という旨を記載する必要があります。
具体的な日時や担当者名まで詳細に記す必要まではないのが一般的です。ただし、登録支援機関に委託する場合は、委託する機関名を明記しなければなりません。記載方法の詳細は、念のため管轄の出入国在留管理局に確認すると、より確実でしょう。
Q. 遠方の空港でも送迎は必須?地理的な負担への対応は?
A. 義務である以上、原則としては特定技能外国人が利用する空港・港への送迎が必要です。
しかし、企業所在地から非常に遠い空港を利用する場合、送迎の負担が大きいのも事実。現実的な対応としては、外国人材を受け入れる前の段階で、利用する空港について双方でよく話し合い、企業側で送迎対応が可能な空港(例:最寄りの国際空港など)を案内し、調整しておく取り組みが推奨されます。
Q. 電車やバスなど公共交通機関での送迎、注意点は?
A. 公共交通機関を利用した送迎も認められています。
注意点としては、乗り換えが必要な場合の分かりやすい案内、切符の購入サポート、ラッシュ時の混雑への配慮、大きな荷物を持っている場合の周囲への気配りなどが挙げられるでしょう。また、移動中に迷子にならないよう、しっかりと付き添う必要もあります。
具体的な疑問点は解消されたでしょうか。
本記事で送迎に関する主要な論点は網羅できたかと思います。最後に、記事全体のポイントをまとめ、適切な出入国時送迎の重要性を改めて確認しましょう。
まとめ:適切な出入国時送迎で、特定技能外国人との良好なスタートを
本記事では、特定技能外国人の受け入れにおける「出入国時の送迎」について、法的根拠から具体的な実施方法、注意点まで詳しく解説してきました。
送迎は単なる移動のサポートではなく、入管法等で定められた企業の重要な法的義務。入国時は空港・港から新生活の拠点まで、出国時は生活拠点から空港・港の保安検査場入場まで、責任を持って対応する必要があります。
費用は全額企業負担であり、外国人本人に負担させることは許されません。実施体制は自社で行うことも、登録支援機関へ委託することも可能ですが、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で選択するのが肝要です。
事前の準備や当日の配慮、そして実施記録の保管も忘れてはならないポイントと言えるでしょう。適切な送迎は、法令遵守はもちろんのこと、日本での生活を始める、あるいは終える外国人材の不安を取り除き、企業との信頼関係を築くための第一歩。丁寧なサポートは、外国人材の早期定着や活躍にもつながるはずです。
出入国時の送迎を含む義務的支援の実施について、「自社のリソースだけでは不安がある」「より具体的なアドバイスが欲しい」「登録支援機関への委託を具体的に検討したい」など、お悩みの場合は、外国人雇用とビザ申請の専門家へ相談するのが最も確実で安心な方法です。
私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
関連するオススメ記事はこちら
- 登録支援機関の義務的支援その⑤「公的手続きへの同行」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その④「生活オリエンテーション」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その③「住居の確保・契約支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その②「出入国時の送迎」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その①「事前ガイダンス」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援・任意的支援とは?人事担当者が知るべき違い・費用・選び方を徹底解説
- 特定技能1号で家族の帯同ができる?要件・必要書類について徹底解説
- 特定技能外国人の転職について|要件・手続き・注意点を解説
- 特定技能ビザから技人国ビザへの変更方法について|要件・方法・注意点を解説
- 特定技能ビザで働く【外国人】のメリット・デメリットについて

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート