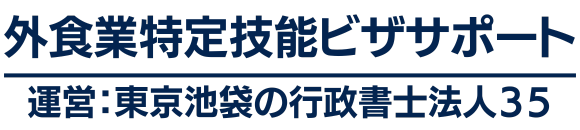登録支援機関の義務的支援その⑦「相談・苦情への対応」とは?|特定技能外国人

特定技能外国人の方の受け入れ準備、本当にお疲れ様です。数ある義務的支援の中でも、「相談・苦情への対応」という項目には
「どんな体制を準備すればいいの?」
「もしネガティブな意見が出たらどうしよう…」
「そもそも、どんな相談が寄せられるんだろう?」など
見えない部分への対応に特にご不安を感じていらっしゃる人事担当者の方も多いことでしょう。
従業員の声に耳を傾ける大切な役割だけに、どのように準備すべきか悩ましいですよね。
この記事は、まさにそのような人事担当者様の疑問や心配事を解消するためにあります。特定技能制度における義務的支援として定められた「相談・苦情への対応」とは一体何なのか、なぜそれが企業にとって重要なのか、そして具体的にどのようなアクションが求められるのかを、一つひとつ丁寧にひも解いていきます。
対応する際に気をつけるべきポイントや、大切な記録の残し方についても触れます。特定技能ビザ申請のプロである行政書士が、出入国在留管理庁の公式な指針に基づいて解説しますので、この記事を最後までお読みいただければ、外国人従業員からの声に適切に向き合うための準備が整い、自信を持って対応に臨めるようになるはずです。
目次
まずは基本から!特定技能の「相談・苦情への対応」とは?
特定技能外国人の方を会社に迎え入れる際、必ず対応が必要となる「義務的支援」
その中でも、「相談・苦情への対応」は、従業員との信頼関係を築く上で特に重要な役割を担います。
この章では、この支援が特定技能制度においてどのような意味を持つのか、そして、なぜ企業がこれに真摯に向き合うことが求められるのか、基本的な定義と目的を分かりやすく解説します。
義務的支援としての位置づけ
特定技能1号の在留資格で働く外国人材を雇用する企業には、法律に基づいて10項目の支援を行う義務があります。
これらを「義務的支援」と呼びますが「相談・苦情への対応」はその中核をなす支援の一つです。これは、事前に生活オリエンテーションなどで伝えた相談窓口などを実際に機能させ、外国人従業員が日本での仕事や生活を送る中で直面するかもしれない様々な問題や悩み、あるいは不満の声を受け止め、その解決に向けて企業がサポートする体制を整え、実行することを意味します。
いわば、言葉や文化の壁を越えて、彼らが安心して頼れる「会社の相談窓口」としての役割を果たすことが求められているのです。
なぜ「相談・苦情への対応」が義務なのか?その目的と重要性
では、なぜ企業が外国人従業員の声に耳を傾け、対応することが法律で義務付けられているほど大切なのでしょうか。
その根本的な目的は、外国人従業員が抱える仕事上、あるいは生活上の様々な問題を早期にキャッチし、大きなトラブルになる前に解決の手助けをすることにあります。異国での新しい生活や仕事には、言葉の壁はもちろん、文化や習慣の違いからくる誤解、予期せぬ困難がつきものです。
「こんなこと相談してもいいのかな…」と遠慮しているうちに、小さな不満が積み重なってしまうことも少なくありません。企業が相談しやすい窓口を設け、真摯に対応する姿勢を示すことで、こうした問題を未然に防いだり、こじれる前に解決したりする糸口が見つかります。これは、結果的に働きやすい職場環境の改善にも繋がる貴重なフィードバックの機会とも言えます。
さらに「困ったことがあればいつでも相談できる」という安心感は、外国人従業員の精神的な安定を支え、仕事への意欲を高め、ひいては会社への定着率を向上させる大きな力となります。加えて、不当な扱いや労働条件に関する問題などを早期に把握することは、労働関連法規などの法令遵守を確認し、人権を守るという企業の社会的責任を果たす上でも不可欠です。外国人従業員が孤立せず、安心して能力を発揮できる環境を作るために、この「相談・苦情への対応」は欠かせない支援なのです。
相談や苦情への対応が、単なる問題解決の手段ではなく、従業員の安心確保、定着促進、そして企業のコンプライアンス維持にも繋がる、非常に重要な義務的支援であることがご理解いただけたかと思います。この大切な役割を具体的にどのように果たしていくべきか、次の章で「企業に求められる具体的な対応」について詳しく見ていきましょう。
企業に求められる具体的な対応

特定技能外国人からの相談や苦情に対して、企業は具体的にどのようなアクションを取るべきなのでしょうか。
法律や関連する運用要領では、単に話を聞くだけでなく、問題解決に向けた積極的なサポート体制を整えることが求められています。この章では、企業に求められる具体的な対応を、5つの重要なポイントに絞って解説していきます。
-
相談しやすい体制の構築
まず基本となるのは、外国人従業員が「困ったときに、いつでも安心して相談できる」と感じられる環境を整備することです。
具体的には、相談を受け付ける担当者(通常は支援責任者や支援担当者を選任します)を明確に決め、その方の氏名や連絡先(電話番号、メールアドレスなど)を外国人従業員全員にしっかりと知らせておく必要があります。相談を受け付ける時間帯にも配慮が求められます。出入国在留管理庁の指針では、平日のうち少なくとも3日以上、さらに土曜日か日曜日のどちらか1日以上、そして就業時間外(例えば夕方や早朝など)でも対応できるような体制を整えることが望ましいとされています。
相談方法も、直接会って話すだけでなく、電話やメール、あるいは普段使っているビジネスチャットツールなど、本人がアクセスしやすい複数の手段を用意しておくと良いでしょう。可能であれば、他の従業員の目を気にせずに落ち着いて話せるような、プライバシーが守られた個室や相談スペースを用意することも、相談のしやすさを高める上で有効です。相談への心理的なハードルをできるだけ低くすることが、問題の早期発見に繋がります。
-
外国人が理解できる言語での対応
寄せられた相談や苦情の内容を正確に理解し、それに対して的確なアドバイスや支援を行うためには、言葉の壁を取り除くことが不可欠です。
そのため、外国人従業員が十分に理解できる言語、原則としてはその方の母国語で相談に応じられる体制を整えることが、法律上も強く求められています。もし社内に対応できる人材がいない場合は、外部の通訳者を必要な時に依頼できる体制を整える、あるいは登録支援機関に支援を委託するなどの対策が必要です。
最近は高性能な機械翻訳ツールも登場していますが、特に込み入った悩みや感情が絡むような相談の場合、微妙なニュアンスまで正確に伝え、共感を示すためには、やはり人を介した通訳の方が望ましい場面も多いでしょう。言葉が通じないことが、相談を諦めさせる原因にならないようにすることが何よりも重要です。
-
相談・苦情内容への適切な対応と助言
実際に相談や苦情を受け付けた際には、その内容に対して迅速かつ誠実に向き合う姿勢が求められます。
「遅滞なく」つまり問題を放置せずに速やかに対応することが基本です。まずは、相談者の話を最後まで注意深く、そして共感を持って聞くことから始めましょう。その上で、状況を整理し、必要な情報を提供したり、具体的な解決策や取るべき行動についてアドバイスを行ったり、時には会社のルールや日本の法律について分かりやすく説明したりします。
頭ごなしに否定したり、問題を軽く扱ったりするような態度は絶対に避けなければなりません。たとえすぐに解決できない難しい問題であっても、会社として問題解決に向けて真摯に取り組む姿勢を示すことが、従業員との信頼関係を維持・強化するために不可欠です。
-
必要に応じた関係行政機関への案内・同行
相談内容によっては、社内での対応だけでは解決が困難な場合や、より専門的な機関の介入が必要となるケースも出てきます。
例えば、労働条件に関する深刻な問題であれば労働基準監督署、賃金未払いに関するトラブルであればハローワークや弁護士への相談、人権に関わる問題であれば法務局の人権擁護機関、在留資格に関する専門的なアドバイスが必要であれば出入国在留管理庁といったように、相談内容に応じて頼るべき公的機関や専門機関があります。
受け入れ企業(または登録支援機関)は、これらの関係機関の連絡先や役割を日頃から把握しておき、必要に応じて外国人従業員にその情報を提供し、どの窓口に相談すべきかを案内する義務があります。さらに、本人が希望し、かつ問題解決のために必要だと判断される場合には、単に情報提供するだけでなく、実際にその機関の窓口まで付き添い(同行支援)手続きが円滑に進むようサポートすることも求められています。
-
相談記録の作成と保管
特定技能外国人から受けた相談や苦情については、その対応内容をきちんと記録として残しておくことが法律で義務付けられています。
この記録は「相談記録書」と呼ばれ、出入国在留管理庁が参考様式(第5-4号)を示しています。記録すべき主な内容は、相談を受けた日付、相談者の氏名、相談内容の具体的な概要、それに対して企業(または登録支援機関)がどのような対応や助言を行ったか、そして対応した担当者の氏名などです。たとえ日常的な小さな相談事であっても、記録を残しておくことが望ましいとされています。この記録は、支援が適切に行われていることの証明になるだけでなく、後日、同様の問題が発生した場合の対応の参考にもなります。
作成した相談記録書は、その外国人従業員の雇用契約期間中、および契約終了日から1年間は、受け入れ企業(または支援委託先の登録支援機関)が責任を持って保管する必要があります。
相談しやすい体制の整備から、言語対応、具体的なアドバイス、行政機関との連携、そして正確な記録管理まで、企業に求められる対応は実に多岐にわたりますね。
相談・苦情対応における注意点
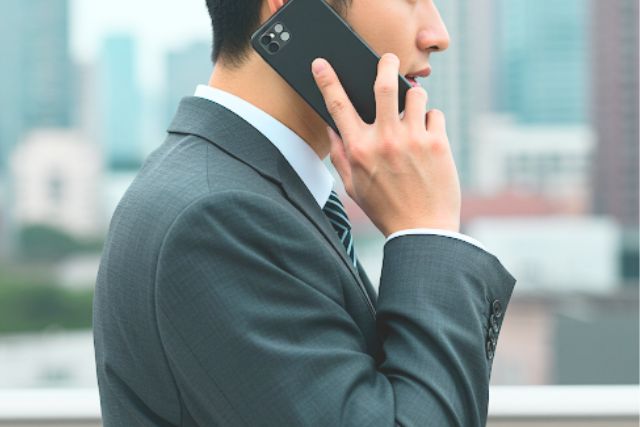
特定技能外国人からの相談や苦情に適切に対応するためには、その具体的な方法を知るだけでなく、実施する上で特に注意すべき点がいくつかあります。
これらは従業員との信頼関係や法令遵守に関わる重要なポイントです。この章では、担当者として必ず心に留めておくべき5つの注意点を解説します。
-
プライバシーと秘密保持への配慮
相談や苦情の内容は、給与のこと、職場での人間関係、個人的な悩みなど、非常にプライベートでデリケートな情報を含むことが想定されます。
したがって、対応にあたっては、相談者のプライバシーを最大限に尊重し、知り得た情報の秘密保持を徹底することが絶対条件です。相談内容を本人の明確な同意なく他の従業員に漏らしたり、社内で噂話の種にしたりするようなことは、絶対にあってはなりません。相談者が「ここで話したことは守られる」と安心して本音を打ち明けられる環境を守ることが、信頼の第一歩です。相談記録書の保管・管理についても、アクセス権限を限定するなど、情報漏洩が起こらないよう厳重な体制を整える必要があります。
-
不利益取扱いの禁止
これも極めて重要な原則です。
特定技能外国人が、勇気を出して相談や苦情を申し出たことを理由として、その従業員に対して解雇、減給、不当な配置転換、あるいは職場での無視や嫌がらせといった、いかなる形であれ不利益な取り扱いを行うことは、法律で固く禁じられています。
「会社に意見を言ったら、後で何をされるか分からない」と従業員が感じてしまうようでは、相談窓口は全く意味をなさなくなってしまいます。企業として、「相談や苦情を申し出ることは従業員の正当な権利であり、それによって不利益を被ることは一切ない」という明確な姿勢を示し、誰もが安心して自分の意見や悩みを伝えられるオープンな職場風土を醸成することが不可欠です。
-
客観的な事実確認と公平な対応
寄せられた相談や苦情、特に複数の人が関わる問題(例えば、同僚とのトラブルや上司の言動に関する苦情など)については、一方の当事者の話だけを信じるのではなく、客観的な事実確認に努めることが重要です。
必要であれば、関係する他の従業員からも慎重に、かつプライバシーに配慮しながら話を聞くなどして、状況を多角的に把握するようにしましょう。対応する担当者自身が感情的になったり、特定の個人に肩入れしたりすることなく、常に中立・公平な立場で問題の本質を見極め、事実に基づいた適切な解決策を模索する姿勢が求められます。
ただし、共感を持って話を聞く姿勢と、客観的に事実を確認することは両立します。まずは相手の気持ちを受け止め、その上で冷静に事実関係を整理することが大切です。
-
対応状況の適切な記録と報告
既述の通り、相談・苦情への対応内容は必ず「相談記録書」に正確かつ具体的に記録し、保管する義務があります。
いつ、誰から、どのような相談を受け、それに対して企業としてどのような対応(助言、調査、関係機関への連絡など)を行い、最終的にどうなったのか、という一連の経緯を時系列で分かりやすく記録します。この記録は、後々「言った」「言わない」の不毛な水掛け論を防ぐためにも役立ちますし、出入国在留管理庁への定期的な報告(2025年4月以降は年1回に頻度変更)や、万が一問題がこじれた際の行政機関への説明責任を果たす上でも、必要不可欠な証拠資料となります。対応が継続中の場合でも、その都度進捗状況を記録しておくことが望ましいでしょう。
-
登録支援機関との連携(委託している場合)
もし、義務的支援の全部または一部を登録支援機関に委託契約している場合は、その機関との緊密な連携体制を構築しておくことが非常に重要になります。
外国人従業員から受けた相談や苦情の内容、企業としての見解や対応方針、登録支援機関に期待する役割などを、迅速かつ正確に共有する必要があります。例えば、「この相談はまず企業側で対応する」「この件は専門的な知見が必要なので支援機関に対応を依頼する」といったように、具体的なケースごとにどちらが主担当として動くのか、役割分担を事前に明確にしておくことが、スムーズな連携の鍵となります。
委託しているからといって企業側の責任が完全に免除されるわけではありません。常に情報を共有し、連携して問題解決にあたるというパートナーシップの意識を持つことが求められます。
プライバシー保護、不利益取扱いの禁止、公平な事実確認、正確な記録、そして委託先とのスムーズな連携。これらは、相談・苦情対応というデリケートな支援を適切に行う上で、必ず守るべき基本ルールです。
「法律的な部分も絡むと、自社での判断や対応は難しいかもしれない」「記録管理や報告義務まで含めると、やはり専門家のサポートが欲しい」と感じられる場合は、決して無理をせず、外部の専門家を頼ることをご検討ください。
まとめ:信頼関係を築くための重要なコミュニケーション
この記事では、特定技能外国人を受け入れる企業に課せられた義務的支援の中でも、特に丁寧な対応が求められる「相談・苦情への対応」について、その目的から具体的な方法、注意すべき点までを詳しく解説してまいりました。
最後に、本記事の重要なポイントをまとめ、この支援が持つ深い意味について改めて考えてみましょう。
特定技能1号外国人に対する「相談・苦情への対応」は、単なる形式的な業務ではなく、彼らが日本で安心して働き、生活するための基盤を支える法律上の重要な義務です。
企業には、相談しやすい体制を整え、本人が理解できる言語で真摯に耳を傾け、適切な助言を行い、必要であれば関係機関への橋渡しをし、その全てを正確に記録・保管するという、一連の責任ある行動が求められます。プライバシーの保護、不利益取扱いの絶対禁止といった原則を守り、常に公平な立場で接することが不可欠です。これらの支援を自社で担うか、専門の登録支援機関に委託するかは、それぞれの企業の体力や方針に応じて慎重に検討すべき課題です。
そして何よりも覚えておきたいのは、この「相談・苦情への対応」が単に問題を処理するためだけのものではない、ということです。むしろ、これは外国人従業員との間に確かな信頼関係を築き、それを育んでいくための、かけがえのないコミュニケーションの機会なのです。
従業員一人ひとりの声に真剣に耳を傾け、問題解決に向けて共に汗を流す姿勢を示すことで「この会社は自分のことを気にかけてくれている」という強い安心感とロイヤリティが生まれます。こうした日々の地道なコミュニケーションの積み重ねこそが、従業員のエンゲージメントを高め、職場への定着を促し、多様な視点を取り入れた企業の活性化にも繋がっていくのではないでしょうか。
私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
関連するオススメ記事はこちら
- 登録支援機関の義務的支援その⑩「定期面談・行政機関への通報」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑨「転職支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑧「日本人との交流促進」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑦「相談・苦情への対応」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑥「日本語学習の機会の提供」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑤「公的手続きへの同行」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その④「生活オリエンテーション」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その③「住居の確保・契約支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その②「出入国時の送迎」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その①「事前ガイダンス」とは?|特定技能外国人

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート