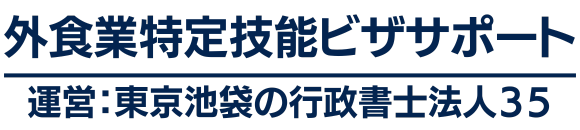登録支援機関の義務的支援その⑧「日本人との交流促進」とは?|特定技能外国人
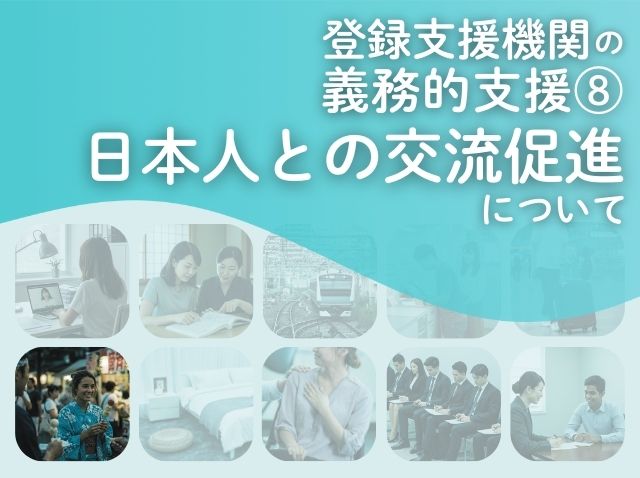
特定技能外国人の方を迎え入れる準備、本当にお疲れ様です。
受け入れ企業に義務付けられている様々な支援項目を確認されている中で「日本人との交流促進」という項目について
「具体的にどんなサポートをすれば良いのだろう?」
「地域のお祭りに参加を促す、といった程度で十分なのかな?」
「そもそも、会社がそこまで関与する必要があるの?」など
戸惑いや疑問を感じている人事担当者の方も少なくないでしょう。
この記事は、まさにそうした疑問にお答えするためにあります。特定技能制度における義務的支援の一つ「日本人との交流促進」とは一体何を指すのか、なぜこの支援が重要視されるのか、そして企業として具体的にどのような方法でサポートを提供すべきなのか、そのポイントを分かりやすく解説していきます。
目次
なぜ必要?特定技能の義務的支援「日本人との交流促進」とは
特定技能外国人の受け入れにあたり「日本人との交流促進」という支援が義務付けられていることをご存知でしょうか。
ここでは、この支援が特定技能制度の中でどのような役割を担い、なぜ企業にとって重要な取り組みなのか、その基本的な考え方と目的を解説していきます。
義務的支援としての位置づけ
特定技能1号の外国人材を受け入れる企業には、10項目の支援を行う義務があります。これが「義務的支援」です。
「日本人との交流促進に係る支援」は、その中の一つとして明確に定められています。これは、住居の確保や各種手続きといった物理的な生活基盤の整備だけでなく、外国人従業員が精神的・社会的に日本コミュニティに溶け込めるようサポートすることを目的とした、非常に大切な支援項目です。例えば、生活オリエンテーションで地域の情報をインプットし、この交流促進支援で実際に地域活動に参加してみる、といった流れで活用されることも想定されています。
「日本人との交流促進」支援の目的と重要性
では、なぜ企業が従業員のプライベートな時間にも関わるような「交流」をサポートする必要があるのでしょうか。その最大の理由は、特定技能外国人が日本社会や地域の中で孤立してしまうのを防ぎ、それによって生じる可能性のあるストレスや不安を和らげ、日本の生活文化への適応をスムーズにすることにあります。
言葉も文化も違う国での生活は、想像以上に大変なことです。
職場と自宅の往復だけの日々が続くと、地域社会との接点が持てず、孤独を感じてしまう外国人の方は決して少なくありません。このような孤立感は、仕事への意欲低下を招くだけでなく、時には深刻な問題に発展するリスクもはらんでいます。
日本人との交流機会を持つことは、こうした状況を改善するための重要な鍵となります。
地域のお祭りやイベントへの参加は、楽しみながら日本の文化や習慣を直接体験できる絶好の機会です。また、職場以外の人々と会話することで、より自然な日本語に触れ、実践的なコミュニケーション能力を磨く場ともなります。地域に顔見知りができれば、日常のちょっとした困りごとを相談できる相手が見つかるかもしれません。
受け入れ企業にとって、この支援は単なるコストではありません。
外国人従業員が地域にうまく溶け込み、日本での生活に満足感を感じながら安心して働けるようになれば、それは従業員の定着率向上に直結します。長期的に活躍してくれる優秀な人材を確保することは、企業にとって大きな財産となるはずです。さらに、社内外での交流を通じて、日本人従業員も異文化への理解を深め、多様な価値観を受け入れるきっかけとなり、結果として職場全体の活性化やより良いチームワークの醸成にも貢献することが期待できるのです。つまり、この支援は、外国人従業員本人、受け入れ企業、そして地域社会の三方にとってメリットのある、意義深い取り組みと言えるでしょう。
「日本人との交流促進」が、単に楽しいイベントに参加させることではなく、外国人従業員の定着と活躍、そして共生社会の実現に向けた大切な支援であることが、お分かりいただけたかと思います。
「なるほど、重要性は分かったけれど、具体的にどんなことをすればいいのだろう?」という疑問が次に湧いてくることでしょう。
次の章では、この支援を具体的にどのように実施していくのか、その方法について詳しく解説します。
具体的に何をすればいい?「日本人との交流促進」の支援内容

「日本人との交流促進」が特定技能外国人にとっても、受け入れ企業にとっても大切であることは分かっていただけたと思います。
では、企業として具体的にどのような行動を取れば、この義務的支援を果たしたことになるのでしょうか。難しく考える必要はありません。出入国在留管理庁の指針などを参考に、企業に求められている具体的なサポート内容を、一つひとつ見ていきましょう。
-
地域コミュニティとの交流機会の情報提供
まず基本となるのは、外国人従業員が地域の人々と触れ合うきっかけとなるような情報を提供することです。
皆さんの会社がある地域や、従業員が住んでいる地域では、きっと市町村役場や地域のボランティアグループ、国際交流協会などが主催する交流イベント(例えば、地域のフェスティバル、スポーツ交流会、文化体験ワークショップなど)が開催されているはずです。こうしたイベントの開催日時、場所、内容、参加方法といった情報を集め、外国人従業員に分かりやすく伝えることが、大切な支援の第一歩となります。
また、日本の地域社会の基盤である自治会や町内会を紹介し、そこが主催するお祭りや清掃活動などの行事について案内することも、地域に自然に溶け込む良いきっかけ作りとなるでしょう。掲示板にポスターを貼ったり、朝礼で紹介したり、多言語での案内を作成したりする方法が考えられます。
-
地域の行事への参加サポート
単に情報を伝えるだけでなく、外国人従業員が「参加してみたい」と思った時に、その背中をそっと押してあげるサポートも必要に応じて行います。
例えば、参加申し込みが必要なイベントであれば、申込書の書き方を一緒に確認したり、手続きを手伝ったりします。初めて参加する行事で、一人では心細いと感じているようであれば、担当者が会場まで一緒に行き(同行支援)行事の楽しみ方や守るべきマナー、注意点などを隣で説明してあげることも、運用要領で求められている立派な支援です。こうした少しのサポートが、参加への心理的な壁を取り払い、実際の交流体験へと繋げる力になります。
-
日本文化を理解するための情報提供
日本人との交流をより有意義なものにするためには、背景にある日本の文化や習慣を知ることが助けになります。
そこで、従業員が働いている地域や住んでいる地域に根ざした伝統的なお祭りや季節の行事(例えば、近所の神社のお祭り、地域の盆踊り大会、文化祭など)について、その由来や意味などを簡単に説明し、参加を促すことも大切な支援となります。地域の歴史や文化に触れる機会を提供することで、外国人従業員の日本への関心や理解が深まり、地域住民との会話のきっかけも生まれやすくなるでしょう。
もし可能であれば、地域の博物館や資料館、歴史的な建造物などを紹介したり、希望があれば一緒に訪れて説明を加えたりすることも、効果的なサポートと言えます。
-
【任意的支援】さらに進んだサポート(推奨される取り組み)
上記の①から③までが、法律で定められた義務的支援の範囲ですが、企業が任意でさらに一歩進んだサポートを行うことも推奨されています。
例えば、外国人従業員が地域のお祭りへの参加を熱望している場合に、業務スケジュールを調整して有給休暇を取得しやすくしたり、勤務時間を柔軟に変更したりする配慮です。また、受け入れ企業自身が音頭を取り、社内で日本人従業員と外国人従業員が気軽に交流できるイベント(例えば、新入社員歓迎会、部署対抗のスポーツ大会、お互いの国の料理を紹介しあう食事会など)を企画・開催することは、職場の活性化と相互理解を深める上で非常に有効です。社内に誰でも自由に使える休憩スペースやカフェコーナーなどを設け、自然なコミュニケーションが生まれる場を作ることも良い取り組みでしょう。
これらは義務ではありませんが、外国人従業員の満足度を高め、「この会社で長く働きたい」と思ってもらうための重要な施策となり得ます。
交流促進支援を効果的に行うためのポイントと注意点

日本人との交流促進支援は、ただ機会を設けるだけでなく、その質を高め外国人従業員にとって本当に有意義な体験となるよう工夫することが大切です。
また、意図せずトラブルを招かないためにも、いくつか注意しておきたい点があります。この章では、交流促進支援をより効果的に、そしてスムーズに進めるための重要なポイントを5つご紹介します。
-
外国人本人の意思と興味の尊重
まず最も基本となるのは、交流活動への参加を強制しないという姿勢です。
会社が良かれと思って企画した社内イベントや、地域で評判のお祭りであっても、本人が興味を持てなかったり、参加することに心理的な抵抗を感じたりするかもしれません。無理に参加させることは、かえって本人のストレスとなり、逆効果になる可能性が高いです。大切なのは、支援を始める前に、日頃のコミュニケーションや定期的な面談を通じて、本人が「どんなことに興味があるのか」「どんな形の交流なら参加してみたいか」といった意向を丁寧に聞き取ることです。その上で、本人の希望を最大限尊重し、自発的に参加したいと思えるような機会を提案・サポートすることが、実りある交流への第一歩となります。あくまで主役は外国人本人である、という視点を忘れないようにしましょう。
-
文化・宗教・習慣への配慮
多様な国や地域から来日する特定技能外国人を受け入れる際には、それぞれの文化、宗教、生活習慣への深い理解と配慮が不可欠です。
交流イベントを企画したり、地域の行事を紹介したりする際には、その内容が特定の文化や宗教的信条に偏っていないか、本人のバックグラウンドに照らして不快感を与える可能性がないかを事前に確認しましょう。例えば、食事を提供する場であれば、イスラム教徒向けのハラル食や、ヒンドゥー教徒、ベジタリアンなど、食事制限を持つ従業員への対応が可能かを確認・準備する必要があります。また、飲酒が伴う懇親会などは、文化や宗教によっては参加しにくいと感じる人もいることを理解しておくべきです。全ての従業員が安心して、気持ちよく参加できるような、インクルーシブ(包括的)な視点を持った企画や情報提供を心がけることが重要です。
-
一方的な「日本文化の押し付け」にならないように
日本人との交流促進は、日本文化を一方的に教え込む場ではありません。
その目的は、あくまで「相互理解」を深めることにあります。日本の素晴らしい文化や習慣を紹介することはもちろん大切ですが、それが「日本のやり方が正しい」といった押し付けになってしまわないよう、細心の注意が必要です。大切なのは、相手の国の文化や習慣にも敬意を払い、私たち日本人自身も異文化から学ぶという謙虚な姿勢を持つことです。例えば、社内イベントでお互いの国の料理を紹介しあったり、それぞれの国の祝日や習慣について話を聞く機会を設けたりするのも良いでしょう。交流は、お互いの違いを認め合い、尊重し合いながら、共に楽しむ場であるという認識を持つことが、真の国際交流の基本です。
-
継続的な機会提供の意識
外国人従業員が地域社会や職場に溶け込み、日本人との間に自然な人間関係を築くには、ある程度の時間が必要です。
そのため、交流促進支援は、一度きりの特別なイベントで終わらせるのではなく、年間を通じて継続的に機会を提供していくという意識が大切になります。地域のお祭りや季節ごとのイベント、社内での気軽なランチ会やスポーツ同好会など、大小様々な形で定期的に交流の場があることで、従業員は徐々に人間関係を広げ、コミュニティへの帰属意識を高めていくことができます。
担当者としては、自治体の広報誌やウェブサイト、地域のNPO団体の情報などに常にアンテナを張り、イベント情報を定期的に収集・更新し、社内で共有する仕組みを作っておくと良いでしょう。
-
費用負担について
最後に、費用負担に関するルールを再確認しておきましょう。
義務的支援として企業が行う、交流イベントに関する情報提供、参加手続きの補助、必要に応じた同行など、これらの「機会提供」に直接かかる費用(担当者の人件費や交通費など)は、受け入れ企業が負担しなければなりません。
これを本人に請求することはできません。一方で、イベントそのものへの参加費や、交流会での飲食代などについては、必ずしも企業が全額負担する義務はありません。原則としては本人負担となりますが、企業が福利厚生の一環として任意で補助することは、従業員の参加意欲を高め、大変喜ばれるでしょう。ただし、費用負担については、事前に誰が何を負担するのかを明確に取り決め、従業員に誤解のないようにしっかりと伝えておくことが、後のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。
本人の意思を尊重し、文化に配慮し、継続的に、そして費用ルールを守って支援を行うこと。これらのポイントを押さえることで、日本人との交流促進支援は、単なる義務を超え、外国人従業員の定着と活躍を促す有効な施策となります。
まとめ:交流促進で、より良い職場と地域社会を
この記事では、特定技能1号外国人を受け入れる企業に義務付けられている支援の中でも、特に「日本人との交流促進」に焦点を当て、その目的、具体的な支援方法、そして成功のためのポイントを詳しく解説してまいりました。
最後に、本記事でお伝えした重要な点を振り返り、この支援が持つ豊かな可能性について改めて考えてみましょう。
「日本人との交流促進」は、特定技能制度における大切な法的義務であり、外国人従業員が孤立することなく、日本社会にスムーズに溶け込んでいくための重要な架け橋となる支援です。企業には地域のイベント情報を提供したり、参加の手続きを手伝ったり、時には行事に同行したりといったサポートが求められます。
任意ではありますが、企業自身が交流の場を設けることも非常に有効です。実施にあたっては、外国人本人の意思を第一に尊重し、多様な文化や習慣に配慮すること、そして単発ではなく継続的な視点を持つことが成功の鍵となります。
こうした交流促進の取り組みは、単に義務を果たすという側面を超え、関わる全ての人々にとって価値あるものとなり得ます。外国人従業員にとっては、生きた日本語に触れ、日本の文化を肌で感じ、地域に友人を作ることで、日本での生活はより安心で充実したものになるでしょう。
受け入れ企業にとっては、従業員の定着率が向上し、異なる視点を持つ人材との交流を通じて、職場全体の活性化や新たなアイデアの創出に繋がることも期待できます。そして地域社会にとっては、多様な人々が互いを理解し尊重し合う、より豊かで活力ある共生社会への大切な一歩となるのです。
私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
関連するオススメ記事はこちら
- 登録支援機関の義務的支援その⑩「定期面談・行政機関への通報」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑨「転職支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑧「日本人との交流促進」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑦「相談・苦情への対応」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑥「日本語学習の機会の提供」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑤「公的手続きへの同行」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その④「生活オリエンテーション」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その③「住居の確保・契約支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その②「出入国時の送迎」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その①「事前ガイダンス」とは?|特定技能外国人

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート