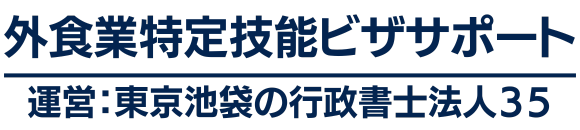【特定技能】外食業協議会への加入申請について|手続き・必要書類・注意点を解説

深刻な人手不足は、多くの外食企業にとって喫緊の課題ではないでしょうか。
その解決策として、特定技能外国人材の活用に注目が集まっています。
貴社でも、新たな戦力としての採用を具体的に検討されているかもしれませんね。ただし、特定技能外国人を受け入れる上で、必ずクリアしなければならない手続きがあります。それは「食品産業特定技能協議会」への加入手続きです。この協議会への加入は法律上の義務であり、特に初めて特定技能外国人を受け入れる企業様は、在留資格を申請する「前」に加入を済ませる必要があります。
「具体的にいつまでに申請すればいいの?」
「手続きはどう進める?」
「どんな書類が必要になるのだろう…」など、担当者様は多くの疑問や不安を抱えていらっしゃるかもしれません。
この記事では、外食業の企業様が特定技能協議会へスムーズに加入申請できるよう、具体的な手続きの流れから、準備すべき書類、そして見落としがちな注意点まで、分かりやすく徹底的に解説いたします。本記事を最後までお読みいただければ、複雑に思える協議会加入申請の全体像が掴め、安心して外国人採用の準備を進めることができるようになります。
目次
なぜ必要?外食業で特定技能外国人を採用するなら「協議会加入」が必須です
この章では、特定技能外国人を受け入れる外食企業の皆様にとって、なぜ「食品産業特定技能協議会」への加入がこれほどまでに重要であり、そして法的に必須とされているのか、その理由と背景について詳しくご説明いたします。
特定技能制度を正しく理解し、活用するための大切な第一歩となりますので、ぜひご確認ください。
特定技能制度と協議会の役割とは?
まず、特定技能制度そのものについて、基本を確認しましょう。
この制度は、国内での人材確保が特に難しいとされる産業分野において、即戦力となる専門性や技能を持つ外国人材の受け入れを促進するために設けられました。皆様が事業を展開されている外食業も、まさにその対象分野の一つであり、人手不足解消の有効な手段として活用が進んでいます。ただ、国としては、単に労働力を確保するだけでなく、この制度が適正に運用され、日本で働く外国人の方々が不利益を被ることなく、安心して活躍できる環境を整えることを非常に重要視しているのです。そのための仕組みが「特定技能協議会」というわけです。協議会は、各分野を管轄する省庁(外食業の場合は農林水産省)が中心となり、実際に外国人材を受け入れる企業、そして必要に応じて彼らをサポートする登録支援機関などが連携するための場です。
ここでは、最新情報の共有現場での課題や成功事例の共有、ルール違反や不正行為の防止策の検討、法令遵守のための啓発活動などが行われます。いわば、特定技能制度という仕組みを関係者全員で適切に、そして健全に運営していくための、官民一体となった協力体制と考えると分かりやすいでしょう。外国人材が不当な労働条件で働かされたり、制度が意図しない形で利用されたりするのを防ぎ、業界全体の信頼性を高める役割を担っています。
外食業が加入するのは「食品産業特定技能協議会」
特定技能制度には、現在12の対象分野がありますが、それぞれの分野ごとに専門の協議会が設置されています。
例えば、
建設業なら「建設特定技能受入計画審査・指導協議会」
介護なら「介護分野における特定技能協議会」といった具合です。
では、レストラン、居酒屋、カフェ、ファストフード店など、外食業を営む企業様はどの協議会に加入する必要があるのでしょうか。
正解は「食品産業特定技能協議会」です。この協議会は、少し特徴的で、「外食業分野」と「飲食料品製造業分野」という密接に関連する二つの産業分野を一つの組織で管轄しています。したがって、貴社が調理師、ホールスタッフ、店舗管理者などの職種で特定技能外国人を受け入れる計画があるのであれば、この「食品産業特定技能協議会」への加入手続きが必須となります。
この協議会は農林水産省が所管しており、外食・飲食料品製造の両分野に共通する課題への対応や、関連情報の提供などを行っています。「うちの業種はどこの協議会だろう?」と迷う必要はありません。外食サービスを提供する企業であれば、加入すべきは「食品産業特定技能協議会」です。この点をしっかり押さえておきましょう。
加入は法律上の義務!加入しない場合のリスク
ここで強調しておきたいのは、特定技能協議会への加入は、「推奨」や「任意参加」といった類のものではない、ということです。
これは、出入国管理及び難民認定法(入管法)および関連する省令などによって明確に定められた、特定技能外国人を受け入れる企業が必ず果たさなければならない法的義務なのです。
国がこの制度の適正な運用と、日本で働く外国人の方々の保護をいかに真剣に考えているかの証左とも言えます。では、もしこの義務を果たさず、協議会に未加入のまま特定技能外国人を雇用しようとしたり、雇用し続けたりした場合、どのような結果を招くのでしょうか。
それは、企業にとって看過できない重大なリスクにつながります。最も直接的な影響は、特定技能外国人の在留資格に関する申請が一切認められなくなることです。
つまり、せっかく時間とコストをかけて採用が決まった優秀な人材が、日本で働くためのビザを取得できない、あるいは更新できないという事態が発生します。採用計画が根本から覆されることになりかねません。さらに、すでに特定技能外国人を雇用している状況で未加入が発覚した場合、指導や勧告を受けるだけでなく、悪質なケースや改善が見られない場合には、特定技能外国人の受け入れ自体ができなくなったり、受け入れ機関としての認定そのものが取り消されたりする可能性もゼロではありません。
これは単なる手続き上の問題ではなく、法令違反として企業の社会的信用を大きく損なうことにも繋がります。したがって、コンプライアンスを遵守し、安定的に外国人材を受け入れていくためには、協議会への加入手続きを確実に行うことが絶対に必要なのです。
ここまでお読みいただき、協議会加入の必要性は十分にご理解いただけたことと思います。
【重要】いつまでに加入?協議会への加入タイミングについて

このセクションでは、食品産業特定技能協議会への加入を「いつまでに行うべきか」という手続き上、非常にクリティカルなタイミングの問題について詳しく解説します。
重要な点として、この加入タイミングに関するルールが最近変更されています。この変更を知らずに手続きを進めてしまうと、予定していた外国人材の受け入れスケジュールに遅れが生じる可能性もありますので、ここでしっかりと最新情報を確認していきましょう。
従来のルール:「受け入れ後4ヶ月以内」が基本だった
これまでの基本的なルールでは、特定技能外国人を受け入れた企業は、その外国人材が日本で就労を開始した日(=受け入れ日)から起算して4ヶ月以内に、管轄の特定技能協議会に加入することが求められていました。
つまり、先に外国人材を受け入れて業務を開始し、その後、定められた期間内に協議会への加入手続きを行う、という流れが一般的でした。現在でも、例えば2024年6月14日以前にすでに特定技能外国人を受け入れていた企業が、その後の手続きとして加入する場合などには、このルールが適用されるケースも考えられます。
しかし、これから新たに特定技能外国人を受け入れようとお考えの企業様にとっては、注意すべき新しいルールが適用されます。
【最重要】初めて特定技能外国人を受け入れる企業のルール変更(2024年6月15日〜)
ここが今回の最も重要なポイントです。貴社がこれから初めて特定技能外国人を受け入れるという場合、2024年6月15日をもって協議会への加入タイミングに関する運用が大きく変更されました。
結論から申し上げますと、従来の「受け入れ後」の加入ではなく、「在留資格の申請手続きを行う前」に食品産業特定技能協議会への加入を完了させている必要が生じたのです。
これはつまり、外国人材の採用が決定し、入国管理局に対して在留資格認定証明書(海外から呼び寄せる場合)や在留資格変更許可(国内にいる留学生などを採用する場合)の申請を行う、その申請手続きよりも「前」の段階で、貴社が協議会の正式なメンバーとして登録されていなければならない、ということを意味します。手続きの順番が根本的に変わった、とご理解ください。
在留資格申請「前」の加入が必須になった理由
なぜ、このように手続きの順番が変更されたのでしょうか。
それは、在留資格の申請時に提出が求められる書類が変わったためです。2024年6月15日以降の申請においては、入国管理局へ提出する書類の中に、「受け入れ企業が食品産業特定技能協議会の構成員であることを証明する書類」(具体的には、協議会から発行される加入証明書などが該当します)が含まれることになりました。
この証明書がなければ、在留資格申請に必要な書類が揃っていないと見なされ、申請が受理されなかったり、審査が開始されなかったりするリスクがあります。つまり、加入証明書を入手するために、必然的に在留資格申請の前に協議会への加入を済ませておく必要があるのです。このルール変更を知らずに従来の感覚で進めてしまうと、いざビザ申請という段階で「書類が足りない!」となり、採用計画全体に遅れが生じかねません。
手続き期間を考慮した早めの行動を
協議会への加入申請を行ってから、審査を経て正式に加入が認められ、加入証明書が発行されるまでには、一定の期間が必要です。一般的には2週間から1ヶ月程度かかると言われていますが、申請が集中する時期などによっては、さらに時間がかかる可能性も考慮すべきでしょう。そのため、特定技能外国人の採用が決まったら、できるだけ速やかに協議会への加入申請手続きに着手することが、スムーズな受け入れを実現するための鍵となります。在留資格の申請スケジュールから逆算して、余裕を持った計画を立てることが非常に重要です。
加入タイミングに関するルールの変更点、お分かりいただけましたでしょうか。
特に「初めて」特定技能外国人を受け入れる際には、手続きの順番を間違えないよう、十分にご注意ください。「証明書の発行まで、具体的にどれくらい時間がかかるのだろう?」「申請に必要な情報がまだ全部揃っていない場合はどうすれば?」など、個別のケースに応じた疑問や心配事も出てくるかと思います。
食品産業特定技能協議会への加入申請 完全ステップガイド
ここからは、食品産業特定技能協議会への具体的な加入申請手続きを、一つ一つのステップに沿って分かりやすくご案内します。申請は主にオンラインで行いますので、インターネットに接続されたパソコンをご用意いただくとスムーズに進められます。
-
食品産業特定技能協議会への加入申請Step 1:農林水産省の協議会公式ページを探してアクセス
申請手続きのスタート地点は、農林水産省のウェブサイト内にある食品産業特定技能協議会の専用ページです。
まず、お使いのウェブブラウザを開き、GoogleやYahoo!などの検索エンジンを利用しましょう。「農林水産省 食品産業特定技能協議会」や「外食 特定技能 協議会 申請」といったキーワードで検索を実行してください。検索結果の中から、農林水産省(maff.go.jp)のドメインを持つ公式サイトへのリンクを見つけ出し、クリックします。
協議会のページにたどり着いたら「入会申請はこちら」や「オンライン申請フォーム」といった趣旨の案内やボタンを探し、クリックして申請フォームのページへと進んでください。
-
食品産業特定技能協議会への加入申請Step 2:オンライン加入申請フォームに必要事項を正確に入力
申請フォームのページが開いたら、ここからが具体的な入力作業です。
画面に表示される項目に従って、貴社の情報を丁寧に入力していきましょう。少し項目が多いかもしれませんが、一つ一つ確認しながら進めれば大丈夫です。
まず、貴社に関する基本的な情報を入力します。会社名(法人の場合)や屋号(個人事業主の場合)、代表取締役の氏名、そして法人番号(13桁)は必須項目となるでしょう。もし個人事業主様で法人番号がない場合は、フォーム内の指示(例えば「無」と入力するなど)に従って対応してください。
次に、労働保険番号や、本社所在地、そして実際に特定技能外国人の方が働くことになる店舗や事業所の名称・所在地も正確に入力します。担当者様の氏名、所属部署、電話番号、そして重要な連絡手段となるメールアドレスも忘れずに入力しましょう。さらに、会社の規模を示す従業員数や、事業内容を示す日本標準産業分類コードなども選択または入力する項目があると考えられます。これらの情報は、協議会が受け入れ企業の状況を正確に把握するために用いられます。
加えて、受け入れを予定している、または既に受け入れている特定技能外国人の方の情報を入力する欄も設けられているはずです。氏名(パスポート記載のアルファベット表記)、国籍、生年月日、在留カード番号、就労予定の店舗名などを入力します。
ここで「まだ採用候補者が決まっていない」「内定は出したがビザ申請前で在留カード番号が分からない」といった状況もあるかと存じます。提供された情報によれば、このような場合でも、外国人情報の欄を空欄にしたり、未定である旨を記載したりして申請を進めることが可能なようです。ただし、運用は変更される可能性もあるため、申請フォームの注意書きをよく読むか、不明点は事前に協議会事務局へ問い合わせるのが確実です。
特に、初めての受け入れで在留資格申請前に加入が必要な場合は、外国人材の情報がある程度固まった段階で申請を進める方が、後の手続きがスムーズになる可能性が高いです。
-
食品産業特定技能協議会への加入申請Step 3:申請完了メールを確認し、「誓約書」を準備・返送する
オンラインフォームの全ての項目を入力し、送信ボタンをクリックしても、まだ手続きは完了ではありません。
むしろ、ここからが重要なステップです。申請が無事に受け付けられると、フォームに入力した担当者様のメールアドレス宛に、通常数日以内に協議会の事務局から確認メールが届きます。このメールは迷惑メールフォルダに入ってしまう可能性もあるため、注意深く確認してください。メールの内容には、申請を受け付けた旨と、次に行うべき手続きが記載されています。
特に重要なのが「特定技能外国人の受入れに関する誓約書」に関する指示です。多くの場合、誓約書のテンプレートファイル(WordやPDF形式など)がメールに添付されているか、ダウンロードできるURLが記載されています。この誓約書は、貴社が特定技能制度の関連法令やルールを遵守し、外国人材に対して適切な雇用管理と支援を行うことを正式に約束する書類です。ダウンロードした様式に従い、会社名、所在地、代表者名などを正確に記入し、社印を押印するなどの対応(指定された形式に従ってください)を行います。完成した誓約書は、スキャンするなどしてPDFファイルに変換し、事務局から届いたメールに添付して返信します。
返信する際のメールの件名や本文についても、事務局からの指示があればそれに従ってください。この誓約書の提出をもって、協議会による正式な加入審査がスタートします。
-
食品産業特定技能協議会への加入申請Step 4:審査完了の連絡と「加入証明書」の受け取り
提出された誓約書の内容などを基に協議会事務局で加入審査が行われます。審査が無事に完了し、貴社の加入が承認されると、その旨を知らせるメールが担当者様宛に届きます。そして、このメールには通常、在留資格申請に必要となる「加入証明書」(協議会の構成員であることを証明する公的な書類)がPDFファイルなどで添付されています。
この加入証明書は、前述の通り、特に初めて特定技能外国人を受け入れる企業様が在留資格申請を行う際に、入国管理局へ必ず提出しなければならない重要書類です。受け取ったら内容を確認し、大切に保管してください。これで、一連の協議会加入申請手続きは完了となります。お疲れ様でした。
以上、食品産業特定技能協議会への加入申請手続きを4つのステップに分けてご説明しました。流れを掴んでいただけましたでしょうか。一つ一つの作業はそれほど複雑ではありませんが、入力する情報の正確性や、誓約書の準備、メールの確認など、確実にこなす必要があります。
失敗しないためのチェックリスト!協議会申請の注意点とQ&A
食品産業特定技能協議会への加入申請、その手続きの流れは掴んでいただけたかと思います。
この章では申請プロセスをより確実に、そしてスムーズに進めるために、事前に知っておきたい重要な注意点と、企業の担当者様から特によくいただくご質問とその回答をまとめてご紹介します。これらのポイントを押さえておくことで、手続き中の不安を減らし、より安心して特定技能外国人の受け入れ準備を進めることができるでしょう。
-
食品産業特定技能協議会への加入申請注意点①:申請前にしっかり準備!必要な情報・書類リスト
何事も準備が大切です。
協議会へのオンライン申請をスムーズに進めるためには、入力に必要な情報をあらかじめ手元に揃えておくことを強くお勧めします。いざフォーム入力を始めてから「あの情報どこだっけ?」と探す手間を省くためです。具体的に準備しておきたいのは、まず貴社の正確な法人名(または個人事業主としての屋号)代表者様の氏名、登記簿謄本などで確認できる本社所在地、そして13桁の法人番号です。
個人事業主様の場合は法人番号がありませんので、申請フォームの指示に従ってください。また、労働保険番号も必要となる場合があります。さらに、実際に特定技能外国人の方が勤務する店舗や事業所の名称と所在地、連絡先として担当者様の氏名、部署、電話番号、そして確実に連絡が取れるメールアドレスも必須です。
加えて、従業員数や事業内容を示す日本標準産業分類の該当コードなども確認しておきましょう。受け入れる外国人材が決まっている場合は、その方の氏名、国籍、生年月日、在留カード番号(もしあれば)なども整理しておくと入力が捗ります。そして、申請後に提出が必要となる「誓約書」
どのような内容か、事前に農林水産省のウェブサイトなどで様式を確認し、内容を理解しておくと、後の手続きがスムーズになります。これらの事前準備が、申請作業の時間短縮とミスの防止に繋がります。
-
食品産業特定技能協議会への加入申請注意点②:「変更」があったら忘れずに届出を!
無事に協議会への加入が完了しても、それで終わりではありません。
加入時に申請した情報に変更が生じた場合は、その都度、速やかに協議会へ変更の届出を行う義務があります。例えば、会社の本店所在地が移転した場合、代表者が交代した場合、申請時の担当者が変更になった場合などが該当します。
また会社の商号(名称)変更や、受け入れる特定技能外国人の情報に関する変更(新たに追加で雇用した場合や、雇用していた方が離職した場合など)も、届け出が必要となるケースが多いです。どのような変更事項が届出の対象となるか、具体的な手続き方法や提出書類については、食品産業特定技能協議会の規約や、農林水産省のウェブサイトで必ず確認してください。
この変更届を怠ってしまうと、協議会からの重要なお知らせが届かなくなったり、制度の適正な運用を妨げていると見なされたりする可能性があります。登録情報は常に最新の状態を維持するよう、社内での情報共有体制を整えておくことが大切です。
-
食品産業特定技能協議会への加入申請注意点③:気になる費用は?加入は「無料」です!
様々な許認可申請や手続きには費用が伴うことが多いですが、特定技能協議会への加入に関しては、嬉しいお知らせがあります。
現時点において、食品産業特定技能協議会への加入にあたって、入会金や年会費といった費用は一切発生しません。これは、外食業分野に限らず、特定技能制度における全ての分野の協議会で共通の扱いです。費用負担がないことは、特に中小規模の事業者様にとっては安心材料の一つとなるでしょう。ただし、制度は将来的に変更される可能性も皆無ではありません。
念のため申請手続きを行う際には、農林水産省の公式ウェブサイト等で、費用に関する最新の情報を確認することをお勧めしますが、基本的には無料で加入できると考えて問題ありません。
-
食品産業特定技能協議会への加入申請注意点④:どれくらいかかる?審査期間の目安
「申請してから加入証明書が届くまで、どのくらいの期間を見ておけばいいの?」これは、採用スケジュールを立てる上で非常に重要な情報ですよね。
明確な期間が公表されているわけではありませんが、一般的に、オンラインで申請情報を送信し、その後のメールでのやり取り(誓約書の提出など)を経て、協議会事務局での審査が完了し、加入が承認されるまでには、おおよそ2週間から1ヶ月程度を見込んでおくのが妥当とされています。しかし、これはあくまで目安の期間です。
申請内容に確認事項があったり、書類に不備があったりした場合には、さらに時間がかかることもあります。また、年度末や制度変更の直後など、申請が集中する時期には、通常よりも審査に時間を要する可能性も考慮しておくべきでしょう。特に、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、加入証明書がないと在留資格の申請に進めません。外国人材の入社予定日から逆算し、十分な余裕をもって、できるだけ早めに加入申請に着手することを強くお勧めします。
Q&A:よくあるご質問にお答えします
最後に、特定技能協議会への加入に関して、企業の担当者様から特に多く寄せられる疑問点について、Q&A形式でお答えします。
Q1. 特定技能外国人の日常生活や仕事上の支援は、すべて登録支援機関に委託する予定です。この場合でも、私たち受け入れ企業が協議会に加入する必要はありますか?
A1. はい、必要です。
外国人材への支援業務を登録支援機関に全部委託する場合であっても、特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)自身の協議会への加入義務はなくなりません。受け入れ企業と登録支援機関は、それぞれが協議会に加入する義務を負っています。
Q2. Q1の回答に関連して、私たちが契約する登録支援機関も、やはり協議会に加入していないといけないのでしょうか?
A2. その通りです。
特定技能外国人の支援を行う登録支援機関は、支援を行う特定技能外国人が属する分野の協議会に加入することが義務付けられています。つまり、貴社が外食業の特定技能外国人の支援を委託する場合、その登録支援機関は「食品産業特定技能協議会」の構成員でなければなりません。委託契約を結ぶ前に、登録支援機関が適切に協議会へ加入しているかを確認することをお勧めします。
Q3. 当社ではレストラン事業(外食業)に加えて、セントラルキッチンでの食品製造(飲食料品製造業)も行っており、両方の分野で特定技能外国人を受け入れたいと考えています。手続きは別々に行う必要がありますか?
A3. いいえ、一つの手続きで両分野をカバーできます。
食品産業特定技能協議会は、「外食業分野」と「飲食料品製造業分野」の両方を管轄しているため、一度の加入申請で、両分野の受け入れ企業として登録することが可能です。申請フォームや誓約書には、両方の分野で受け入れを行う(または予定している)旨を正確に記載するようにしてください。なお、参考情報として、登録支援機関が2025年3月1日以降に新規で加入する場合は、両分野での登録が必須となったようです。
Q4. 申請すれば必ず協議会に加入できるのでしょうか?加入が認められないことはありますか?
A4. 基本的には、特定技能外国人の受け入れ機関としての要件を満たし、適切に申請を行えば加入できますが、認められないケースも存在します。
例えば、申請内容に虚偽があったり、重大な不備が解消されなかったりする場合。また、過去5年以内に労働関連法規や入管法に関する重大な違反があったり、税金の未納があったりするなど、受け入れ機関としての適格性を欠くと判断される場合は、加入が認められない可能性があります。さらに、届け出た業務内容が特定技能「外食」の活動範囲から逸脱していると判断された場合も同様です。法令を遵守し、誠実に対応することが加入の前提となります。
協議会加入に関する様々な注意点や疑問について解説してきましたが、クリアになりましたでしょうか。手続きは無料ですが、守るべきルールやタイミングがあり、特に初めての受け入れでは事前の準備と計画性が求められます。
協議会だけじゃない!特定技能外国人受け入れに必要なその他の要件

食品産業特定技能協議会への加入は、特定技能外国人材を貴社に迎えるための、いわば「入場券」のようなものですが、それだけでゴールではありません。
実際に外国人材を受け入れ共に働いていくためには、企業として満たすべき重要な要件が他にもいくつか存在します。
この章では、協議会加入と並行して、あるいは加入後に必ず確認・整備しておくべき主要な受け入れ要件について、ポイントを絞ってご説明します。これらの準備を怠ると、せっかく採用が決まっても受け入れが進まない、あるいは後々トラブルに発展する可能性もありますので、しっかりと内容を確認していきましょう。
適切な雇用契約の締結:公正な労働条件の約束
外国人材を受け入れる上で、最も基本となるのが、労働条件を明確に定めた適正な雇用契約を結ぶことです。
特に注意すべきは給与水準です。特定技能制度では、「日本人と同等額以上の報酬」を支払うことが厳格に定められています。同じ仕事内容・責任範囲で働く日本人従業員がいる場合、その方の給与水準を下回ることは許されません。
これは、国籍による不当な差別をなくし、外国人材が安定した生活を送れるようにするための根幹となるルールです。また、雇用形態は必ず「直接雇用」でなければならず、派遣労働者として受け入れることはできません。勤務時間についても、週30時間以上のフルタイムが原則となります。
もちろん労働基準法で定められている休憩時間の確保、法定休日の付与、そして年次有給休暇の権利も、日本人と同様に保障する必要があります。さらに、万が一の病気や怪我、失業に備えるための社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入も、企業と労働者双方の義務です。
これらの条件を全て満たした上で、内容を詳細に記載した雇用契約書を作成し、外国人材本人に母国語等で十分に説明し、理解・合意を得た上で締結することが、信頼関係の基礎となり、将来的なトラブルを未然に防ぐことに繋がります。
外国人材への支援体制:日本での活躍をバックアップ
言葉や文化、生活習慣の異なる日本で、外国人材が能力を発揮し、安心して働き続けられるように、受け入れ企業には手厚い支援を行うことが法律で義務付けられています。
その支援内容を具体的にまとめたものが「1号特定技能外国人支援計画」であり、この計画を作成し、着実に実行していく必要があります。支援計画に盛り込むべき内容は多岐にわたります。
例えば、入社前には日本のルールや雇用契約の内容について説明する事前ガイダンスを実施します。来日時には空港への出迎え、帰国時には空港への見送りも必要です。日本での生活基盤を整えるため、住居探し(アパート契約など)のサポートや、銀行口座の開設、携帯電話の契約、役所での住民登録といった手続きへの同行支援も行います。
入社後には、ゴミの出し方や交通ルール、災害時の対応などを教える生活オリエンテーションを実施し、必要に応じて日本語学習の機会(日本語教室の情報提供や学習教材の提供など)も提供します。職場で困ったことや生活上の悩みがあれば、母国語で相談できる相談・苦情対応の窓口を設け、適切に対応することも重要です。
さらに、地域のお祭りやイベントへの参加を促すなど、地域社会との交流を促進することも求められます。これらの支援は、受け入れ企業内に支援担当者を置いて自社で直接行うことも可能ですが、専門的な知識や多言語対応が必要な場面も多いため、国から認定を受けた「登録支援機関」に全ての支援業務を委託することもできます。
ただし、委託した場合でも、支援が計画通り適切に実施されているかを監督する最終的な責任は、受け入れ企業が負うことを忘れてはなりません。充実した支援は、外国人材の定着率向上や生産性向上に直結する、企業にとっても重要な投資と言えるでしょう。
法令遵守の徹底:信頼される受け入れ企業であるために
特定技能外国人を受け入れる企業であるためには、当然ながら、日本の法律やルールをしっかりと守っていることが大前提となります。
特に、従業員の権利を守るための労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などの労働関係法令を遵守することは絶対条件です。長時間労働の強制、残業代の未払い、不当な解雇などは決してあってはなりません。安全で健康的な職場環境を整備することも重要です。
また、外国人雇用に関する出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められた各種届出(例えば、雇用契約の内容変更や、外国人が離職した場合の届出など)を、定められた期限内に正確に行う必要があります。さらに、企業としての社会的責任として、法人税、消費税、従業員の所得税(源泉徴収)など、納付すべき税金をきちんと納めていることも、受け入れ機関としての適格性を判断する上で見られます。
加えて、過去5年以内に、入管法や労働関係法令に関して重大な違反(例えば、不法就労助長罪や悪質な労働基準法違反など)を起こしていないこと、そして安定した経営状況であること(極端な債務超過状態でないことなど)も求められます。日頃からコンプライアンス体制を整備し、クリーンな企業経営を心がけることが、特定技能制度を活用するための基本中の基本です。
協議会への加入手続きと並行して、これらの受け入れ要件を一つ一つ確認し、整備していく必要があります。
まとめ:複雑なルールを正しく理解し、スムーズな外国人採用を実現
この記事を通じて、外食業の企業様が特定技能外国人を受け入れる上で避けて通れない「食品産業特定技能協議会」への加入について、その重要性、最新の加入タイミング、具体的な申請ステップ、注意点、そして協議会加入以外に満たすべき要件まで、幅広く解説してまいりました。特定技能制度は、人手不足が深刻な外食業界にとって、優秀な人材を確保するための強力な選択肢となり得ます。しかし、その制度を有効に活用するためには、定められたルールや手続きを正確に理解し、一つ一つ着実に実行していくことが何よりも重要です。特に、協議会への加入は法的な義務であり、初めての受け入れに際しては在留資格申請の「前」に完了させておく必要があるという点は、計画立案における最重要ポイントです。申請から承認までには時間もかかりますので、採用スケジュールをしっかりと見据え、余裕を持った準備と情報収集を心がけることが、スムーズな受け入れ成功への近道となるでしょう。本記事が、貴社の特定技能外国人材活用の一助となっていれば、これほど嬉しいことはありません。
私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
関連するオススメ記事はこちら
- 外食業「特定技能1号技能測定試験」とは?
- 特定技能ビザで働く【外国人】のメリット・デメリットについて
- 【JLPT】特定技能ビザ取得に必要な日本語能力試験の種類・レベル・対策・合格のコツとは?
- 登録支援機関とは? 特定技能外国人の支援機関です|費用・選び方・行政書士への委託メリットを解説
- 登録支援機関の義務的支援その③「住居の確保・契約支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援・任意的支援とは?人事担当者が知るべき違い・費用・選び方を徹底解説
- 特定技能外国人の転職について|要件・手続き・注意点を解説
- 「特定技能1号ビザ」の在留期間は何年なのか?|更新・延長・満了後の選択肢について解説
- 登録支援機関の義務的支援その⑦「相談・苦情への対応」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑩「定期面談・行政機関への通報」とは?|特定技能外国人

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート