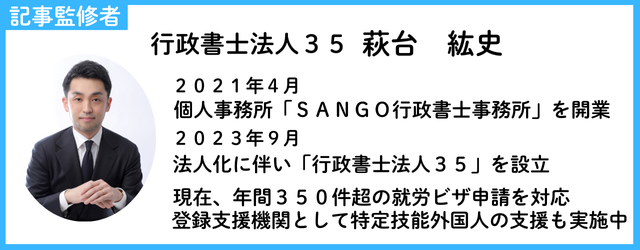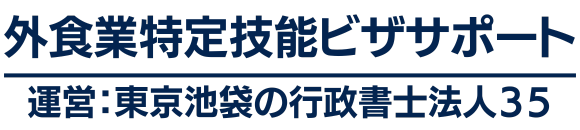【外食業向け】特定技能外国人材を雇用するための会社側の要件とは?

深刻な人手不足が続く外食業界において、外国人材の活用は不可欠な経営戦略の一つとなっています。
2019年に導入された特定技能制度は、外食業の人材不足解消に大きく貢献する可能性を秘めていますが、制度を理解し、適切に活用するためには、会社が満たすべき要件を正確に把握しておく必要があります。
「特定技能外国人を受け入れたいけど、何から始めればいいのか」
「自社は要件を満たしているのか」
「具体的にどんな準備が必要なのか」など、
特定技能制度の活用を検討されている外食業の経営者、人事担当者は、多くの疑問や不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、特定技能「外食」で外国人材を雇用するために、会社が満たすべき要件について、詳しく、わかりやすく解説します。
特定技能制度の基本から、受け入れ企業(特定技能所属機関)になるための要件、外国人材への支援体制、雇用契約、採用の流れ、注意点まで、特定技能「外食」の採用を成功させるために必要な情報を網羅的に提供します。
本記事では、行政書士の専門的な視点から、特定技能「外食」の会社要件に関する疑問を解消し、皆様の外国人材活用を成功に導くための情報を提供いたします。
最後までお読みいただければ、特定技能「外食」の会社要件に関する理解が深まり、自社が特定技能外国人を受け入れるための具体的なステップが見えてくるはずです。
ぜひ、ご一読ください。
目次
特定技能制度の基本(外食分野を中心に)
特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。
外食業もその対象分野の一つであり、特定技能「外食」の在留資格を持つ外国人は、調理、接客、店舗管理など、幅広い業務に従事することができます。
特定技能「外食」の活用は、人手不足の解消だけでなく、外国人顧客への対応力強化、多様な人材による組織活性化など、企業にとって様々なメリットをもたらします。
特定技能「外食」受け入れ企業(特定技能所属機関)の要件

特定技能「外食」の外国人材を受け入れるためには、企業は「特定技能所属機関」となる必要があります。
特定技能所属機関には、外国人材を適切に受け入れ、就労を支援するための体制を整えることが求められます。ここでは、特定技能所属機関になるための要件を、「共通要件」と「外食業分野固有の要件」に分けて詳しく解説します。
共通要件
特定技能所属機関には、分野を問わず共通して求められる要件があります。まず、法人格の有無は問われません。株式会社や合同会社などの法人だけでなく、個人事業主でも特定技能外国人を受け入れることができます。ただし、事業の継続性が求められます。安定した経営基盤があり、外国人材を継続的に雇用できる見込みがあることが必要です。
次に、過去の法令違反の有無が審査されます。
出入国管理法や労働関係法令に違反した経歴がある場合、特定技能所属機関として認められない可能性があります。
具体的には、過去5年以内に出入国管理法違反や労働基準法違反などで罰金刑以上の刑に処せられた場合、欠格事由に該当し、特定技能所属機関にはなれません。
また、税金や社会保険料の未納がないことも要件の一つです。税金や社会保険料を滞納している企業は、特定技能外国人を受け入れることができません。
外食業分野固有の要件
特定技能「外食」の外国人材を受け入れるためには、上記の共通要件に加えて、外食業分野固有の要件を満たす必要があります。
まず、食品産業特定技能協議会への加入が義務付けられています。
この協議会は、農林水産省が設置した組織で、特定技能制度の適切な運用を図ることを目的としています。
協議会への加入は、特定技能外国人を受け入れるための必須条件であり、受け入れ前の加入が前提となります。
次に、特定技能外国人との雇用契約は、直接雇用でなければなりません。
派遣会社などを介した間接雇用は認められていません。
また、雇用契約はフルタイム、いわゆる一般的な正社員雇用である必要があります。雇用期間に定めがある場合は、更新の可否や更新手続きについて、雇用契約書に明記する必要があります。
特定技能外国人に支払う報酬は、日本人と同等以上でなければなりません。
これは、外国人材の適正な労働条件を確保するための重要な要件です。
具体的には、同じ業務に従事する日本人従業員の賃金と比較し、同等以上の賃金を支払う必要があります。
また、最低賃金法を遵守し、最低賃金を下回る賃金を支払うことはできません。
最後に、特定技能外国人を受け入れることができるのは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)で規制されている「接待飲食等営業」や「性風俗関連特殊営業」に該当しない事業所である必要があります。
これらの事業所で特定技能外国人を受け入れることはできません。
これらの要件を全て満たすことで、企業は特定技能「外食」の外国人材を受け入れることができます。次章では、特定技能1号外国人に対する支援体制について解説します。
特定技能1号外国人に対する支援体制
特定技能「外食」で外国人材を受け入れる企業は、特定技能1号外国人に対して、日本での生活や就労を円滑に進めるための支援を行う義務があります。
この支援は、企業が自ら行うこともできますし、登録支援機関に委託することも可能です。ここでは、企業が構築すべき支援体制について、義務的支援を中心に詳しく解説します。
支援体制の構築義務
特定技能1号外国人に対する支援は、企業(特定技能所属機関)の義務です。
企業は、自社で支援体制を構築するか、登録支援機関に支援業務を委託するかのいずれかを選択する必要があります。
自社で支援を行う場合は、支援責任者および支援担当者を選任し、支援計画を作成・実施する必要があります。支援責任者と支援担当者は、外国人材の受け入れや支援に関する一定の知識や経験を持つ人物でなければなりません。
一方、登録支援機関に委託する場合は、適切な登録支援機関を選定し、委託契約を締結する必要があります。
義務的支援の内容
特定技能1号外国人に対しては、以下の10項目の義務的支援を行う必要があります。
これらの支援は、外国人材が日本での生活や仕事にスムーズに適応し、安心して働くことができるようにするためのものです。
- 事前ガイダンスの提供

- 入国前に、特定技能外国人に対して、日本での活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などについて、対面またはテレビ電話等で説明します。外国人が十分に理解できる言語で行うことが求められます。
- 説明内容は多岐にわたりますが、業務内容、報酬額、労働条件、入国手続きなどが含まれます。特に、保証金や違約金に関する契約を結んでいないことを確認することが重要です。これは、外国人材が来日前に不安を解消し、スムーズに日本での生活をスタートできるようにするための重要な支援です。
- 出入国時の送迎

- 入国時には空港から事業所または住居まで、帰国時には空港の保安検査場まで、送迎と付き添いを行います。特定技能外国人が入国する際には、上陸手続きを受ける港または飛行場から特定技能所属機関の事業所、または当該特定技能外国人の住居までの送迎を行う義務があります。
- 出国する際も同様で、出国手続きを受ける港もしくは飛行場まで送迎を行う必要があります。単に港・飛行場に外国人を送り届けるだけでなく、保安検査場の前まで同行して、入場を確認する必要があります。
- 住居確保・生活に必要な契約支援

- 外国人材の住居探しをサポートし、賃貸借契約の締結を支援します。
- また、銀行口座の開設や携帯電話の契約など、生活に必要な契約手続きを支援します。
- 具体的には、不動産業者や賃貸物件に関する情報提供、必要に応じた物件の内見や契約への同行、連帯保証人の確保などを行います。適切な連帯保証人がいない場合は、企業が緊急連絡先となることもあります。
- 生活オリエンテーションの実施

- 入国後、外国人材に対して、日本の生活ルール、マナー、公共機関の利用方法、交通ルール、連絡先などについて、8時間以上かけて説明します。
- 日本の生活習慣やルールを理解させることで、外国人材が地域社会で円滑に生活できるように支援します。具体的には、金融機関や医療機関の利用方法、交通ルールや公共交通機関の利用方法、生活必需品の購入方法、緊急時の連絡先などを説明します。
- 公的手続き等への同行

- 必要に応じて、外国人材の住居地、社会保障、税金などの手続きに同行し、書類作成の補助などを行います。
- 具体的には、市区町村役場での転入手続き、銀行口座の開設、携帯電話の契約、年金や健康保険の加入手続きなどに同行し、サポートします。
- 日本語学習機会の提供

- 外国人材の日本語能力向上を支援するため、日本語教室やオンライン教材などの情報を提供します。
- 日本語学習の費用を企業が負担したり、就業時間中に日本語学習の時間を設けたりすることも、支援の一環として考えられます。日本語能力の向上は、職場でのコミュニケーションを円滑にするだけでなく、外国人材の生活の質を高める上でも重要です。
- 相談・苦情への対応

- 外国人材から、職場や生活上の相談・苦情を受けた場合は、適切に対応し、必要な指導や助言を行います。
- 外国人材が十分に理解できる言語で対応することが求められます。相談内容に応じて、関係行政機関への案内や、手続きの補助を行うこともあります。
- 日本人との交流促進

- 地域のお祭りやイベントなど、日本人との交流の機会に関する情報を提供し、参加を促します。
- 地域住民との交流を促進することで、外国人材が日本社会に溶け込み、孤立を防ぐことができます。具体的には、地域のお祭りやイベント、自治会活動などの情報を提供したり、参加を呼びかけたりします。
- 転職支援(人員整理等の場合)

- 企業側の都合で雇用契約を解除する場合、次の受け入れ先を探すための転職支援を行います。
- 具体的には、新たな受け入れ先に関する情報提供、職業安定所や職業紹介事業者への案内などを行います。これは、外国人材のキャリアを守るための重要な支援です。
- 定期的な面談・行政機関への通報

- 支援責任者等が、特定技能外国人およびその上司と定期的に面談を実施し、労働基準法違反などがあれば、関係行政機関に通報します。
- これは、外国人材の労働環境を守り、法令遵守を徹底するための措置です。
自社支援の場合の注意点
企業が自社で支援を行う場合、支援体制を適切に構築し、運用することが重要です。支援責任者と支援担当者は、特定技能制度や外国人支援に関する十分な知識と経験を持つ人物を選任する必要があります。
また、支援計画は、外国人材の状況に合わせて具体的に作成し、確実に実行する必要があります。支援の記録は、適切に作成・保管し、必要に応じて関係機関に提出できるようにしておく必要があります。
登録支援機関の利用メリット、選び方
登録支援機関に支援を委託することで、企業は専門的な知識やノウハウを活用し、質の高い支援を提供することができます。
また、支援業務の負担を軽減し、本来の業務に集中することができます。登録支援機関を選ぶ際には、以下の点を考慮すると良いでしょう。
- 実績と経験:特定技能外国人の支援実績が豊富で、外食業分野に精通しているか。
- 支援内容:義務的支援だけでなく、任意的支援(24時間対応の生活相談、日本語教育など)も充実しているか。
- 費用:費用が明確で、自社の予算に合っているか。
- 対応言語:外国人材の母国語に対応できるか。
- 担当者の対応:相談しやすく、信頼できる担当者がいるか。
特定技能外国人との雇用契約

特定技能外国人を受け入れるためには、適切な雇用契約を締結することが不可欠です。ここでは、特定技能外国人との雇用契約における注意点、雇用契約書の作成方法、キャリアアッププランの作成について解説します。
雇用契約の注意点
特定技能外国人との雇用契約は、労働基準法、最低賃金法などの労働関係法令を遵守し、日本人と同等以上の待遇を保証する必要があります。
以下の点に注意して、雇用契約を締結しましょう。
- 労働時間、休日、休暇
- 労働時間、休日、休暇は、労働基準法の規定を遵守する必要があります。特定技能「外食」の場合、フルタイムでの雇用が義務付けられています。時間外労働や休日労働をさせる場合は、36協定を締結し、割増賃金を支払う必要があります。
- 賃金
- 特定技能外国人に支払う賃金は、同じ業務に従事する日本人と同等以上でなければなりません。基本給だけでなく、賞与や各種手当についても、日本人と同等に支給する必要があります。また、最低賃金法を遵守し、最低賃金を下回る賃金を支払うことはできません。外国人材の技能レベルや経験年数に応じて、適切な賃金を設定することが重要です。
- 社会保険、労働保険
- 特定技能外国人も、日本人と同様に、社会保険(健康保険、厚生年金保険)および労働保険(雇用保険、労災保険)に加入させる必要があります。保険料は、企業と外国人材がそれぞれ負担します。
- 契約期間
- 特定技能1号の在留期間は、通算で5年が上限です。雇用契約の期間は、この在留期間を超えないように設定する必要があります。雇用期間に定めがある場合は、契約更新の有無や更新手続きについて、雇用契約書に明記する必要があります。
- 業務内容
- 特定技能「外食」で認められている業務は、飲食物調理、接客、店舗管理などです。雇用契約書には、具体的な業務内容を明記する必要があります。風俗営業法で規制されている業務や、デリバリー専門業務など、特定技能「外食」で認められていない業務に従事させることはできません。
直接雇用:特定技能外国人は、派遣や請負ではなく、直接雇用しなければなりません。
雇用契約書の作成
特定技能外国人との雇用契約は、必ず書面で作成する必要があります。雇用契約書には、以下の事項を必ず記載しなければなりません。
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項
- 賃金の額、計算方法、支払方法、支払時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
- 昇給に関する事項(該当する場合)
- 賞与に関する事項(該当する場合)
- 退職手当に関する事項(該当する場合)
- 臨時に支払われる賃金に関する事項(該当する場合)
- 労働者に負担させるべき食費、居住費その他に関する事項(該当する場合)
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項(該当する場合)
- 休職に関する事項(該当する場合)
- 表彰及び制裁に関する事項(該当する場合)
- 災害補償及び業務外の疾病扶助に関する事項
- 雇用契約書は、日本語で作成するとともに、外国人材が理解できる言語(母国語など)に翻訳したものを作成することが推奨されています。
また、雇用契約書の内容について、外国人材に十分に説明し、理解を得ることが重要です。
キャリアアッププランの作成
特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人材のキャリアアップを支援するための「キャリアアッププラン」等を作成することも良いでしょう。
キャリアアッププランには、以下のような内容を盛り込むことが考えられます。
- 研修制度:調理技術、接客スキル、店舗管理など、業務に必要な知識や技能を習得するための研修制度を設ける。
- 昇給制度:技能レベルや経験年数に応じて、定期的に昇給を行う制度を設ける。
- 資格取得支援制度:調理師免許やレストランサービス技能士など、業務に関連する資格の取得を支援する制度を設ける。
- 特定技能2号への移行支援:特定技能2号への移行を目指す外国人材に対して、試験対策や実務経験の機会を提供する。
キャリアアッププランを作成し、外国人材に提示することで、外国人材のモチベーション向上や、長期的な定着に繋がることが期待できます。
雇用契約は、特定技能外国人を受け入れる上で最も重要な要素の一つです。適切な雇用契約を締結し、良好な労使関係を築くことが、外国人材の活躍と企業の発展に繋がります。
特定技能「外食」採用の流れ

ここでは、特定技能「外食」の外国人材を採用する際の、具体的な流れについて解説します。採用活動は、計画的に進めることが重要です。各ステップにおける注意点も合わせて説明します。
1. 求人募集
特定技能「外食」の外国人材を募集する方法は、いくつかあります。
- ハローワーク:ハローワークでは、特定技能外国人に特化した求人を出すことができます。
- 民間の職業紹介事業者:外国人材の紹介に特化した職業紹介事業者も増えています。
- 自社ホームページやSNS:自社のホームページやSNSで、特定技能外国人を募集することも可能です。
求人票には、業務内容、勤務地、勤務時間、給与、休日、社会保険の加入状況など、労働条件を明確に記載する必要があります。
また、特定技能「外食」の在留資格が必要であること、日本語能力や技能レベルの要件なども明記しましょう。外国人材が理解しやすいように、求人票を多言語で作成することも効果的です。
2. 選考(書類選考、面接、技能・日本語能力の確認)
応募があったら、まずは書類選考を行います。
履歴書、職務経歴書、日本語能力試験の合格証明書、技能測定試験の合格証明書などを確認し、応募資格を満たしているかを確認します。
書類選考を通過した応募者に対しては、面接を行います。面接では、職務経験、スキル、日本語能力、日本での就労意欲などを確認します。
特定技能「外食」では、技能測定試験と日本語能力試験の合格が必須ですが、面接の際に、改めて日本語でのコミュニケーション能力や、調理・接客の実務能力を確認することも重要です。
必要に応じて、実技試験や適性検査などを実施することも検討しましょう。
また、面接は、外国人材が企業の雰囲気や仕事内容を理解する機会でもあります。
企業側も、自社の魅力を積極的にアピールし、外国人材の疑問や不安に丁寧に応えることが大切です。
3. 雇用契約締結
採用が決まったら、特定技能雇用契約を締結します。
雇用契約書には、労働条件(業務内容、勤務地、勤務時間、給与、休日、社会保険の加入など)を明確に記載する必要があります。
雇用契約書は、日本語で作成するとともに、外国人材が理解できる言語(母国語など)に翻訳したものを作成することが推奨されています。
雇用契約の内容について、外国人材に十分に説明し、理解を得ることが重要です。また、雇用契約締結前に、特定技能外国人に対して事前ガイダンスを行う必要があります。
4. 在留資格諸申請(入国管理局への申請)
この申請は、企業(特定技能所属機関)が行うこともできますが、一般的には行政書士等の専門家に依頼をすることをおすすめいたします。
申請書類に不備や不足があると審査が遅滞したり、最悪の場合、不許可になったりする可能性があります。申請前に、必要書類をしっかりと確認し、正確に記入するようにしましょう。

5. 特定技能ビザの許可
許可後、本人(外国人)が海外にいる場合には、自国の日本大使館または総領事館でビザを申請します。
ビザ申請に必要な書類は、国によって異なりますので、事前に確認しておく必要があります。
すでに国内に在留している場合には、新しい在留カードの交付手続きをおこないます。
6. 入国・就労開始
ビザが発給され、外国人材が入国(又は在留資格の変更)したら、いよいよ就労開始です。
入国後、企業は外国人材に対して、生活オリエンテーションを実施し、日本の生活ルールやマナー、職場でのルールなどを説明する必要があります。
また、外国人材が安心して働けるように、相談しやすい環境を整え、定期的に面談を行うことも重要です。
特定技能「外食」の採用は、計画的に進めることが成功の鍵となります。各ステップにおいて、必要な手続きや注意点をしっかりと確認し、外国人材がスムーズに日本で働き、生活できるようにサポートしましょう。
次章では、特定技能外国人を受け入れた後の注意点について解説します。
特定技能外国人受け入れ後の注意点

特定技能外国人を受け入れた後も、企業は様々な点に注意し、外国人材が安心して働き、能力を最大限に発揮できる環境を整える必要があります。
ここでは、特定技能外国人を受け入れた後の注意点について、詳しく解説します。
定期的な面談の実施
特定技能1号外国人に対しては、支援責任者または支援担当者が、定期的な面談を実施する必要があります。
面談では、外国人材の業務状況、生活状況、日本語学習の進捗状況などを確認し、困っていることや悩みがないかを聞き取ります。
面談は、外国人材が理解できる言語で行うことが求められます。面談の結果は記録し、保管しておく必要があります。
定期的な面談は、外国人材の状況を把握し、問題の早期発見・解決に繋がるだけでなく、外国人材との信頼関係を築く上でも重要な機会となります。
関係機関への報告義務
特定技能所属機関(受け入れ企業)は、特定技能外国人の受け入れ状況や支援状況について、定期的に、または必要に応じて、関係機関に報告する義務があります。
具体的には、以下の報告が必要です。
- 出入国在留管理庁への報告
- 受入れ状況届出(四半期ごと)
- 活動状況届出(四半期ごと)
- 支援計画の変更届出(変更があった場合)
- 特定技能雇用契約の変更・終了・新たな契約の締結に係る届出(変更等があった場合)
- 食品産業特定技能協議会への報告
- 特定技能外国人の受け入れ状況に関する報告(年1回)
これらの報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりすると、罰則が科せられる可能性があります。報告義務を確実に履行するため、社内での報告体制を整備し、担当者を明確にしておくことが重要です。
労働関係法令の遵守
特定技能外国人を雇用する場合も、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などの労働関係法令を遵守する必要があります。
外国人だからといって、日本人と異なる労働条件を設定することはできません。労働時間、休日、休憩、年次有給休暇、賃金、割増賃金など、労働条件は、日本人と同等以上にする必要があります。
また、安全衛生に関する教育や健康診断の実施も義務付けられています。労働関係法令の違反は、外国人材の離職やトラブルの原因となるだけでなく、企業の社会的信用を失墜させることにも繋がります。法令を遵守し、適切な労務管理を行うことが重要です。
外国人材とのコミュニケーション
特定技能外国人と円滑なコミュニケーションを図ることは、良好な職場環境を構築し、業務をスムーズに進める上で非常に重要です。
外国人材の日本語能力には個人差があるため、理解できる言語でコミュニケーションを取るように努めましょう。
必要に応じて、通訳や翻訳ツールを活用することも検討しましょう。また、日本の文化や習慣、職場でのルールなどを丁寧に説明し、理解を促すことも大切です。
外国人材からの質問や相談には、親身になって対応し、不安や疑問を解消できるように努めましょう。定期的な面談の機会を設け、コミュニケーション不足によるトラブルを未然に防ぐことも重要です。
トラブル発生時の対応
特定技能外国人との間でトラブルが発生した場合、まずは当事者間で話し合い、解決を目指すことが重要です。
しかし、当事者間での解決が難しい場合は、登録支援機関や行政書士などの専門家に相談しましょう。専門家は、中立的な立場から、問題解決をサポートしてくれます。
また、外国人材が労働基準監督署や出入国在留管理庁などの行政機関に相談することも可能です。トラブルを放置すると、問題が深刻化したり、企業の評判を損なったりする可能性があります。早期に適切な対応を行うことが重要です。
特定技能2号への移行支援
特定技能1号の在留期間は通算5年が上限ですが、要件を満たすことで特定技能2号への移行が可能になります。
企業は、外国人材のキャリアアップを支援し、2号への移行を希望する外国人材に対しては、必要な情報提供やサポートを行うことが望ましいです。
よくある質問(Q&A)

ここでは、特定技能「外食」の外国人材の受け入れに関して、企業からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- Q1. 食品産業特定技能協議会とは何ですか?必ず加入しなければなりませんか?
- A1. 食品産業特定技能協議会は、農林水産省が設置した組織で、特定技能制度の適切な運用を図ることを目的としています。特定技能「外食」の外国人材を受け入れる企業は、この協議会への加入が義務付けられています。協議会では、特定技能制度に関する情報提供、相談支援、会員間の情報交換などが行われています。加入手続きは、オンラインで行うことができます。受け入れ前に加入していることが前提です。
- Q2. 登録支援機関は必ず利用しなければならないのですか?
- A2. いいえ、必ずしも利用する必要はありません。特定技能1号外国人に対する支援は、企業(特定技能所属機関)が自ら行うことも可能です。ただし、自社で支援を行うためには、支援責任者および支援担当者の選任、外国人材への適切な情報提供体制の整備など、一定の要件を満たす必要があります。これらの要件を満たすことが難しい場合や、より専門的なサポートを受けたい場合は、登録支援機関の利用を検討すると良いでしょう。
- Q3. 特定技能「外食」の外国人材の採用には、どのくらいの費用がかかりますか?
- A3. 採用にかかる費用は、登録支援機関を利用するかどうか、外国人材の日本語能力や技能レベル、採用方法などによって異なります。一般的には、初期費用(求人広告費、登録支援機関への委託費用、ビザ申請費用など)と、月額費用(登録支援機関への委託費用、給与、社会保険料など)がかかります。具体的な費用については、登録支援機関や行政書士に見積もりを依頼することをおすすめします。
- Q4. 自社で支援を行う場合の注意点は何ですか?
- A4. 自社で支援を行う場合は、支援体制を適切に構築し、運用することが重要です。支援責任者と支援担当者は、特定技能制度や外国人支援に関する十分な知識と経験を持つ人物を選任する必要があります。また、支援計画は、外国人材の状況に合わせて具体的に作成し、確実に実行する必要があります。支援の記録は、適切に作成・保管し、必要に応じて関係機関に提出できるようにしておく必要があります。さらに、外国人材からの相談に適切に対応できる体制を整えることも重要です。
- Q5. 特定技能1号から特定技能2号への移行は可能ですか?
- A5. はい、可能です。特定技能1号の在留期間が満了する前に、外食業特定技能2号技能測定試験に合格し、必要な実務経験(複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての2年間の実務経験)などの要件を満たせば、特定技能2号への移行が可能です。特定技能2号は、在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同も可能となるため、外国人材の長期雇用に繋がります。
- Q6. 特定技能外国人を採用するメリットは何ですか?
- A6. 特定技能外国人を採用するメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。
- 人手不足の解消
- 即戦力人材の確保
- 若年層の労働力の確保
- 外国人観光客への対応力強化
- 職場の活性化
これらのQ&Aは、企業が特定技能「外食」の外国人材を受け入れる上で、よくある疑問の一部を解消するためのものです。
まとめ

本記事では、特定技能「外食」の外国人材を雇用するために、企業が満たすべき要件について詳しく解説しました。最後に、記事の重要なポイントをまとめます。
- 特定技能「外食」の外国人材を雇用するためには、企業は「特定技能所属機関」となる必要がある。
- 特定技能所属機関には、共通要件(法人格不問、事業継続性、法令遵守など)と、外食業分野固有の要件(食品産業特定技能協議会への加入、直接雇用、日本人と同等以上の報酬など)がある。
- 特定技能1号外国人に対しては、義務的支援(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、日本語学習支援など)を行う必要がある。
- 義務的支援は、企業が自ら行うことも、登録支援機関に委託することもできる。
- 特定技能外国人との雇用契約は、労働関係法令を遵守し、日本人と同等以上の待遇を保証する必要がある。
- 特定技能外国人の採用は、計画的に進める必要がある。(求人募集、選考、雇用契約締結、在留資格諸申請、入国、就労開始)
- 特定技能外国人を受け入れた後も、定期的な面談、関係機関への報告、労働関係法令の遵守、外国人材とのコミュニケーション、トラブル発生時の対応などに注意する必要がある。
- 特定技能1号から特定技能2号への移行も可能。
特定技能「外食」の活用は、外食企業にとって、人手不足解消の有効な手段であると同時に、外国人材の受け入れを通じて、企業の成長や国際化にも繋がる可能性を秘めています。
しかし、制度を適切に活用するためには、ここで解説した会社要件をしっかりと理解し、準備を整えることが重要です。
外食業特定技能ビザサポート(運営:行政書士法人35)は、特定技能制度に関する豊富な知識と経験を持つ行政書士が、企業の外国人材採用・ビザ申請を全面的にサポートしています。
特定技能ビザ申請の代行から、登録支援機関としての業務まで、ワンストップで対応可能です。無料相談も実施しておりますので、
- 「外国人材の採用を検討しているが、何から始めれば良いか分からない」
- 「自社が特定技能の要件を満たしているか確認したい」
- 「特定技能制度についてもっと詳しく知りたい」など、どんなことでもお気軽にご相談ください。
メールでの無料相談はこちら
関連するおすすめ記事
- 特定技能1号で家族の帯同は可能なのか?認められる要件について解説
- 特定技能外国人の転職について|要件・手続き・注意点を解説
- 特定技能ビザから技人国ビザへの変更方法について|要件・方法・注意点を解説
- 特定技能ビザで働く【外国人】のメリット・デメリットについて
- 特定技能人材を採用する場合の【会社側】のメリット・デメリットについて
- 「特定技能1号ビザ」の在留期間は何年なのか?|更新・延長・満了後の選択肢について解説
- 特定活動(移行準備)ビザとは?|特定技能ビザの申請が間に合わない方へ
- 留学ビザから特定技能ビザへの変更方法とは?
- 外食業「特定技能1号技能測定試験」とは?
- 【JLPT】特定技能ビザ取得に必要な日本語能力試験の種類・レベル・対策・合格のコツとは?