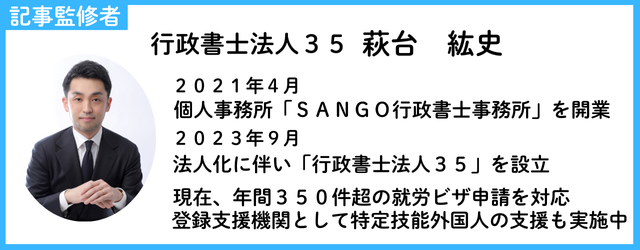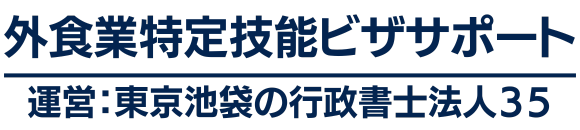登録支援機関の義務的支援・任意的支援とは?人事担当者が知るべき違い・費用・選び方を徹底解説
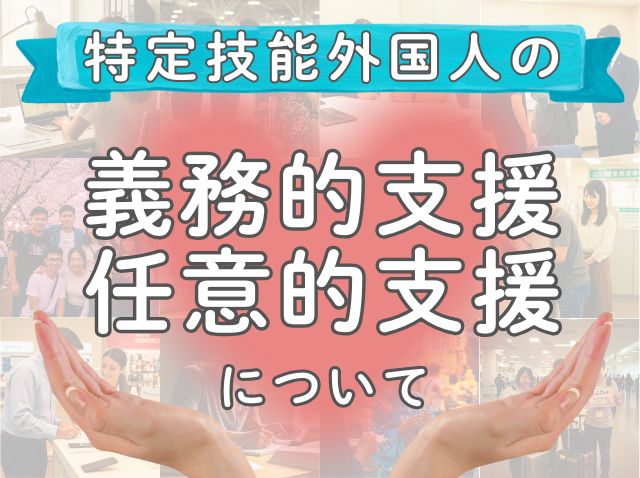
特定技能外国人の採用を進めているものの、
「義務的支援と任意的支援の違いがはっきりしない」
「どこまでが必須の対応で、何を任意で行うべきか判断に迷う」
外国人材の受け入れを担当する人事の皆様は、支援に関する課題やお悩みをお持ちかもしれません。
特定技能制度を活用して優秀な人材を確保するためには、法律で定められた支援体制を正しく理解し、適切に運用することが不可欠なのです。
外国人材が日本で安心して働き、定着してもらうためには、受け入れ企業側のサポート体制が極めて重要となります。
特に、「義務的支援」と呼ばれる必ず行わなければならない10項目の支援と、
実施が推奨される「任意的支援」の内容を正確に把握しておく必要が生じます。
両者の違いを理解せずに受け入れを進めてしまうと、法令違反のリスクだけでなく、せっかく採用した人材の早期離職にも繋がりかねません。
本記事では、特定技能外国人の受け入れに携わる人事担当者の皆様に向けて、
登録支援機関が担う「義務的支援」と「任意的支援」の具体的な内容、両者の明確な違い、そしてそれぞれの重要性を詳しく解説していきます。
さらに、支援を自社で行う場合と登録支援機関へ委託する場合のメリット・デメリット比較、気になる費用相場、そして失敗しない登録支援機関の選び方まで、皆様が知りたい情報を網羅的にお届けします。
この記事を読み進めることで、貴社にとって最適な支援体制を構築するための具体的な道筋が見えてくるはずです。
外国人材が持つ能力を最大限に引き出し、企業の成長力へと繋げるために、まずは支援の全体像を正しく理解することから始めませんか。
貴社に最適な支援体制を見つけ出す第一歩として、ぜひこの記事で義務的支援・任意的支援の基本から、委託や選び方の応用までご確認ください。
具体的なプランニングやご相談をご希望の場合は、専門家がいつでもお待ちしております。
目次
- 特定技能制度と登録支援機関の基本をおさらい
- 【法律で必須】登録支援機関が行う「義務的支援」10項目を完全理解
- 【定着率UPの鍵】重要性が増す「任意的支援」とは?内容とメリット
- 一目でわかる!義務的支援と任意的支援の主な違い
- 支援体制はどう構築する?「自社支援」vs「登録支援機関への委託」
- 失敗しない!信頼できる登録支援機関の選び方【6つのチェックポイント】
- 【2025年最新動向】知っておくべき制度変更と市場の動き
- まとめ:義務的支援と任意的支援を理解し、最適な支援体制を構築しよう
特定技能制度と登録支援機関の基本をおさらい
まず、義務的支援と任意的支援の詳細に入る前に、特定技能制度そのものと、支援の担い手である登録支援機関について基本的な知識を確認しておきましょう。
これらの背景を知ることで、なぜ支援が必要とされ、重要視されるのかが見えてくるはずです。
なぜ今「特定技能」なのか?制度の目的と現状
日本国内の多くの産業分野では、少子高齢化を背景とした深刻な人手不足が、避けては通れない課題です。
この状況に対応するため、2019年4月に創設された在留資格が「特定技能」となります。特定技能制度は、特に人手不足が著しい特定の産業分野を対象に、一定の専門性や技能を持ち、即戦力となり得る外国人材の受け入れを目的としています。
制度開始以来、特定技能外国人材の数は増加の一途をたどり、日本経済を支える重要な存在となりつつあるのが現状です。さらに、技能実習制度に代わる新たな「育成就労」制度の創設も予定されており、今後、特定技能資格を持つ外国人材への期待は一層高まるものと考えられます。
「登録支援機関」とは?受入れ企業を支えるパートナーの役割
特定技能1号の資格を持つ外国人材が、日本で安定して働き、円滑な社会生活を送るためには、多岐にわたるサポートが不可欠となります。
その支援を専門的に実施するのが「登録支援機関」と呼ばれる存在です。登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)からの委託に基づき、個々の外国人材に合わせた支援計画を作成し、計画に沿った支援を実行する役割を担います。出入国在留管理庁長官から正式な登録を受けた機関だけが、登録支援機関としての活動を認められています。
技能実習制度における「監理団体」が実習生を監督する側面が強いのに対して、登録支援機関は外国人材を文字通り「サポート」することに主眼を置く点に違いがあります。
注意!受入れ企業(特定技能所属機関)が負う支援義務の全体像
ここで重要なポイントは、特定技能外国人材に対する支援義務は、本来、受け入れ企業自身が負うものであるという事実です。
企業は、外国人材に対して適切な支援を提供しなければなりません。
支援の実施方法については、企業は「全ての支援を自社で完結させる」か、
「支援の全部または一部を登録支援機関に委託する」かのいずれかを選択することになります。
自社で支援を行う場合であっても、支援責任者や支援担当者を配置するなど、出入国在留管理庁が定める基準を満たした体制整備が求められます。
支援業務の内容は幅広いため、現実的には、専門的なノウハウを持つ登録支援機関へ委託する企業が多い傾向にあります。
委託を選択することで、企業は支援業務に関わる負担を軽減し、本来の事業活動へより集中できるというメリットが生まれます。
特定技能制度と登録支援機関の基本的な役割、そして企業が負う支援義務についてご理解いただけたでしょうか。
この基礎知識を土台として、いよいよ次章では、法律で定められた「義務的支援」の具体的な内容に迫ります。全10項目にわたる必須の支援内容を、一つひとつ詳しく解説していきますので、ぜひご注目ください。
【必須】登録支援機関が行う「義務的支援」10項目を完全理解

特定技能外国人を受け入れる上で、必ず実施しなければならない支援、それが「義務的支援」です。
このセクションでは、全10項目にわたる義務的支援の具体的な内容を、一つひとつ分かりやすく解説します。これらの支援内容を正確に理解し適切に実行することが、法令遵守はもちろん、外国人材との良好な関係を築き、無用なトラブルを防ぐための基礎となります。
義務的支援とは?必ず実施すべき支援の定義と法的根拠
まず「義務的支援」とは何か、その定義を確認しましょう。
義務的支援は、特定技能1号の在留資格で就労する外国人材に対し、受け入れ企業(特定技能所属機関)または委託を受けた登録支援機関が、必ず提供しなければならないと法律で定められたサポート活動全体を指します。
特定技能制度関連の法令を根拠とし、外国人材が日本で安定した職業生活と社会生活を送る基盤を整えることを目的としています。支援の不履行はペナルティに繋がる可能性もあるため、内容の正確な把握が不可欠です。
項目1:入国前の不安解消「事前ガイダンス」
最初の義務的支援は、外国人材が日本での就労・生活をスムーズに始められるよう、入国前に行う情報提供、すなわち事前ガイダンスです。
雇用契約を結んだ後、在留資格の申請前などに、対面あるいはオンライン会議システムなどを活用して行います。伝えるべき情報は、雇用条件、従事する業務内容、日本での活動全般、入国・在留に関する手続き、そして保証金の徴収や違約金契約は絶対に無いことなど、多岐にわたります。外国人材が母国語などで十分に理解できるよう、少なくとも3時間程度の時間をかけ、丁寧に説明することが推奨されています。入国後の認識齟齬を防ぐ、非常に大切なステップです。
項目2:スムーズな移動をサポート「出入国時の送迎」
外国人材が日本へ入国する時と、任期を終えて帰国する際の送迎も、企業または登録支援機関の義務です。
入国時は、到着した空港などから、用意された住居または事業所まで安全かつ確実に送り届けます。一方、帰国する際は、出国する空港まで同行し、保安検査場の入口まで見届けることが求められます。送迎に伴う交通費は、受け入れ企業の負担となります。ただし、就労期間中の一時帰国については、送迎義務の対象外です。なお、2025年からは、登録支援機関が車両を用いて送迎を行う場合の道路運送法遵守に関する具体的な解釈が示される予定となっています。
項目3:生活基盤を整える「住居確保・生活契約支援」
外国人材が安心して日本での生活をスタートできるよう、生活の基盤となる住居の確保を支援します。企業が社宅を提供する方法や、賃貸物件探しを手伝い、必要に応じて企業が連帯保証人となるといったサポートが考えられます。
確保する住居には広さなどの基準がある点に注意が必要です。さらに、銀行口座の開設、携帯電話の契約、電気・ガス・水道などライフラインの契約といった、日常生活に欠かせない手続きについても、必要書類の案内や窓口への同行などを通じて、円滑に進むようお手伝いします。
項目4:日本の生活ルールを伝える「生活オリエンテーション」
日本でトラブルなく、快適に社会生活を送ってもらうために、日本の法律・ルール、交通マナー、公共サービスの利用方法、ゴミ出しのルール、そして地震などの災害時の適切な対応や連絡先といった重要な情報を提供します。これが生活オリエンテーションです。
外国人材が母国語などで十分に内容を理解できるよう、少なくとも8時間以上の時間を確保して実施する必要があります。説明後は、内容理解の確認と確認書への署名取得も求められます。一度だけでなく、定期面談などの機会をとらえて情報を再確認することも有効な方法です。
項目5:役所手続きなどをサポート「公的手続き等への同行」
外国人材は、日本で暮らす上で様々な行政手続きに直面します。
例えば、住んでいる市区町村役場での住民登録、社会保険や税金に関する手続きなどです。義務的支援の一環として、外国人材が必要とする場合に、これらの手続きに同行し、書類作成の補助などを行います。マイナンバーカードの申請手続きや、自転車を利用する際の防犯登録なども、必要に応じて支援の対象となり得ます。
項目6:コミュニケーション円滑化へ「日本語学習の機会の提供」
職場や日常生活での円滑なコミュニケーションを助けるため、外国人材が日本語を学ぶ機会を提供することも義務となります。
具体的な支援としては、地域の日本語教室やオンライン日本語講座、適切な学習教材などの情報を提供し、必要であれば入学手続きや教材購入の手伝いをします。企業内で日本語研修を企画・実施することも考えられますが、まずは学習機会に関する情報提供を行うことが求められます。
項目7:困りごとに寄り添う「相談・苦情への対応」
仕事上の悩み、生活上の不安、あるいはハラスメントなど、外国人材が抱える様々な相談や苦情に対応できる体制を整備することが必要です。
相談を受ける際には、外国人材が安心して話せるよう、母国語など十分に理解できる言語で対応します。内容に応じて適切なアドバイスや指導を行い、必要であれば労働基準監督署や人権擁護機関といった専門の行政機関を紹介し、同行して手続きを補助することも求められます。受け付けた相談内容や対応の経過は、相談記録書としてきちんと記録・保管する必要があります。
項目8:地域社会との繋がりを促進「日本人との交流促進」
外国人材が職場だけでなく、地域社会にも自然に溶け込み、孤立感を抱くことなく生活できるよう、日本人住民との交流を促進する支援を行います。
具体策としては、地域のお祭りや清掃活動、スポーツイベントなどの情報を提供し、参加を希望する場合には手続きを手伝います。社内で日本人従業員との懇親会や交流イベントを企画することも、有効な取り組みの一つです。
項目9:万が一のセーフティネット「転職支援(非自発的離職の場合)」
企業の業績悪化による人員整理など、外国人材自身の責任ではない理由で雇用契約が終了となる場合に備え、転職支援を行う義務があります。
具体的には、次の就職先を探すためのサポート(ハローワークへの同行など)これまでの職務経歴を証明する推薦状の作成、求職活動のための有給休暇の付与、そして離職に伴って必要となる各種行政手続き(社会保険、税金など)に関する情報提供など、セーフティネットとしての役割を果たします。
項目10:定期的な状況確認と是正「定期的な面談・行政機関への通報」
外国人材が不当な労働条件で働かされていないか、ハラスメントなどを受けていないかなどを確認するため、定期的な面談の実施が義務付けられています。
面談は、外国人材本人だけでなく、その外国人材の仕事を監督する立場にある日本人従業員(直属の上司など)とも、それぞれ3ヶ月に1回以上の頻度で行う必要があります。面談を通して、労働基準法違反などの問題が発覚した場合は、見て見ぬふりをせず、速やかに労働基準監督署などの関係行政機関へ通報する義務があります。
なお、2025年4月からは、外国人材本人が同意する場合に限り、オンライン形式での面談も認められる予定です。
義務的支援を怠った場合のリスクとは?
これまで解説してきた10項目の義務的支援は、いずれも法律で定められた企業や登録支援機関の責任です。
もし、これらの支援を適切に実施しなかった場合、出入国在留管理庁から指導を受けたり、改善命令が出されたりする可能性があります。それでも状況が改善されない悪質な場合には、登録支援機関であれば登録を取り消され、受け入れ企業であれば特定技能外国人の受け入れができなくなるという、非常に重い処分が科される恐れがあります。支援体制の不備は、企業の社会的信用にも関わる重大な問題と認識すべきでしょう。
以上が、定められた10項目の義務的支援の具体的な内容です。
多岐にわたる支援項目を、責任を持って確実に実施していくことの重要性がお分かりいただけたかと思います。しかしながら、外国人材の活躍と日本での定着を真に願うのであれば、これらの義務的支援に留まらず、さらに一歩進んだサポート体制を検討することも非常に有効です。次の章では、実施が推奨される「任意的支援」に焦点を当て、その内容と企業にもたらされるメリットについて詳しく掘り下げてまいります。
【定着率UPの鍵】重要性が増す「任意的支援」とは?内容とメリット
前章では、実施が義務付けられた10項目の「義務的支援」を確認しました。
しかし、特定技能外国人材に日本で長く活躍してもらい、企業の確かな戦力となってもらうためには、定められた範囲を超えるサポート、すなわち「任意的支援」への取り組みが非常に重要性を増しています。この章では、任意的支援の具体的な内容と、企業が実施することで得られる戦略的なメリットについて詳しく見ていきましょう。
任意的支援とは?義務ではないが推奨される支援の目的
まず「任意的支援」とは、実施義務はないものの、特定技能外国人材の日本での生活や就労をより円滑にし、職場への定着を促進するために行うことが望ましいとされる様々なサポート活動です。
義務的支援が最低限の生活基盤と就労環境を保障するセーフティーネットであるのに対し、任意的支援は、外国人材一人ひとりの状況やニーズに応じ、より快適で充実した日本での経験を提供するための「付加価値」の高い支援と言えます。義務的支援を補完し、外国人材の満足度や企業へのエンゲージメントを高めることを主な目的としています。
具体的な任意的支援の例
任意的支援の具体的な内容は実に様々です。義務的支援の各項目を、さらに手厚く、きめ細かくするイメージを持つと分かりやすいでしょう。
例えば、事前ガイダンスでは、義務内容に加えて日本の気候に合わせた服装や持参すべき物、当面の生活費目安などの情報提供。住居支援では、物件探しの補助に留まらず、生活に必要な家具・家電の準備を手伝ったり、地域独自のゴミ出しルールを一緒に確認したりする配慮。状況に応じて、雇用契約終了後も次の仕事が見つかるまで一時的に住居を提供するなどのサポートも考えられます。
日本語学習支援では、情報提供だけでなく、社内での学習時間確保、日本語能力試験(JLPT)の受験料補助や合格者への報奨金設定など、学習意欲を引き出す工夫が任意的支援にあたります。相談・苦情対応では、公的機関の相談窓口リストを事前に渡したり、労災手続きに関して本国の家族へも情報提供したりするサポート。
日本人との交流促進では、地域行事参加のためのシフト調整や有給取得奨励、社内交流会の積極的な企画などが有効です。さらに、本人のキャリアプランに合わせた資格取得支援なども、働く意欲を高める重要な任意的支援となり得ます。
なぜ任意的支援が重要なのか?企業と外国人双方にもたらすメリット
任意的支援の実施は義務ではありませんが、企業経営の観点から見ても多くのメリットがあります。
最大の効果として期待されるのは、外国人材の定着率向上です。手厚いサポートを通じて、外国人材は企業への信頼と安心感を深め、結果的に早期離職のリスクが大幅に低減します。これは、採用・育成コストの削減に直結する重要なポイントです。
次に、従業員のエンゲージメント向上による生産性のアップが見込めます。
生活面の不安が解消され、職場にスムーズに適応できれば、外国人材はより早く、そして意欲的に業務に取り組むようになります。日本語能力や関連スキルの向上支援は、直接的な業務効率の改善にも繋がるでしょう。
さらに、任意的支援を通じた良好なコミュニケーションは、日本人従業員との相互理解を促進し、職場全体の活性化やチームワーク向上にも貢献します。
加えて、任意的支援への積極的な取り組みは、企業の社会的な評価を高める効果も見逃せません。「外国人材を大切にし、多様性を尊重する企業」という評判は、今後の人材獲得競争において大きな武器となります。法令遵守を超えた支援体制は、企業の持続的成長を支える、まさに戦略的な人的投資と言えるのです。
注意点:任意的支援も「支援計画」に記載すれば義務になる
任意的支援はあくまで「任意」であると述べてきましたが、一つだけ重要な注意点が存在します。それは、受け入れ企業が外国人材ごとに作成し、出入国在留管理庁へ提出する「支援計画書」に任意的支援の内容を具体的に記載した場合です。
計画書に記載された支援項目は、たとえ本来は任意であっても、法的に実施する義務が生じます。計画に盛り込む際には、その支援が継続的に実施可能かどうかを十分に検討することが不可欠です。安易な記載は避け、実行可能な範囲で計画することが肝要となります。
任意的支援は、義務ではないからこそ、企業の状況や文化に合わせて創意工夫を凝らすことができる魅力的な領域です。外国人材の活躍を力強く後押しする任意的支援の価値をご理解いただけたでしょうか。次の章では、これまでに解説した「義務的支援」と「任意的支援」、両者の違いを比較表などを用いて改めて整理し、その関係性をより明確に理解することを目指します。
一目でわかる!義務的支援と任意的支援の主な違い
これまでの章で、義務的支援と任意的支援、それぞれの内容やその大切さについて触れてきました。ここでは、両者の違いをよりクリアにするために、いくつかの重要な観点から比較し、それぞれの特性を整理してみましょう。
この違いを正確に理解することが、自社に合った支援体制を考える上での確かな土台となります。
ポイント1:法的な位置づけと「実施義務」の有無
まず根本的な違いとして、法的な位置づけと実施義務の有無が挙げられます。
義務的支援は、特定技能関連の法令により、受け入れ企業または登録支援機関が「必ず実施しなければならない」と定められた支援です。つまり、法的な実施義務があります。
それに対し、任意的支援は、法律上の実施義務はなく、あくまで「実施することが推奨される」あるいは「望ましい」とされるサポート活動です。実施するか否かは、基本的には受け入れ側の判断に委ねられている点が大きく異なります。
ポイント2:支援が目指す「目的」の違い
支援の目的にも、それぞれの性格が表れています。
義務的支援が主に目指すのは、特定技能1号の外国人材が日本で就労・生活する上での最低限の基盤を保障し、安定した活動を可能にすること。いわば、生活と就労のセーフティーネットとしての役割を担います。
一方、任意的支援は、義務的支援を土台としつつ、外国人材の満足度を高め、日本社会や職場へのよりスムーズな適応を助け、結果として長期的な定着を促すことを目的とします。生活の質(QOL)向上や、より一層の活躍を後押しする「付加価値」を提供する支援と言えるでしょう。
ポイント3:「支援計画書」への記載とその効力
受け入れ企業が作成する支援計画書への記載に関する扱いも、見逃せない違いです。
義務的支援については、定められた全10項目を支援計画書に記載することが必須とされています。計画書に記載された内容は、当然、確実に実行する責任が生じます。
他方、任意的支援は、支援計画書へ記載するかどうか自体が任意です。ただし、ここで注意が必要なのは、任意的支援であっても、もしその内容を支援計画書に記載した場合には、法的な実施義務が発生する、という点。「計画書に記載した時点で任意ではなくなる」と覚えておくことが重要です。
ポイント4:支援の「対象者」と内容の「柔軟性」
支援の対象者は、義務的支援・任意的支援ともに、主に「特定技能1号」の外国人材となります(特定技能2号は義務的支援の対象外)。
支援内容の性質に目を向けると、義務的支援は法律で具体的に定められた10項目であり、全ての対象者に対して網羅的かつ、ある程度画一的に提供されるものと言えます。
それに対して任意的支援は、法律による細かな規定がないため、受け入れ企業や登録支援機関が、外国人材一人ひとりの状況やニーズ、あるいは自社の理念や強みに合わせて、柔軟に内容を設計し提供できるという、自由度の高さが特徴です。
義務的支援と任意的支援、それぞれの特徴と違いが明確になったでしょうか。法律上の義務である義務的支援の確実な実施は絶対条件ですが、外国人材の定着促進や戦力化を考えると、任意的支援をどのように取り入れるかが戦略的な鍵となります。さて、これらの重要な支援を「誰が担うのか」という実践的な問題が次に浮上します。
次の章では、支援体制の選択肢として「自社で実施する場合」と「登録支援機関に委託する場合」を取り上げ、それぞれのメリット・デメリット、そして費用面などを具体的に比較検討していきます。
支援体制はどう構築する?「自社支援」vs「登録支援機関への委託」

義務的支援と任意的支援、それぞれの内容を理解した上で、次に直面する実践的な課題は「これらの支援を具体的に誰が、どのように実施していくのか」という体制構築の問題です。特定技能外国人材への支援体制には、大別して「すべて自社内で対応する(自社支援)」方法と「専門家である登録支援機関に委託する」方法が存在します。
委託する場合でも、支援業務の全てを任せるか、一部に限定するかという選択肢があります。この章では、それぞれの体制が持つ利点や課題、費用感を比較検討し、貴社にとって最適な形を見つけ出すための道筋を探っていきましょう。
ケース1:すべて自社で支援する場合(メリット・デメリット、注意点)
まず、全ての支援業務を自社の人員で完結させる「自社支援」のケースです。
この方法の魅力は、何と言っても登録支援機関への委託費用がかからない点、つまりコスト抑制の可能性にあります。加えて、支援活動を通じて外国人材と直接、頻繁にコミュニケーションを取ることで、より強固な信頼関係を築きやすいというメリットも期待できます。社内に外国人支援の経験やノウハウが蓄積されれば、将来の受け入れ拡大にも繋がるでしょう。
一方で、自社支援には相応の準備と覚悟が必要です。義務的支援は10項目に及び、専門知識や細やかな対応が求められます。十分な人的リソース、時間的コストの確保が必須です。多言語での対応、複雑な行政手続き、あるいは予期せぬトラブルへの対応などは、専門知識なしでは困難を伴う可能性があります。支援の質が十分に担保できないリスクや、意図せず法令を遵守できない事態に陥るリスクも考慮すべきです。
2025年4月から定期面談がオンラインでも可能になるなど、負担軽減策も講じられていますが、体制構築のハードル自体が低くなるわけではない点に留意が必要です。
ケース2:すべて登録支援機関に委託する場合(メリット・デメリット)
次に、支援業務の全てを登録支援機関にアウトソースする方法を考えます。
この選択肢の最大の利点は、受け入れ企業側の負担を大幅に軽減できることです。支援計画の策定から日々の支援実施まで、専門的なスキルと経験を持つ登録支援機関に一任できるため、企業はコア業務にリソースを集中させられます。専門家による質の高い支援が期待でき、法令遵守の面でも安心感が増すでしょう。また、企業と外国人材の間でデリケートな問題が生じた際にも、中立的な第三者である登録支援機関が介在することで、円滑な解決に繋がりやすいという側面もあります。
もちろんデメリットも存在します。
最も分かりやすいのは、継続的な委託コストの発生です。また、支援業務を完全に外部に依存することで、社内に外国人支援に関する実践的な知見が蓄積されにくいという点は否めません。登録支援機関との連携が不十分だと、支援の状況が見えにくくなったり、企業の細かな要望が反映されにくかったりする可能性もゼロではありません。
ケース3:一部を委託する場合(委託範囲の考え方、注意点)
三つ目のアプローチとして、支援業務の一部だけを登録支援機関に委託するという方法も考えられます。
例えば、日常的な声かけや職場内での簡単な相談は自社で行い、専門知識が特に必要な行政手続きへの同行、初期段階での多言語ガイダンス、法律で定められた定期面談などを外部に委託する、といった形です。この方法の利点は、自社のリソースや強みを活かしつつ、不得意な分野や特に負担の大きい業務だけを専門家の力で補完できる点にあります。コストと社内負担のバランスを取りやすい、柔軟な選択肢と言えるでしょう。
一部委託を選択する上で重要なのは、まず「どの業務範囲を委託し、どこからを自社で担うのか」を明確に定義し、契約書などで双方の役割分担を書面で確認することです。
そして、自社と登録支援機関との間で常にスムーズな情報共有と緊密な連携を保つ体制が不可欠となります。責任の所在が曖昧にならないよう、コミュニケーションを密に取ることが成功の鍵です。
【コスト比較】委託する場合の費用相場と内訳
登録支援機関への委託を検討する際、避けて通れないのが費用に関する問題です。
費用体系は機関により異なりますが、一般的には特定技能外国人材1名あたり月額で費用が発生する形態が多く見られます。その費用相場ですが、一概には言えないものの、月額2万円から3万円程度が一つの目安とされています。ただし、近年は登録支援機関の数が増え、価格競争も生じているため、地域やサービス内容によっては月額1万円台のケースも存在します。市場動向によって変動する可能性がある点はご留意ください。
月額費用以外にも、初期費用として登録支援機関への登録料や、個別の支援計画書作成費用などがかかる場合があります。また、人材紹介サービスも提供している機関の場合、紹介手数料が別途必要となることもあります。
費用を比較する際は、単に提示された月額料金の安さだけで飛びつくのではなく、支援内容の詳細、含まれるサービス範囲、追加費用の有無などを細かく確認し、総合的な費用対効果を慎重に見極める姿勢が求められます。
自社支援か委託かの判断ポイントは?
最終的に自社支援、全部委託、一部委託のいずれが最適かは、各企業の個別の状況によって結論が変わってきます。
判断を下す際の主な考慮事項を整理してみましょう。
- 企業の規模、経営体力(人的リソース、財務状況)
- 社内の専門知識(法規、手続き、多言語対応能力など)の有無
- 受け入れ外国人材の人数、出身国、日本語能力レベル
- 法令遵守への考え方、リスク許容度
- 外国人材との関わり方に関する組織としての方針
これらの多角的な視点から総合的に検討し、自社にとって最も現実的で持続可能、かつ外国人材にとっても最良となる支援体制を選択することが肝要です。
自社にふさわしい支援体制の輪郭が見えてきたでしょうか。
どの選択肢にもメリットとデメリットが存在するため、社内で十分に議論を重ねることが大切です。もし、登録支援機関への委託(全部または一部)を具体的に進める方向になった場合、次にクリアすべき課題は「数多く存在する登録支援機関の中から、信頼できるパートナーをいかにして選ぶか」という点に移ります。
次の章では、後悔しないための登録支援機関選びについて、具体的なチェックポイントを詳しく解説していきます。
失敗しない!信頼できる登録支援機関の選び方【6つのチェックポイント】
特定技能外国人材への支援を登録支援機関に委託する方針が決まったら、次のステップは信頼できるパートナー選びです。現在、日本全国には多数の登録支援機関が存在しますが、残念ながら提供される支援の質や体制には差があるのが実情と言わざるを得ません。後悔のない選択をするために、ここでは信頼できる登録支援機関を見極めるための具体的なチェックポイントを6つ提示します。
これらの観点を一つひとつ吟味し、慎重に選定を進めていきましょう。
チェック1:【基本】正式な登録と確かな「支援実績」
まず大前提として、候補の機関が出入国在留管理庁の「登録支援機関登録簿」に正式に登録されているかを確認します。登録簿は同庁ウェブサイトで確認可能です。しかし、登録されているだけで安心はできません。
指摘されている通り、実際には活動実態の乏しい機関も存在するためです。重要なのは、登録の事実に加え、実際に特定技能外国人材を支援した具体的な「実績」があるか、そしてどの程度の期間や人数を支援してきた経験があるかです。実績が豊富な機関ほど、多様な状況に対応できるノウハウが期待できます。
チェック2:【疎通】「対応言語」と「多文化理解」の深さ
円滑な意思疎通は、質の高い支援の根幹を成します。受け入れ予定の外国人材の母国語に対応可能なスタッフがいるか、信頼できる通訳体制が整備されているかの確認は必須です。さらに、単に言語が通じるだけでなく、出身国の文化、宗教、生活習慣に対する深い理解があるかどうかも見極めたいポイント。
異文化への理解がある機関は、外国人材特有の悩みや誤解に寄り添った細やかな対応が可能です。
チェック3:【具体性】「支援内容」の明確さと「柔軟性」
提供される支援サービスの範囲が、具体的かつ明確に提示されているかを確認しましょう。義務的支援10項目を具体的にどのように実施するのか、任意的支援はどこまで含まれるのか、その詳細を事前に把握することが重要です。
また、定型的なサービス提供に留まらず、企業の個別の事情や外国人材の状況変化に応じて、柔軟に対応してくれる姿勢があるかも見極めるべき点。契約前にサービス内容に関する疑問点を全てクリアにしておくことが大切です。
チェック4:【費用】「料金体系」の透明性と「妥当性」
費用に関する取り決めは、後々のトラブル回避のためにも極めて重要です。料金体系(月額制か、項目ごとの従量制か、初期費用や追加費用の有無など)が明瞭で、分かりやすく提示されているかを確認します。
詳細な内訳が記載された見積もりを取得することも有効でしょう。市場では価格競争も見られますが、提示された料金の安さだけで判断するのは避けるべきです。提供される支援内容の質と範囲を考慮し、料金が妥当なものか、費用対効果を冷静に分析する視点が求められます。
チェック5:【連携】「担当者との相性」と「レスポンス速度」
登録支援機関は、長期にわたる協力関係を築くパートナーとなります。
実際に窓口となる担当者との相性や、コミュニケーションの取りやすさは、実務上、非常に重要です。可能であれば契約前に担当者と直接話し、信頼して業務を任せられるか、相談しやすい雰囲気かなどを見極めましょう。日々の連携において、問い合わせや相談に対する回答の速さ、対応の丁寧さも、円滑な協力関係を維持する上で欠かせない要素です。
チェック6:【専門性】「受け入れ分野」や「国籍」への知見
登録支援機関の中には、特定の産業分野(例:介護、建設、外食)や、特定の国籍の外国人材支援に特化したノウハウや強みを持つ機関も存在します。
自社が属する業界や、受け入れる外国人材の国籍に関して、深い専門知識、豊富な経験、あるいは関連するネットワークを有する機関を選ぶことで、より的確で質の高い支援が期待できます。機関のウェブサイト、パンフレット、担当者へのヒアリングなどを通じて、その専門性についても確認することをお勧めします。
信頼できる登録支援機関を選び出すための6つのチェックポイント、いかがでしたでしょうか。これらの観点を踏まえ、複数の候補機関を客観的に比較検討することが、最適なパートナー選びの鍵となります。さて、最後に、特定技能制度そのものを取り巻く最新の動向、特に2025年に予定されている制度変更点について触れておきましょう。常に最新の情報を把握しておくことも、適切な受け入れ体制を維持するためには不可欠です。
【2025年最新動向】知っておくべき制度変更と市場の動き
特定技能制度や、それを支える登録支援機関を取り巻く環境は、常に変化しています。社会の要請や制度運用の経験を反映し、より良い仕組みを目指して見直しが行われています。外国人材の受け入れを成功させ、適切な支援体制を維持するためには、こうした最新の動向を常に把握しておくことが欠かせません。
この章では、特に2025年4月1日現在で押さえておくべき制度の変更点や、登録支援機関市場の現状と今後の見通しについて解説します。
注目すべき2025年4月からの主な変更点
2025年4月1日から、特定技能制度の運用に関わるいくつかの重要なルール変更がスタートしました。注目すべき点として、まず義務的支援の一つである「定期的な面談」が挙げられます。
これまでは原則対面での実施が必要でしたが、本日以降は外国人材本人が同意すればオンライン形式での実施も認められることになりました。ただし、面談頻度は従来通り3ヶ月に1回以上が必要です。また、出入国在留管理庁への各種届出に使用する様式も更新されていますので、今後の申請や報告の際には新しい様式を使用する必要があります。さらに、特定技能外国人支援計画を作成する上で、地方公共団体が推進する多文化共生施策との連携を考慮することも求められるようになりました。
加えて、登録支援機関が車両を用いて出入国時の送迎を行う場合の道路運送法遵守に関する解釈も、より具体的に示されました。これらの変更は、支援実務の効率化を図るとともに、地域社会との連携強化を促す狙いがあると考えられます。
登録支援機関の増加と競争激化の実態
特定技能制度が定着するにつれて、外国人材の支援サービスを提供する登録支援機関の数も顕著に増加しました。現在では全国で1万を超える機関が登録され、受け入れ企業にとっては選択の幅が広がっています。しかし、その一方で、機関数の急増は市場における競争激化、特に価格競争を招いている側面もあります。
一部では、月額の支援委託料が1万円台前半という、以前では考えられなかったような低価格帯のサービスも登場しています。価格競争は利用者にとって一見メリットのように思えますが、過度な低価格化が支援内容の質の低下を招くリスクもはらんでいる点は、冷静に評価する必要があるでしょう。
今後の見通し:制度厳格化と淘汰の可能性
登録支援機関の中には、残念ながら十分な活動実態がない機関や、質の高い支援を提供する体制が整っていない機関も存在すると指摘されています。こうした状況を踏まえ、今後は登録支援機関の登録要件がより厳しくなったり、支援状況に対する監督・指導体制が強化されたりする可能性が十分考えられます。
結果として、質の低い機関や事業継続が困難な機関は市場から淘汰され、業界全体の健全化と質の向上が進むかもしれません。受け入れ企業にとっては、長期的に見て、より信頼できる質の高い支援機関を選びやすくなる環境へと変化していく可能性があります。
「育成就労」制度創設の影響は?
従来の技能実習制度に代わる新しい在留資格として「育成就労」制度の創設準備が進められています。この新しい枠組みにおいても、外国人材への適切な支援体制は引き続き重視される見込みです。現在の登録支援機関、あるいは類似の機能を持つ支援機関が、育成就労人材のサポートにおいても重要な役割を担い、その管理・支援能力の向上が図られる方向性が示されています。
特定技能制度と育成就労制度がどのように連携し、外国人材にとってより良いキャリアパスを形成していくのか、具体的な制度設計はまだ確定していない部分もありますが、外国人材の受け入れから育成、そして日本社会への定着を支援する取り組みの重要性は、今後ますます高まることは間違いないでしょう。
特定技能制度を取り巻く環境は、まさに変化の渦中にあります。施行されたばかりのルール変更、市場の競争環境、そして将来的な制度見直しの可能性。
これらの最新動向を踏まえた上で、自社の外国人材受け入れ・支援体制を定期的に見直していく姿勢が重要です。さて、本記事を通じて様々な角度から考察してきましたが、いよいよ最後のまとめに入ります。これまでの内容を整理し、最適な支援体制を構築するための要点を改めて確認しましょう。
まとめ:義務的支援と任意的支援を理解し、最適な支援体制を構築しよう
本記事では、特定技能外国人材の受け入れを検討・実施されている人事担当者の皆様が抱える疑問や課題に応えるべく、「義務的支援」と「任意的支援」を中心に、制度の基本から具体的な支援内容、体制構築の選択肢、信頼できるパートナー選びのポイント、そして最新の制度動向までを網羅的に解説してまいりました。
特定技能外国人材のスムーズな受け入れと活躍のために、今、何をすべきか、その道筋が見えてきましたでしょうか。
改めて強調したいのは、定められた10項目の「義務的支援」を確実に実施することは、企業が果たすべき最低限の責任であるという点です。
法令遵守は、リスク管理の基本となります。しかし、これからの時代、外国人材に選ばれ、長く活躍し続けてもらうためには、義務の範囲を超えた「任意的支援」への戦略的な投資が不可欠です。任意的支援は、単なる福利厚生ではなく、外国人材の定着率向上、モチベーションアップ、ひいては企業全体の生産性や採用ブランドの強化に直結する重要な経営課題と捉えるべきでしょう。
どのような支援体制を構築するのが最適解かは、企業の規模、業種、リソース、そして理念によって異なります。「自社支援」で密な関係を築くか、「登録支援機関への委託」で専門性と効率を求めるか、あるいは両者を組み合わせる「一部委託」か。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の実情に照らし合わせて、最も効果的で持続可能な方法を選択することが重要です。
外国人材は、単なる労働力ではなく、多様な価値観と可能性をもたらす大切な仲間です。彼らが安心して、その能力を最大限に発揮できる環境を整えることは、間違いなく企業の未来を明るく照らすでしょう。
この記事が、貴社における外国人材支援体制の整備・改善に向けた具体的なアクションのきっかけとなれば、これ以上の喜びはありません。
もし、「自社だけでは不安がある」「専門家の意見を聞きたい」「そもそも特定技能ビザの取得は可能なのか?」といった疑問や具体的なご相談事項がございましたら、どうぞ一人で悩まず、専門家にご相談いただくことも有効な手段です。
関連するオススメ記事
- 登録支援機関の義務的支援その⑤「公的手続きへの同行」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その④「生活オリエンテーション」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その③「住居の確保・契約支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その②「出入国時の送迎」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その①「事前ガイダンス」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援・任意的支援とは?人事担当者が知るべき違い・費用・選び方を徹底解説
- 特定技能1号で家族の帯同ができる?要件・必要書類について徹底解説
- 特定技能外国人の転職について|要件・手続き・注意点を解説
- 特定技能ビザから技人国ビザへの変更方法について|要件・方法・注意点を解説
- 特定技能ビザで働く【外国人】のメリット・デメリットについて