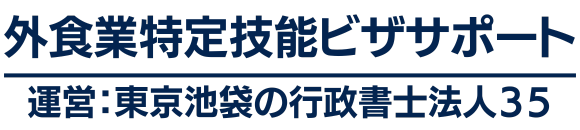登録支援機関の義務的支援その①「事前ガイダンス」とは?|特定技能外国人
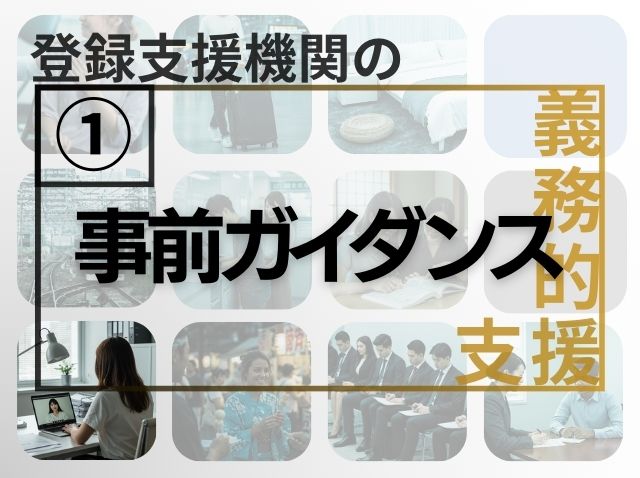
特定技能外国人材の受け入れ準備を進める中で、「事前ガイダンス」の実施について、具体的な進め方に悩んでいませんか。「義務的支援として必須なのは理解しているが、何を、いつ、どう伝えれば良いのだろう?」「なぜ、事前ガイダンスがそれほど重要なのか?」――外国人材の受け入れを担う人事ご担当者であれば、一度はこうした疑問に突き当たるかもしれません。この事前ガイダンスは、単なる通過儀礼ではなく、外国人材が安心して日本での新生活を始め、入社後の認識のずれや思わぬトラブルを防ぐために、非常に大きな意味を持つ「最初の重要なステップ」なのです。
この記事では、そんな人事担当者の皆様が抱える疑問を解消し、自信を持って事前ガイダンスに取り組めるよう、特定技能制度における義務的支援としての「事前ガイダンス」に徹底的に焦点を当てます。その目的や法的根拠といった基礎知識から、説明が必須となる項目、具体的な実施方法、そして見落としがちな注意点に至るまで、実務に必要な情報を網羅的かつ分かりやすく解説いたします。最後までお読みいただければ、事前ガイダンスの全体像が明確になり、適切な準備と実施が可能になるはずです。
適切な事前ガイダンスを通じて、これから仲間となる外国人材との良好な信頼関係を築く第一歩を踏み出しましょう。まずは、事前ガイダンスの基本的な定義や、なぜそれが必要なのかという目的から、詳しく見ていくことにします。
目次
- 特定技能の義務的支援における事前ガイダンスの基本
- 特定技能の事前ガイダンス:具体的な実施方法とルール
- 【最重要】特定技能の事前ガイダンスで必ず説明すべき必須項目
- さらに丁寧なサポートへ!推奨される任意項目
- 特定技能の事前ガイダンスを成功させる!実施上の重要ポイントと注意点
- 【混同注意!】「生活オリエンテーション」と事前ガイダンスの違い
- 事前ガイダンスの負担軽減策:登録支援機関への委託
- まとめ
まずは基本から!特定技能の義務的支援における事前ガイダンスの基本
事前ガイダンスの具体的な内容を学ぶ前に、まずはその土台となる基本的な知識、すなわち定義、目的、法的な位置づけ、そして実施に関するルールをしっかり理解しておきましょう。基本を押さえることで、事前ガイダンスがいかに重要であるか、そして実施する上で何に注意すべきかが見えてきます。
事前ガイダンスとは?特定技能外国人に対する「入国前の説明義務」
事前ガイダンスとは、特定技能1号の在留資格で日本での就労を予定している外国人材に向けて、日本での仕事や生活を始める「前」に行う、法律に基づいたオリエンテーションや説明会のことです。受け入れ企業や登録支援機関が任意で行うものではなく、実施することが明確に義務付けられている重要なプロセスと認識してください。
なぜ必要?特定技能における事前ガイダンスの重要な目的
事前ガイダンスがこれほど重要視されるのには、複数の大切な目的があります。
- 第一の目的は、外国人材が抱えるであろう、見知らぬ国での新しい生活や仕事に対する不安を和らげること。正確な情報を事前に得ることで、安心して来日・就労に臨めます。
- 第二に、雇用契約の内容、特に労働条件や実際の業務、そして日本での生活環境について入国前に正確な理解を促し、入国後の「こんなはずではなかった」という認識の齟齬(ミスマッチ)を未然に防ぐこと。
- 第三に、入国後の手続きや日常生活に必要な知識をあらかじめ提供することで、日本でのスムーズなスタートアップを力強く支援すること。
- そして最後に、受け入れ企業が法律で定められた外国人材への支援義務を適切に果たしていることを示す、コンプライアンスの観点からの目的も含まれます。
法的根拠は?特定技能制度の義務的支援としての位置づけ
事前ガイダンスの実施義務は、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)や特定技能制度に関する各種の省令、そして出入国在留管理庁が示す運用要領などによって具体的に定められています。特定技能1号外国人に対して受け入れ企業等が実施すべき「義務的支援」は全10項目ありますが、事前ガイダンスはその中でも、外国人材が日本での活動を開始する前の、一番初めに行われるべき重要な支援項目として明確に位置づけられています。
誰が・いつ・誰に?事前ガイダンスの実施責任者・タイミング・対象者
事前ガイダンスを実施する責任は、原則として、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)自身にあります。ただし、専門的な知識やリソースの観点から自社での実施が難しい場合には、出入国在留管理庁に正式に登録された「登録支援機関」へ支援業務の一部または全部を委託することも可能です。
実施しなければならないタイミングも厳格に定められており、「外国人材との間で雇用契約を締結した後」かつ、「日本への入国に必要な在留資格認定証明書の交付申請前(または国内在住者の場合は在留資格変更許可申請前)」に行う必要があります。入国直前や入国後に行うものではない点に、十分注意してください。
そして、事前ガイダンスの対象となるのは、主に「特定技能1号」の在留資格で日本での就労を予定している外国人材です。より高度な専門性を持つ「特定技能2号」の外国人材は、事前ガイダンスを含む義務的支援の対象とはなりません。
事前ガイダンスの基本的な意味合いや目的、そして実施に関する基本的なルールについて、整理できたでしょうか。この基礎知識を踏まえた上で、次は、実際に事前ガイダンスを「どのように」行えばよいのか、その具体的な実施方法や守るべき詳細なルールについて、さらに詳しく解説していきます。
特定技能の事前ガイダンス:具体的な実施方法とルール

事前ガイダンスの基礎知識を理解した次は、具体的に「どのように実施すべきか」という方法論と、守らなければならないルールを確認していきましょう。定められた手順とルールに従って正しく実施することが、事前ガイダンス本来の目的を達成し、後の無用なトラブルを未然に防ぐ鍵となります。
【方法】対面?オンライン?特定技能ガイダンスの実施形式と注意点
事前ガイダンスを実施する形式は、必ずしも対面に限定されていません。外国人材と直接顔を合わせて行う「対面」形式はもちろんのこと、ZoomやTeamsといったツールを用いた「オンライン」形式(ビデオ通話)での実施も可能です。電話での実施もルール上は可能ですが、互いの表情を見ながら対話できるビデオ通話の方が、より丁寧な説明や相手の理解度を把握する上で望ましい場面が多いでしょう。
絶対に避けなければならないのは、説明資料や雇用契約書を送付したり、メールで情報を伝えたりするだけで完結させてしまうことです。書面や電子ファイルのみの情報提供では、法律で定められた事前ガイダンスを実施したことにはなりませんので、十分注意が必要です。
オンライン形式を選択する場合は、いくつかの留意点があります。
- 双方で安定したインターネット接続環境を確保すること。
- 画面越しであっても、説明を受けているのが確かに申請者本人であることを確認すること。
- 説明資料を画面上で共有したり、事前に送付したりする工夫も理解を助けること。
- プライバシーに配慮し、背景に個人情報等が映り込まないように注意すること。
- 情報セキュリティが確保された安全な通信手段を選ぶこと。
対面は丁寧ですがコストや時間がかかり、オンラインは効率的ですが環境整備やITリテラシーが求められる、という点を考慮し、状況に応じた最適な方法を選ぶことが重要です。
【時間】最低「3時間以上」を確保!特定技能ガイダンスの所要時間
事前ガイダンスにかけるべき時間について、法律で厳密に「〇時間」と定められているわけではありませんが、出入国在留管理庁からは「最低でも3時間以上」の時間を確保することが推奨されています。なぜなら、後述するように説明すべき必須項目が非常に多岐にわたる上に、一方的に情報を伝えるだけでなく、外国人材からの質問に丁寧に答え、内容を本当に理解してもらえたかを確認するための時間も十分に取る必要があるからです。形式的に時間を満たすことだけを考えるのではなく、中身の伴った、分かりやすく丁寧な説明とコミュニケーションを通じて、質疑応答を含めて十分な時間を確保するという意識が大切になります。
【言語】最重要!外国人本人が理解できる言語での説明義務(通訳手配)
実施方法に関するルールの中で、最も重要かつ厳格に守らなければならないのが、使用する言語に関する規定です。事前ガイダンスは、説明を受ける外国人材本人が「十分に内容を理解できる言語」で実施することが絶対条件とされています。日本語能力が十分でない外国人材に対して日本語のみで説明を行うことは認められません。その場合は、必ず、本人の母国語など、確実に内容を理解できる言語の通訳者を介して説明を行う法的義務があります。
この通訳者の手配は、受け入れ企業または委託を受けた登録支援機関の責任において行わなければなりません。通訳者を選定する際は、単に語学力があるだけでなく、専門用語も含めて正確に内容を伝えられる能力、そして中立的な立場で通訳できる資質を持っているかを確認することが望ましいでしょう。
【記録】実施記録は必須!署名入り確認書の作成・提出義務
事前ガイダンスを適切に実施したことを証明するために、必ず実施記録を作成し、保管する必要があります。具体的には、「事前ガイダンスの確認書」という書面を作成します。この確認書には、ガイダンスを実施した日時、場所(もしくはオンライン等の実施方法)、説明した内容の要点、説明者の氏名、そして説明を受けた外国人材本人の氏名を明記します。さらに最も重要な要素として、説明された内容を外国人材本人が十分に理解したことを示す「本人の署名」が不可欠です。この署名が入った確認書は、後の在留資格申請手続きにおいて、出入国在留管理庁へ提出することが義務付けられている、法的に重要な書類となります。
事前ガイダンスを実施する上での具体的な方法と、遵守すべきルールについて確認できたでしょうか。実施形式、所要時間、使用言語、そして実施記録の作成、いずれも外国人材のスムーズな受け入れのために欠かせない要素です。さて、実施方法のルールを理解したところで、いよいよ事前ガイダンスの核心、「何を説明しなければならないのか」という必須の説明項目について、次の章で詳しく掘り下げていきます。
【最重要】特定技能の事前ガイダンスで必ず説明すべき必須項目
事前ガイダンスの実施方法を理解したら、次は最も重要な「説明内容」そのものに焦点を当てます。ここで挙げる項目は、法律によって説明が義務付けられている必須事項であり、外国人材が日本で安心して働き、生活するための基盤となる情報です。これらの情報を漏れなく、かつ正確に伝えることが、後の誤解やトラブルを防ぎ、良好な信頼関係を築く上で決定的に重要となります。
-
雇用契約・労働条件:働く上での約束事を明確に
外国人材が最も関心を寄せるであろう雇用契約、特に労働条件に関する詳細な説明は不可欠です。具体的にどのような仕事(業務内容)を担当するのか、報酬(基本給、各種手当、昇給・賞与の有無、残業代の計算方法など)、労働時間(始業・終業時刻、休憩、シフト制の詳細など)、休日や休暇の種類と日数、そして実際に働く場所(就業場所)といった情報を、一切の誤解が生じないよう具体的に伝えます。もし、業務内容に高所作業や特定の機械操作など、危険または有害なものが含まれる場合は、そのリスクと安全衛生に関する注意喚起も必ず行う必要があります。
-
活動内容:在留資格で認められた仕事の範囲
特定技能の在留資格は、定められた特定の産業分野・業務区分内での就労を前提としています。そのため、取得する(または変更する)在留資格で「許可されている仕事の範囲」と、「行ってはいけないこと」を明確に説明しなければなりません。例えば、資格で認められた専門業務とは異なる単純作業のみに従事させることはできないことや、原則として副業(資格外活動)は認められないことなどをはっきりと伝達します。これは、不法就労のリスクを避けるための重要な説明です。
-
【要注意】禁止行為:不当な契約から外国人を守るために
外国人材を不当な束縛や搾取から保護するため、法律で厳しく禁止されている行為について、事前ガイダンスで明確に説明する義務があります。受け入れ企業や仲介者などが、就職を理由に本人や家族から保証金を徴収したり、預金通帳などの財産を管理したりすることは絶対に禁止されています。また、雇用契約の不履行(中途退職など)を理由とした違約金の定めや、損害賠償を予定する契約も無効です。さらに、パスポートや在留カードを強制的に取り上げる行為も認められません。これらの禁止事項を明確に伝え、万が一そのような要求を受けた場合の相談窓口も知らせることが重要です。
-
費用負担:本人の負担はNG!費用のルールを透明に
金銭に関するルールも、誤解がないように透明性をもって説明する必要があります。来日のための渡航費や住居の初期費用など、日本での活動準備にかかる費用について、誰が何を負担するのかを具体的に明示します。ここで最も重要なルールは、事前ガイダンスを含む「義務的支援」の実施にかかる費用は、名目に関わらず、絶対に外国人材本人に負担させてはならない、ということです。企業または登録支援機関が全額負担する旨をはっきりと伝えましょう。もし、例外的に本人負担となる費用(母国での特定の手続き費用など)が存在する場合は、その内容と金額を正確に説明することが求められます。
-
入国手続き:来日・在留資格変更の流れを案内
日本へ入国し、特定技能として就労を開始するための一連の手続きについても説明が必要です。海外から新たに来日するケースでは、在留資格認定証明書の申請・受領から、本国での日本査証(ビザ)申請、そして日本到着後の入国審査や在留カード受領までの流れを説明します。既に他の在留資格で日本に滞在している方の場合は、在留資格変更許可申請の手続きを中心に解説するなど、個々の状況に応じた適切な案内を行います。
-
受ける支援:入国後のサポート内容を伝え安心感を
入国後、受け入れ企業や登録支援機関からどのようなサポートを受けられるのか、その全体像を示すことも外国人材の安心に繋がります。具体的には、義務的支援として法律で定められている10項目(出入国時の送迎、住居確保支援、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談対応など)の概要を説明します。「困ったときにはこういうサポートがある」と事前に知ることで、日本での生活に対する不安を和らげることができます。
-
相談先:一人で悩まないための相談窓口を明示
仕事上の悩み、生活上の不安、あるいはハラスメントや差別といった問題に直面した際に、誰に、どのように相談すればよいのかを具体的に知らせておくことは非常に重要です。まずは、受け入れ企業の担当窓口や、支援を委託している登録支援機関の担当者の連絡先を明確に伝えます。加えて、企業には相談しにくい内容に対応するため、出入国在留管理庁、労働基準監督署、法務局の人権相談窓口など、信頼できる公的な相談機関の連絡先や利用方法についても情報提供することが義務付けられています。
-
担当者情報:支援してくれる人の顔と連絡先を告知
実際に事前ガイダンスを担当している人物の氏名や所属、連絡先はもちろん、入国後に外国人材の生活や仕事の支援を直接担当する予定の人物(受け入れ企業の担当者や登録支援機関の担当者)がいる場合は、その氏名と連絡先(電話番号、メールアドレスなど)を事前に明確に伝えておく必要があります。誰に頼ればよいかが分かっていることは、外国人材にとって大きな安心材料となります。
-
その他:安全衛生など、その他の必須説明事項
上記8項目以外にも、伝達が義務付けられている、あるいは伝えておくべき重要な事項があります。例えば、従事する業務内容に応じた労働安全衛生に関する基本的な注意事項、日本の社会保険(健康保険、厚生年金など)や税金に関する基本的な仕組み、そして地震や台風などの自然災害発生時や緊急時の連絡体制などです。その他、受け入れ企業の就業規則や寮のルールなど、外国人材が遵守すべき事項があれば、合わせて説明することが望ましいでしょう。
以上が、事前ガイダンスにおいて法律で説明が義務付けられている必須項目となります。項目数が多く、内容も多岐にわたりますが、一つひとつが外国人材の日本での安定したスタートを切るために欠かせない情報です。
これらの必須項目に加えて、さらに任意で情報提供を行うことで、より親切で丁寧なサポートが可能になります。次の章では、説明することが推奨される任意項目についてご紹介します。
さらに丁寧なサポートへ!特定技能の事前ガイダンスで推奨される任意項目

前章で解説した法律で定められた必須項目を確実に伝えることは大前提ですが、特定技能外国人材の不安をさらに和らげ、よりスムーズな日本での生活開始を力強く後押しするために、伝えておくと非常に喜ばれる「任意項目」の情報提供も検討しましょう。これらは義務ではありませんが、実施することで、受け入れ企業としての温かい配慮が伝わり、外国人材との良好な関係を築く大きな助けとなります。
日本の気候や服装に関する具体的なアドバイス
特に母国と日本の気候風土が大きく異なる外国人材にとって、服装に関する情報は実用的で大変助かる情報です。来日予定時期の日本の気候特性、例えば春や秋の朝晩の気温差の大きさ、梅雨時期の降雨、夏の蒸し暑さ、冬の厳しい寒さなどを具体的に伝えましょう。
その上で、「重ね着できる服が便利です」「冬はしっかりした防寒着が必要です」「梅雨には傘やレインコートが欠かせません」といった、具体的な服装のアドバイスを提供すると親切です。慣れない環境での体調管理をサポートすることにも繋がります。
持参すべき物・持ち込み禁止品に関する情報提供
日本での新生活スタートにあたり、自国から持参すると便利な物、逆に持ち込むと問題になる可能性がある物についての情報も有益です。例えば、普段から服用している常備薬(成分によっては注意が必要な場合も)特定の宗教儀式に必要な物品、あるいは日本で手に入りにくい故郷の調味料(持ち込み可能な範囲で確認が必要)などが考えられます。一方で、肉製品全般、果物や植物の一部、コピー商品、特定の医薬品などは、日本の検疫や法律によって持ち込みが厳しく制限・禁止されている場合があります。こうした禁止・制限品について事前に注意喚起することで、空港での思わぬトラブルを避けることができます。
来日初期の生活費目安や便利な生活情報
来日してから最初の給与を受け取るまでの期間、どれくらいの生活費が必要になるか、その具体的な目安を伝えておくことも、外国人材の経済的な不安を軽減します。食費、交通費、日用品の購入費、通信費など、想定される主な支出項目を挙げながら、日本円でどれくらいの現金を用意しておくと当面安心か、具体的な金額のイメージを示すと良いでしょう。加えて、企業から制服、作業着、寝具、基本的な家具家電などが支給される場合は、その旨を明確に伝えておくと、本人が準備する荷物を減らす上で大きな助けとなります。
さらに、日本の公共交通機関で便利な交通系ICカード(SuicaやPASMOなど)の使い方や、緊急時に連絡すべき日本の連絡先リスト(警察110番、消防・救急119番など)といった、実用的な生活情報も提供すると喜ばれるでしょう。これらの任意項目はあくまで一例であり、受け入れる外国人材の状況に合わせて、役立つと思われる情報を積極的に提供する姿勢が大切です。
必須項目に加えて、こうした任意項目に関する情報を提供することは、受け入れ企業が外国人材一人ひとりの状況を考え、細やかに配慮していることの表れです。このような丁寧なコミュニケーションが、結果として深い信頼関係の礎となるでしょう。
さて、伝えるべき内容が見えてきたところで、次は、情報提供を行う際の伝え方、つまり事前ガイダンスをより効果的に、そして確実に成功させるための実施上の重要なポイントや注意点について、詳しく見ていくことにします。
特定技能の事前ガイダンスを成功させる!実施上の重要ポイントと注意点
事前ガイダンスで何を伝えるべきかを理解したら、次は「どのように伝えれば効果的か」という実施方法の質を高める視点が重要になります。単に必須項目を説明するだけでなく、いくつかの重要なポイントを押さえることで、外国人材の理解度は深まり、安心して日本でのスタートを切れるようになります。ここでは、事前ガイダンスを成功に導き、後のトラブルを未然に防ぐための実践的なポイントと注意点を解説します。
一方通行はNG!質疑応答で双方向性を確保する
事前ガイダンスを、説明者が一方的に情報を伝えるだけの場にしてはいけません。最も大切な心得の一つは、常に「双方向のコミュニケーション」を意識することです。説明の途中や最後に、必ず質疑応答の時間を十分に設けましょう。そして、外国人材がどんな些細なことでも気軽に質問できるような、オープンな雰囲気を作ることが肝心です。「何か質問はありませんか?」と全体に問いかけるだけでなく、時には「給与のことで、何か分かりにくい点はありましたか?」など、項目を特定して問いかけ、発言を促す工夫も有効です。丁寧な質疑応答を通じて疑問や不安を解消することが、真の理解と信頼に繋がります。
理解度確認の徹底:外国人材が本当に理解したかを確認する方法
説明した内容を、外国人材が表面上だけでなく、実質的に理解しているかを確認するプロセスは絶対に省略できません。単に「分かりましたか?」と尋ね、「はい」という返答を得るだけでは、本当の理解度は測れない可能性があります。
文化的な配慮から、十分に理解していなくても否定的な返事を避け、「はい」と答えるケースも少なくないからです。より確実な方法として、例えば「今説明した残業代の計算方法について、あなたの言葉で説明してもらえますか?」と復唱を促したり、「もし病気で会社を休む場合、どういう手続きが必要だと説明しましたか?」と具体的な状況を想定して質問したり、あるいは重要事項に関する簡単な確認クイズを実施したりする方法が考えられます。理解が不十分な点があれば、焦らず、言葉を変えたり図を用いたりしながら、相手が納得するまで説明し直す姿勢が求められます。最終的な確認書への署名は、この理解度確認をしっかりと行った上で進めるべきです。
情報の正確性・最新性を担保する重要性
事前ガイダンスで提供する情報は、その正確性と最新性が命です。
特に、在留資格制度、労働関連の法律、社会保険制度、各種行政手続きに関する情報は、法改正などによって頻繁に変更される可能性があります。古い情報や誤った情報に基づいて説明してしまうと、外国人材に予期せぬ不利益を与えたり、コンプライアンス上の問題を引き起こしたりする重大なリスクがあります。
受け入れ企業や登録支援機関は、出入国在留管理庁の公式ウェブサイト、厚生労働省や関係省庁、地方自治体などが発信する信頼できる一次情報を定期的に確認し、ガイダンスの内容や使用する資料を常に最新の状態に保つ努力を怠ってはなりません。
トラブル回避のために:ガイダンス不足による失敗事例から学ぶ
もし事前ガイダンスでの説明が不十分だったり、内容が不正確だったりした場合、どのような問題が起こりうるでしょうか。
例えば、労働時間や休日に関する認識の違いから「契約と違う」と感じてしまい、早期離職に繋がるかもしれません。あるいは、副業が原則禁止であることを理解しておらず、軽い気持ちでアルバイトをしてしまい、結果として在留資格の更新が不許可になるという深刻な事態も考えられます。また、保証金や違約金に関する禁止事項を知らずに不当な要求に応じてしまったり、住民登録などの重要な行政手続きを期限内に行わなかったりするケースも起こりえます。
こうした様々なトラブルを未然に防ぐためにも、丁寧で正確、かつ分かりやすい事前ガイダンスの実施がいかに重要であるか、改めて認識することが大切です。
双方向の対話、確実な理解度の確認、情報の正確性と最新性の維持、そして潜在的なトラブルへの意識。これらのポイントを実践することで、事前ガイダンスは形式的な義務履行を超え、外国人材との強固な信頼関係を築くための価値ある機会となるはずです。
ところで、外国人材への説明機会としては、事前ガイダンスの他に「生活オリエンテーション」というものもあります。名前は似ていますが、目的や内容は異なります。次の章では、この二つの違いを明確にし、混同しないように整理していきましょう。
【混同注意!】特定技能の「生活オリエンテーション」と事前ガイダンスの違い
ここまで「事前ガイダンス」に焦点を当てて解説を進めてきましたが、特定技能の義務的支援には、もう一つ「生活オリエンテーション」という名称の似た項目が存在します。
どちらも外国人材への重要な情報提供である点は共通していますが、その目的、実施されるタイミング、そして説明内容の重点は明確に異なります。両者の違いを正しく理解し、混同しないように整理しておくことが、適切な支援実施のために大切です。
実施タイミングの違い:入国前(事前ガイダンス)vs 入国後(生活オリエンテーション)
最も明確で分かりやすい違いは、それぞれの支援を実施するタイミングにあります。
これまで詳しく見てきた「事前ガイダンス」は、その名の通り、外国人材が日本に入国する「前」、あるいは日本在住者が在留資格を変更する許可申請の「前」に実施されるものです。日本での新たな生活や仕事が始まる前に、基本的なルールや契約内容を確認し、不安を解消することを目的としています。
それに対して、「生活オリエンテーション」は、外国人材が日本に無事入国した「後」できるだけ速やかに(遅滞なく)実施することが求められます。こちらは、実際に日本での生活をスタートさせた外国人材に向けて、より実践的な情報を提供することが主眼となります。
内容の焦点の違い:基本的重要事項 vs 実践的・詳細な生活情報
実施するタイミングが異なることから、説明内容の焦点も自ずと変わってきます。
「事前ガイダンス」では、雇用契約の内容、給与や労働時間といった労働条件、在留資格で認められる活動範囲、保証金や違約金に関する禁止事項、これから受ける支援の全体像など、日本で働く上での基本的な権利・義務や、契約上の重要な約束事に関する説明が中心です。いわば、日本での就労と生活の基盤となる「ルールブック」の要点を伝える場と言えるでしょう。
一方、「生活オリエンテーション」では、入国後の「リアルな日常生活」に直結する、より具体的で実践的な情報の提供に重点が置かれます。
例えば、日本の交通ルール(自転車の安全な乗り方や標識の意味なども含む)銀行・郵便局・病院・役所といった公共機関の利用方法、地域ごとに異なるゴミの分別・収集ルールの詳細、そして地震や台風などの自然災害発生時の具体的な避難方法や安否確認手段、緊急連絡先などが主要なテーマです。さらに、社会保険や税金、年金に関する具体的な手続きなども、生活オリエンテーションで詳しく説明されることが多い内容です。推奨される実施時間も、事前ガイダンス(3時間以上)と比較して生活オリエンテーション(8時間以上)の方が長く設定されており、より多くの時間をかけて詳細な情報提供が行われます。
このように、事前ガイダンスと生活オリエンテーションは、実施時期も内容の重点も異なる、それぞれ独立した重要な義務的支援です。どちらか一方を行えばもう一方は不要、ということにはなりません。それぞれの目的と役割を正確に理解し、適切なタイミングで、求められる内容の情報提供を確実に行うことが必要不可欠なのです。
事前ガイダンスと生活オリエンテーション、それぞれの特性と相違点について、明確にご理解いただけたでしょうか。どちらの支援も外国人材のスムーズな受け入れに欠かせませんが、特に事前ガイダンスは、入国前の限られた時間で、多岐にわたる重要事項を、外国人材が理解できる言語で説明する必要があり、受け入れ企業にとっては少なからぬ負担となる場合があります。
そこで有効な選択肢となるのが、専門家である登録支援機関への業務委託です。次の章では、事前ガイダンスの業務を登録支援機関へ委託する際のメリットや注意点について解説していきます。
事前ガイダンスの負担軽減策:「登録支援機関への委託」という選択肢
特定技能外国人材の受け入れに不可欠な事前ガイダンスですが、その準備と実施には専門知識や多言語対応、そして相応の時間と労力が必要です。
特に初めての受け入れや、社内に十分なリソースがない場合、その負担は決して小さくありません。こうした課題に対する有効な解決策の一つが、外国人支援の専門家である「登録支援機関」へ事前ガイダンス業務を委託するという選択肢です。この章では、委託によって得られるメリットと、委託を成功させるための注意点について解説します。
専門性と効率化!登録支援機関に事前ガイダンスを委託するメリット
登録支援機関への委託には、受け入れ企業にとって魅力的なメリットが複数存在します。
- 「専門性」の活用:外国人支援に関する法規や実務に精通しており、質の高い、法令に準拠したガイダンス実施が期待できます。
- 「企業負担の大幅な軽減」:資料作成、通訳手配、実施時間の確保といった煩雑な準備から解放され、コア業務に集中できます。
- 「多言語対応力」:多様な言語に対応できる体制があり、自社では対応困難な言語でも丁寧なガイダンスが可能となります。
- 「コンプライアンス遵守の安心感」:説明漏れや不正確な情報提供といったリスクを最小限に抑え、適切なガイダンス運営が期待できます。
費用・連携は要確認!委託する場合の注意点
多くの利点がある一方で、登録支援機関への委託を検討する際には、いくつか注意すべき点もあります。
- 「費用の確認」:料金体系は機関ごとに様々です。必ず詳細な見積もりを取り、追加費用も含めて費用対効果を慎重に見極めましょう。
- 「委託=丸投げ」ではない:受け入れ企業としての最終的な責任は残ります。委託後も情報を共有し、登録支援機関と密に連携し、実施状況を把握する必要があります。
- 「委託範囲の明確化」:事前ガイダンス「だけ」を委託するのか、他の義務的支援も併せて委託するのか、契約時に必ず明確にしましょう。
登録支援機関への委託は、事前ガイダンス実施に伴う企業の負担を効果的に軽減し、専門的で質の高い支援を実現するための有力な選択肢です。しかし、そのメリットを最大限引き出すためには、信頼できる機関を吟味して選び、費用や委託範囲を明確にし、そして委託後も責任ある連携を継続していく姿勢が求められます。自社のリソースや状況を考慮し、委託という方法を賢く活用することを検討してみてはいかがでしょうか。
事前ガイダンスの実施方法から、負担を軽減するための委託という選択肢まで、具体的なイメージが掴めてきたかと思います。それでは、本記事を通じて学んできたことの総仕上げとして、事前ガイダンスの重要性を改めて心に刻み、外国人材との良好な関係構築に向けたポイントを最終章でまとめていきましょう。
まとめ:適切な事前ガイダンスで特定技能外国人との信頼関係を築こう
本記事では、特定技能外国人材の受け入れに際して不可欠となる義務的支援の第一歩、「事前ガイダンス」に焦点を当て、その基本から具体的な実施方法、説明すべき必須項目、任意項目、成功のためのポイント、そして委託という選択肢まで、多角的に解説を進めてまいりました。事前ガイダンスの全体像と、その適切な実施がいかに重要であるか、深くご理解いただけたことと存じます。
事前ガイダンスは、単に法律で定められた手続きをこなす作業ではありません。これから遠い異国で新しい挑戦を始める外国人材が抱えるであろう期待と不安に寄り添い、正確な情報を提供することで安心を与え、そして受け入れ企業と外国人材との間に初めて築かれる「信頼の架け橋」となる、極めて重要なコミュニケーションの場です。ここで丁寧な対話を行い、相互理解の土台をしっかりと築くことが、その後の円滑な受け入れ、職場への適応、そして長期的な活躍と定着に繋がるのです。
法律で定められたルールを守り、必須項目を漏れなく伝えることは当然の責務です。しかし、それに加えて、双方向のコミュニケーションを大切にし、相手の理解度を確認しながら、必要であれば任意項目も活用して丁寧な情報提供を心がけること。
この「質」を追求する姿勢こそが、事前ガイダンスを成功させ、ひいては外国人材と共に企業の未来を築いていくための鍵となります。適切な事前ガイダンスは、外国人材のためだけでなく、受け入れ企業自身の持続的な成長にとっても、価値ある投資と言えるでしょう。
この記事が、貴社における事前ガイダンスの質向上、そして特定技能外国人材とのより良い関係構築の一助となることを心より願っております。
私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
関連するオススメ記事はこちら
- 登録支援機関の義務的支援その⑤「公的手続きへの同行」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その④「生活オリエンテーション」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その③「住居の確保・契約支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その②「出入国時の送迎」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その①「事前ガイダンス」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援・任意的支援とは?人事担当者が知るべき違い・費用・選び方を徹底解説
- 特定技能1号で家族の帯同ができる?要件・必要書類について徹底解説
- 特定技能外国人の転職について|要件・手続き・注意点を解説
- 特定技能ビザから技人国ビザへの変更方法について|要件・方法・注意点を解説
- 特定技能ビザで働く【外国人】のメリット・デメリットについて

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート