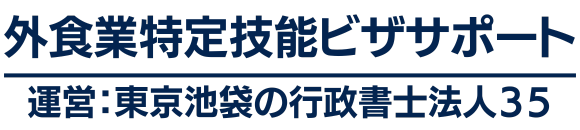登録支援機関の義務的支援その③「住居の確保・契約支援」とは?|特定技能外国人

初めての特定技能外国人受け入れ、心よりお祝い申し上げます。
大きな期待とともに
「住居の手配は具体的にどう進めれば良いのだろうか?」
「銀行口座開設や携帯電話の契約手続きは、会社としてどこまでサポートする必要があるのだろう?」
など、様々な疑問やご不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。
特定技能制度における義務的支援の中でも、手続きが多く言語の壁も無視できない「住居確保」や「生活に必要な契約支援」は、人事担当者様にとって特に気がかりな部分かもしれません。
本記事は、特定技能の義務的支援に関して人事担当者様が抱える疑問や不安を解消することを目的に作成しました。「住居確保」と「生活に必要な契約支援」について、具体的に何を、どこまで、どのように支援すれば良いのか、企業が守るべきルールや注意点、そして費用負担の基本的な考え方まで、詳細に解説いたします。
特定技能ビザ申請を専門とする行政書士が、最新の法令情報に基づき丁寧に説明を行うため、この記事を最後までお読みいただければ、受け入れ準備に自信を持って取り組めるようになるでしょう。
目次
- 特定技能の義務的支援とは?住居・契約支援の重要性
- 支援① 住居確保支援:何をどこまでやるべきか?
- 支援② 生活に必要な契約支援:具体的なサポート内容
- 支援をスムーズに進めるためのポイントと注意点
- まとめ
特定技能の義務的支援とは?住居・契約支援の重要性
この章では、まず特定技能制度で定められている義務的支援の全体像をつかんでいただきます。
その上で、多くの支援項目の中でも特に「住居確保」と「生活に必要な契約支援」がなぜ重要視されるのか、その理由について一緒に見ていきましょう。
そもそも「義務的支援」って何?10項目の全体像と目的
特定技能制度では、特定技能1号の在留資格を持つ外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)に対し、法律に基づいて様々な支援を行うことが義務付けられています。サポートすべき項目は全部で10項目あり、広範囲にわたります。
これらの支援は、特定技能外国人が日本の社会や職場環境にスムーズに適応し、安定した職業生活と日常生活を送れるようにすることが目的です。受け入れ企業が責任を持ってサポート体制を整えることが、制度上しっかりと求められているわけですね。
なぜ「住居」と「生活契約」の支援が特に重要なのか?
数ある義務的支援の中でも「住居の確保」と「生活に必要な契約の支援」は特に大切だと考えられています。その背景には、外国人ご本人が日本で住居を探し、契約を結ぶ際の難しさがあります。
例えば、賃貸契約を結ぶ際に連帯保証人が必要となる場合が多く、日本に頼れる親族などがいない外国人にとっては、これが大きなハードルになることも。また、契約に関する複雑な手続きや専門用語の理解、日本ならではの商慣習への対応も求められます。
電気、ガス、水道といったライフライン、銀行口座、携帯電話などの契約も同様で、手続きの煩雑さや言葉の壁から、外国人本人だけではなかなかスムーズに進められないのが実情です。安心して暮らせる住まいと、日常生活に不可欠なサービスを利用できる環境は、外国人が日本で安定した生活を送るためのまさに土台と言えるでしょう。
この生活基盤がしっかりと整って初めて、特定技能外国人は仕事に集中でき、持っている力を十分に発揮して、会社に貢献してくれるようになるのです。
義務的支援の全体像や、住居・契約支援の大切さについては、ご理解いただけたのではないでしょうか。
支援① 住居確保支援:何をどこまでやるべきか?

ここからは、具体的な支援内容について詳しく見ていきましょう。まずは、特定技能外国人の生活の基盤となる「住居確保」に関する支援です。
受け入れ企業としてどのような方法で支援できるのか、必ず守るべきルールは何か、そして人事担当者様が特に気になる費用負担について、一つひとつ丁寧に解説していきます。
支援の3つの方法:受け入れ企業としてできること
特定技能外国人の住まいを確保する支援には、主に3つのアプローチがあります。
- 一つ目は、外国人ご本人が主体となって賃貸物件を探し契約する際に、企業がサポートする方法です。この場合、企業は不動産仲介業者の情報を提供したり、物件探しや内見に同行したりします。賃貸借契約の手続き補助や、必要であれば企業が連帯保証人になる、あるいは保証会社を利用する手続きを手伝うことも大切な支援です。本人主導で進められるメリットがありますが、保証人問題などで難航する可能性も考慮する必要があります。
- 二つ目は、受け入れ企業が法人名義で賃貸物件を借り上げ、その部屋を特定技能外国人に提供する、いわゆる又貸しの形式です。企業が契約主体となるため保証人の心配が減り、スムーズに住居を用意しやすいのが利点と言えるでしょう。
- 三つ目は、企業が所有する社宅や社員寮を提供する方法です。すでに住む場所があるため、迅速な入居が可能になりますが、プライバシーや他の従業員との兼ね合いに配慮が必要かもしれません。
どの方法が最適かは、会社の状況や外国人本人の意向を踏まえて検討することが大切です。
必ず守るべき住居のルールと基準
特定技能外国人に住居を提供する場合、絶対に守らなければならないルールがあります。最も基本的な基準が、居室の広さです。
原則として、外国人一人あたり7.5平方メートル以上のスペースを確保することが求められます。例えば、一つの部屋を複数人で共有するルームシェア形式をとる場合は、部屋全体の面積を住んでいる人数で割ったときに、一人あたり7.5平方メートル以上確保されている必要があります。
ただし、例外もあります。技能実習生として既に住んでいた社宅などに、特定技能へ切り替えた後も本人が引き続き住むことを希望している場合などは、7.5平方メートル未満でも認められることがあります。広さの基準だけでなく、例えば物置のようなスペースを居室として使わせないなど、安全面や衛生面にもきちんと配慮することが求められます。
費用負担のルール:敷金・礼金・家賃、どこまで企業が負担?
住居確保にかかる費用負担についても、はっきりとしたルールが存在します。
まず大切な点として、企業が連帯保証人になる場合や、保証会社を利用する際に支払う保証料は、受け入れ企業が負担しなければなりません。この費用を外国人本人に請求することはできませんので注意しましょう。
一方で、敷金・礼金・仲介手数料といった入居時の初期費用や、毎月の家賃については、必ずしも企業が全額負担する必要はありません。外国人本人と事前にしっかりと話し合い、合意が得られれば、周辺の家賃相場などを踏まえた妥当な金額を本人に負担してもらうことは認められています。ただし、ここで非常に重要な注意点があります。企業が社宅や寮を提供したり、又貸ししたりする場合、家賃などで不当な利益を得ることは絶対に許されません。家賃を設定する際には、近隣の類似物件の家賃相場や、物件の取得・維持管理にかかる実際の費用などを考慮し、あくまでも合理的な範囲内の金額に設定する必要があるのです。
家具・家電の準備は義務?推奨される対応とは
新しい生活を始めるにあたって、ベッドや冷蔵庫、洗濯機といった家具や家電製品は欠かせません。
これらの生活必需品を受け入れ企業が用意すること自体は、法律で定められた義務ではありません。しかし、特に母国から直接来日する外国人の場合、入国してすぐにこれらの品物を自分一人で揃えるのは、言葉の問題や地理的な不慣れさもあり、非常に大変です。
ですから、企業が必要な家具・家電の購入に付き添ったり、事前にいくつか準備を手伝ったりするなど、彼らがスムーズに日本での生活をスタートできるようサポートすることが、強く推奨されています。最低限、入国後すぐに日常生活を送るのに困らないよう、可能な範囲で温かくサポートしてあげることが望ましいと言えるでしょう。
住居確保支援の具体的な方法やルール、費用について、イメージが掴めましたでしょうか。
支援② 生活に必要な契約支援:具体的なサポート内容
次に解説するのは、特定技能外国人が日本でスムーズに日常生活を始めるために欠かせない「生活に必要な契約」に関する支援です。
安定した住まいの確保と並んで大切な、ライフラインや通信手段、金融サービスの利用開始をしっかりとサポートするために、企業としてどのようなお手伝いが必要か、具体的な契約の種類ごとに詳しく見ていきましょう。
支援が必要な主な契約とは?
受け入れ企業がサポートすべき生活に必要な契約としては、主に次のようなものが挙げられます。
- まず、お給料の受け取りや日々の生活費の管理に必要となる銀行口座の開設。
- 次に、日本での連絡手段として今や必須とも言える携帯電話(スマートフォン)の契約。
- そして、毎日の暮らしに欠かせない電気・ガス・水道といったライフラインの契約です。
人によっては、ご自宅でインターネットを利用するための回線契約なども支援の対象となり得るでしょう。これらは、日本での生活基盤をしっかりと築くための重要な要素なのです。
具体的な支援方法:どこまで手伝う必要がある?
では、これらの契約手続きにおいて、受け入れ企業は具体的にどのような形で支援を行うべきなのでしょうか。
基本となるのは、それぞれの契約に必要な手続きや提出書類に関する情報を提供することです。必要に応じて、母国語で書かれた案内資料を準備したり、手続きの流れをステップごとに分かりやすく説明したりすることも有効なサポートとなります。次に、契約を行う銀行の支店や携帯電話ショップ、役所の関連窓口などへ場所を案内し、必要であれば一緒に行く(同行する)ことも求められます。窓口での日本語でのやり取りに不安を感じているようであれば、通訳としてサポートすることも心強い助けになるでしょう。
また、申請書類の記入方法を丁寧に教えるなど、書類作成のお手伝いも重要な支援の一つです。ここで大切なのは、契約の主体はあくまで外国人ご本人であるという点です。企業が一方的に手続きを進めるのではなく、必ず本人の意思を確認し、理解を得ながら、二人三脚で進めていく姿勢が求められます。
ライフライン(電気・ガス・水道)契約のポイント
電気・ガス・水道といったライフラインは、新しい住まいに入居したその日からすぐに使える状態にしておくことが、安心して新生活をスタートするために非常に重要です。
そのため、可能であれば外国人本人の入居前に、企業が契約手続きをサポートし、事前に開通の手配を済ませておくことが強く推奨されます。各供給会社への連絡方法や申し込み手順を案内し、必要書類の準備を手伝いましょう。契約者の名義をどうするか(外国人本人か、一時的に企業か)月々の支払い方法(口座振替、クレジットカード、コンビニ払いなど)についても、事前に本人とよく話し合い、納得のいく形で決めておくことが大切です。
銀行口座開設のサポート:必要書類と手続きの流れ
給与振込などに必須となる銀行口座の開設も、外国人にとっては意外とハードルが高い手続きとなりがちです。一般的に、口座開設には在留カードやパスポートが必要ですが、日本の銀行では現在でも印鑑の捺印を求められる場合があります(最近はサインで可能な銀行も増えています)。
金融機関によって必要書類や手続きのルールは異なるため、まずは勤務先や住居の近くにある利用しやすい銀行を選び、事前に必要書類を確認するところから始めましょう。その上で、窓口へ同行し、申込書の記入を手伝ったり、銀行員の方とのコミュニケーションをサポートしたりします。
事前のしっかりとした情報収集と、安心感を与える丁寧な同行支援が、スムーズな口座開設の鍵を握ります。
携帯電話契約のサポート:注意点と選択肢
現代社会で欠かせないコミュニケーションツールである携帯電話。
その契約も、外国人にとっては選択肢の多さや手続きの複雑さから、難しく感じられることがあります。大手キャリアにするのか、格安SIMを選ぶのか、あるいはプリペイドSIMという方法もあるのかなど、様々な契約形態や料金プランがあります。それぞれのメリット・デメリットを分かりやすく説明し、本人の使い方や希望に合ったプランを一緒に考え、選べるように情報提供を行うことが大切です。契約時には、在留カードやパスポートのほか、支払い方法によっては銀行口座やクレジットカードが必要になることが多いです。事前に必要なものを確認し、準備を手伝いましょう。
もし外国人向けの特別プランや多言語対応サポートを提供している通信事業者があれば、そうした情報も積極的に伝えてあげると喜ばれるでしょう。
契約に関する費用負担について
これらの生活に必要な契約手続きをサポートする際、例えば企業担当者が窓口へ同行するための交通費や、外部の通訳を手配した場合の費用などは、義務的支援の実施に必要な経費として、受け入れ企業が負担しなければなりません。
外国人本人にこれらの費用を請求することはできませんので、ご注意ください。一方で、契約に基づいて毎月発生する利用料金、具体的には電気代、ガス代、水道代、携帯電話の通信料、インターネットのプロバイダ料金などは、原則として外国人ご本人が支払うことになります。ただし、誤解やすれ違いを防ぐためにも、家賃と同様、事前に本人との間で誰が何を負担するのかについて明確に話し合い、合意しておくことが、後のトラブルを避ける上で非常に重要です。
銀行口座、携帯電話、ライフラインといった生活に直結する契約のサポートは、特定技能外国人が安心して日本での第一歩を踏み出すために、本当に大切な支援です。
手続きの種類が多く、時には専門的な言葉も出てくるため、人事担当者様のご負担も決して小さくないことでしょう。
「手続きの詳細まで把握しきれない」
「言葉の壁をサポートする余裕がない」といったお悩みをお持ちでしたら、
ぜひ私たち専門家にご相談ください。
支援をスムーズに進めるためのポイントと注意点

ここまで、住居確保と生活契約支援の具体的な進め方について解説してきました。最後に、これらの大切な支援をより円滑に進め、思わぬトラブルを未然に防ぐために、ぜひ押さえておきたい実践的なポイントと注意点をご紹介いたします。
しっかり準備し、適切な対応をすることで、受け入れプロセス全体の成功確率を高めることができるでしょう。
自社で全て対応?登録支援機関に委託?メリット・デメリット比較
特定技能外国人の義務的支援を、すべて自社の力で行うのか、それとも専門の登録支援機関にお願いするのかは、人事担当者様にとって大きな決断の一つです。
自社で対応する場合、外部への委託費用がかからないためコスト面でのメリットがあり、また、支援を通じて外国人従業員との直接的なコミュニケーションが増え、信頼関係を築きやすく、社内に受け入れノウハウが蓄積されるという利点もあります。
しかしながら、担当者の業務負担がかなり大きくなることや、専門的な知識や多言語対応のスキルが不足している場合に、支援の質が低下してしまうリスクも無視できません。一方、登録支援機関に委託すれば、担当者の負担は劇的に軽減され、専門家の知見に基づいた質の高い、安定した支援が期待できます。最新の法令改正などへの対応も任せられるため、コンプライアンス面での安心感も大きいでしょう。
ただし、当然ながら委託には費用がかかります。どちらの方法を選ぶべきかは、会社の規模や受け入れる外国人の人数、人事・総務部門のリソース状況、そして何よりも「どのレベルの支援を提供したいか」という点を総合的に考慮し、慎重に判断することが重要になります。
登録支援機関を選ぶ際のポイント
もし登録支援機関への委託を決めた場合、次は数多く存在する機関の中から、自社に合ったパートナーをどう選ぶかという課題に直面します。信頼できる機関を選ぶためには、いくつかの重要なポイントを確認しましょう。
- まず、今回詳しく解説した「住居確保」や「生活に必要な契約支援」といった分野において、具体的な成功事例や豊富な経験を持っているかを確認することが大切です。
- 次に、受け入れる外国人の母国語に対応できるスタッフが在籍しているか、また、困ったときにすぐに連絡が取れるかなど、サポート体制がしっかりしているかも見極めたい点です。
- 料金体系が明確で分かりやすく、契約内容に含まれない追加費用が発生する可能性がないかも、事前にきちんと確認しておくべきでしょう。
- そして、意外と見落としがちですが、実際にやり取りをする担当者との相性や、報告・連絡・相談がスムーズに行えるかどうかも、長いお付き合いになることを考えると非常に重要です。
焦らず、複数の機関から話を聞き、サービス内容や費用、担当者の対応などを比較検討することをお勧めします。
よくあるトラブル事例とその防止策
どんなに丁寧に準備や支援を行っていても、残念ながら予期せぬトラブルが発生してしまう可能性はあります。よく耳にする事例としては、住居に関するトラブルです。例えば、日本のゴミ出しルールを理解してもらえず近隣から指摘を受けたり、生活音に対する感覚の違いから騒音問題に発展したりするケースがあります。
こうした文化や習慣の違いから生じる問題を未然に防ぐためには、入居前の生活オリエンテーションが非常に重要です。日本の生活ルールやマナーについて、イラストや写真、可能であれば母国語の資料なども活用しながら、具体的かつ根気強く説明し、理解を促すことが効果的です。また、契約に関するトラブル、例えば家賃や公共料金の支払いが遅れてしまう、退去時に必要な解約手続きを忘れてしまうといったことも起こり得ます。これらに対しては、支払い期日が近づいたら優しく声をかける、退去が決まった際には解約が必要な手続きをリストアップして一緒にチェックするなど、きめ細やかなフォローアップが有効です。保証人に関するトラブルを避けるためには、契約時に内容を一方的に説明するのではなく、外国人本人が時間をかけて十分に理解し、納得しているかしっかりと確認するプロセスが不可欠となります。
最新情報への注意(法改正など)
最後に、これは非常に重要な注意点ですが、特定技能制度やそれに関連する出入国管理法などの法律は、社会情勢の変化などを受けて、今後も内容が見直されたり、改正されたりする可能性があるということを常に念頭に置いておく必要があります。
例えば、義務的支援の具体的な基準が変更されたり、提出しなければならない書類の様式が変わったりすることも十分に考えられます。古い情報のまま手続きを進めてしまうと、申請が受け付けられなかったり、知らず知らずのうちに法令違反を犯してしまったりするリスクも。日頃から、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトなどで最新の情報をチェックする習慣をつけ、少しでも疑問に思う点があれば専門家に確認するなど、常に正確な情報に基づいて支援業務を行うよう心がけることが、コンプライアンス上も極めて重要です。
義務的支援をスムーズかつ適切に進めるためのポイント、お分かりいただけたでしょうか。
支援体制の選択、信頼できるパートナー探し、トラブル予防、そして法改正へのアンテナ。どれも担当者様にとってはプレッシャーを感じる部分かもしれません。
まとめ:特定技能外国人の安定した生活基盤を築くために
本記事では、特定技能外国人の受け入れにおける義務的支援の中でも、特に「住居確保」と「生活に必要な契約支援」に焦点を当て、その具体的な内容や注意点を詳しく解説いたしました。最後に、これまでのポイントを振り返り、特定技能外国人の受け入れを成功に導くための要点を確認しましょう。
特定技能外国人が日本で安心して能力を発揮するには、安定した生活基盤が何よりも大切です。その中心となるのが「住居」と「生活に必要な契約」であり、受け入れ企業には法律に基づき、これらをスムーズに確保・手続きできるよう支援する義務があります。
支援の具体的な方法、守るべきルール(広さ、費用負担、利益供与禁止など)を正しく理解することが、適切なサポートの第一歩です。そして、これらの支援を自社で行うか、専門の登録支援機関に委託するか、自社の状況に応じて最適な体制を整えることも重要となります。
義務的支援は、単なる法的な手続きとして捉えるのではなく、慣れない日本での生活を始める外国人従業員に温かく寄り添う機会と考えることが大切です。企業側の丁寧で親身なサポートは、外国人従業員との信頼関係を深め、結果として職場への定着率向上や生産性アップにもつながり、企業の成長に貢献することも期待できるでしょう。
受け入れは、共に働く仲間を迎え入れ、活躍してもらうための大切なスタート地点なのです。
初めての特定技能外国人受け入れでは、住居や契約のサポート、そして複雑なビザ申請手続きなど、ご担当者様には多くの不安や疑問が伴うことでしょう。
「具体的なケースについて相談したい」「専門家の力を借りて、確実に手続きを進めたい」とお考えでしたら、ぜひ私たちにご相談ください。
特定技能ビザ申請の専門家として、豊富な経験と実績に基づき、貴社の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。義務的支援に関する細かな疑問へのアドバイスから、ビザ申請書類の作成、入国管理局への申請代行まで、ワンストップで対応可能です。
私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
関連するオススメ記事はこちら
- 登録支援機関の義務的支援その⑤「公的手続きへの同行」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その④「生活オリエンテーション」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その③「住居の確保・契約支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その②「出入国時の送迎」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その①「事前ガイダンス」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援・任意的支援とは?人事担当者が知るべき違い・費用・選び方を徹底解説
- 特定技能1号で家族の帯同ができる?要件・必要書類について徹底解説
- 特定技能外国人の転職について|要件・手続き・注意点を解説
- 特定技能ビザから技人国ビザへの変更方法について|要件・方法・注意点を解説
- 特定技能ビザで働く【外国人】のメリット・デメリットについて

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート