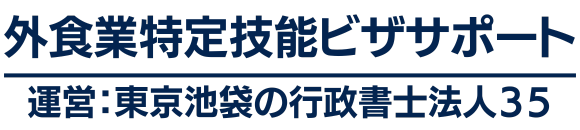登録支援機関の義務的支援その④「生活オリエンテーション」とは?|特定技能外国人
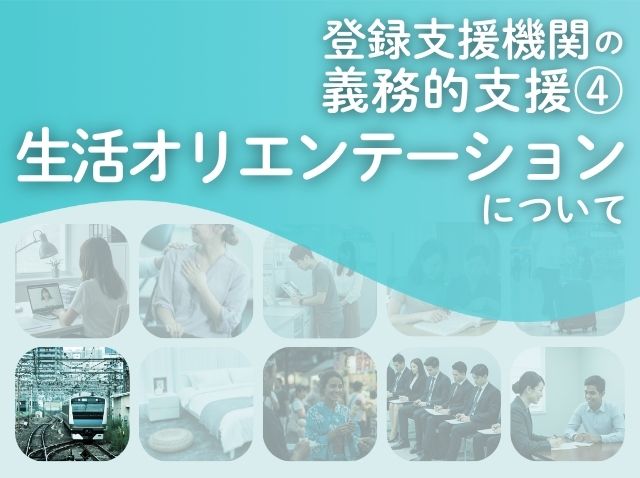
特定技能外国人の方を初めて迎え入れるご準備、本当にお疲れ様です。
様々な手続きを進める中で「義務的支援」の一つ「生活オリエンテーション」について
「具体的に何を話せばいいんだろう?」
「時間はどれくらい確保すべき?」
「そもそも、どうしてオリエンテーションが必要なのだろう?」
といった疑問をお持ちではないでしょうか。初めての経験では、分からないことばかりで戸惑ってしまいますよね。
この記事は、まさにそのような人事ご担当者様の疑問やご不安を解消するためにあります。特定技能制度で義務付けられている「生活オリエンテーション」のそもそもの目的から、具体的に説明すべき内容リスト、必要な実施時間、認められている実施方法、そして気をつけるべき注意点まで、一つひとつ丁寧にご説明いたします。
特定技能ビザ申請の専門家である行政書士が、出入国在留管理庁の指針に沿って、できる限り分かりやすくお伝えしますので、この記事を最後までお読みいただければ、生活オリエンテーションの全体像がすっきりと理解でき、自信を持って準備を進めていただけるはずです。
目次
- 特定技能の「生活オリエンテーション」とは?なぜ必要なのか
- 生活オリエンテーションで伝えるべき内容【必須項目】
- 生活オリエンテーションの実施方法とルール
- 効果的なオリエンテーションにするためのポイントと注意点
- まとめ
特定技能の「生活オリエンテーション」とは?なぜ必要なのか
特定技能外国人の受け入れ準備、お疲れ様です。
ここでは、義務的支援の重要な柱の一つである「生活オリエンテーション」について、その基本的な意味合いと、なぜ企業が時間と労力をかけて実施する必要があるのか、その目的と重要性を分かりやすく解説していきます。
義務的支援の中での「生活オリエンテーション」の位置づけ
特定技能1号の在留資格で外国人材を受け入れる企業には、法律に基づいて合計10項目の支援を行う義務があります。これが「義務的支援」と呼ばれるものです。
その中でも「生活オリエンテーション」は入国前に行う「事前ガイダンス」とは別に、特定技能外国人が日本に入国した後、または国内で在留資格を変更した後に、できるだけ早く実施することが求められる、いわば日本での新生活スタートに向けた最初の本格的なガイダンスとなります。これから始まる日本での暮らしと仕事の基盤を作るための、非常に大切なステップなのです。
生活オリエンテーションを実施する目的と重要性
では、なぜこの生活オリエンテーションがこれほどまでに重要視されるのでしょうか。
その最大の目的は、特定技能外国人が日本のルールや文化、生活習慣を理解し、職業生活はもちろん、日々の暮らしや社会との関わりをスムーズかつ安定的に送れるようサポートすることにあります。
母国とは異なる環境では、知らず知らずのうちにルール違反をしてしまったり、文化的な誤解から思わぬトラブルに巻き込まれたりする可能性があります。例えば、ゴミ出しのルールを守らなかったり、騒音に対する感覚の違いがあったりすると、近隣との関係が悪化しかねません。
また、日本の法律や税金、社会保険などの制度を知らないままでは、不利益を被ることもあるでしょう。生活オリエンテーションは、こうした問題を未然に防ぎ外国人が安心して日本での生活をスタートするための知識を提供する場です。さらに、困った時に誰に相談できるのか、どんな公的支援があるのかといった情報を提供することで、異国での孤立感を和らげ、心理的な支えにもなります。
企業にとっては、単に法律上の義務を果たすだけでなく、外国人従業員の早期定着を促し、安心して仕事に集中できる環境を整えることで、結果的に生産性の向上や長期的な活躍につなげるための重要な取り組みと言えるわけですね。しっかりとしたオリエンテーションは、企業と従業員の良好な関係を築くための第一歩となるでしょう。
生活オリエンテーションが、特定技能外国人にとっても、受け入れ企業にとっても、いかに大切かご理解いただけたでしょうか。
その重要性を踏まえた上で、次はいよいよ「具体的にどんなことを説明すればいいの?」という核心部分に入っていきます。
生活オリエンテーションで伝えるべき内容【必須項目リスト】

さて、生活オリエンテーションの重要性をご理解いただいたところで、次に「具体的にどんな情報を伝えればよいのか」という疑問にお答えします。
出入国在留管理庁は、特定技能外国人が日本で円滑に生活・就労するために必要不可欠な情報提供項目を定めています。この章では、その必須項目を6つの大きなカテゴリーに分け、それぞれのポイントを分かりやすく解説していきます。
① 日本での生活一般に関する情報
まずは、日々の暮らしの基本となる情報です。
給与の受け取りや支払いに不可欠な銀行口座の開設方法やATMの基本的な使い方など、金融機関の利用について案内しましょう。病気や怪我をした際の医療機関のかかり方、健康保険証の役割と使い方、もしもの時の救急車の呼び方なども、必ず伝えるべき重要な情報です。日本の交通ルール、特に自転車利用時の注意点や標識の意味、電車やバスといった公共交通機関の乗り方や料金支払い方法についても説明が必要です。
地域での共同生活を円滑にするためには、ゴミの分別方法や収集日、騒音への配慮、喫煙ルールといった生活マナーの遵守が欠かせません。これらは地域差が大きい部分ですので、必ず外国人従業員が住む自治体のルールを具体的に伝えましょう。日常の買い物ができるスーパーやドラッグストアの場所、おおよその物価感を共有することも、生活の助けになります。日本は自然災害が多い国であるため、台風や地震などの際に気象情報や避難情報をどうやって入手するか、最低限の備えについても説明が必要です。
最後に、日本で厳しく罰せられる違法行為、例えば薬物の所持・使用や、友人であっても不法就労を手伝うことなどの具体例を挙げ、絶対に手を出さないよう強く注意喚起してください。
② 国や地方公共団体への届出・手続きに関する情報
次に、日本で生活する上で避けて通れない公的な手続きについてです。
引っ越しに伴う住民票の異動手続き(転入届・転居届)は、法律で定められた期間内に行う義務があることを伝えましょう。国民年金や健康保険といった社会保障制度への加入手続きや、所得税・住民税といった税金の仕組み、納税方法についても基本的な知識を提供する必要があります。
マイナンバー制度についても説明し、個人番号カードの重要性と適切な管理方法を周知します。加えて、受け入れ企業の名称や所在地が変わった場合、あるいは本人が転職する際など、入国管理局への届け出が必要になるケースについても説明しておくと、後々のトラブルを防げます。
③ 相談・苦情の申出先、支援体制に関する情報
仕事や生活の中で困りごとや悩みが発生した場合に、一人で抱え込まずに相談できる場所を知っていることは、外国人従業員の精神的な安定に繋がります。
まず、会社の担当者や相談窓口の連絡先を明確に伝えることが基本です。登録支援機関にサポートを委託している場合は、その機関名と連絡先、担当者名もしっかりと知らせましょう。さらに、ハローワーク、労働基準監督署、法務局の人権相談窓口、出入国在留管理庁のインフォメーションセンターといった公的な相談機関があること、そしてその連絡先や利用方法についても情報提供することが重要です。
これらの連絡先をまとめたリストを渡すと、いざという時に役立ちます。
④ 医療に関する詳細情報
健康に関わる情報は特に重要ですので、生活一般の項目とは別に、より詳しく説明します。外国人従業員が住む地域で、実際に受診できる病院やクリニックをいくつかリストアップして教えましょう。
もし可能であれば、外国語対応が可能な医療機関や、電話やオンラインで利用できる医療通訳サービスの情報も併せて提供できると、より安心感が高まります。診察の予約方法、受付での手続き、健康保険証の提示、薬の受け取り方など、具体的な受診の流れも説明しておくとスムーズです。
⑤ 防災・防犯・緊急時に関する詳細情報
万が一の災害や事故、急病に備えるための知識も必須です。警察(110番)や消防・救急(119番)への正しい通報方法を確実に理解してもらいます。
母国の大使館や領事館の緊急連絡先も伝えておくことが大切です。地震や台風といった自然災害に備え、住んでいる地域のハザードマップを確認し、指定されている避難場所やそこまでの経路を一緒に確認しておきましょう。災害発生時に家族や会社と連絡を取り合うための安否確認方法(災害用伝言ダイヤルやSNSの活用など)についても説明します。また、空き巣や悪質な勧誘、詐欺といった犯罪から身を守るための基本的な注意点についても触れておきましょう。
⑥ 法的保護に関する情報
最後に、外国人従業員自身の権利を守るための大切な情報です。
もし、職場で入管法や労働基準法などに違反するような行為を目にしたり、自身がハラスメントなどの不当な扱いを受けたりした場合に、どこに相談すれば保護を受けられるのかを具体的に伝える必要があります。③で紹介した公的な相談窓口(労働基準監督署、人権相談窓口など)の役割を改めて説明し、会社としても相談に乗り、必要であれば窓口への同行などのサポートを行う用意があることを伝えましょう。これにより、問題を一人で抱え込まず、適切な助けを求めることができるようになります。
生活オリエンテーションで伝えるべき内容は、このように非常に多岐にわたりますが、一つひとつが特定技能外国人の日本での安全で安心な生活を支える基盤となります。これらの情報を漏れなく、かつ分かりやすく伝えるには、相応の準備と時間が必要になるでしょう。
生活オリエンテーションの実施方法とルール
伝えるべき内容が分かったところで、次に気になるのは「では、具体的にどうやってオリエンテーションを実施すればいいの?」という点ですよね。
実施するタイミングや必要な時間、認められている形式、使用する言語、そして終わった後の手続きについて、守るべきルールを一つひとつ確認していきましょう。
実施時期:いつ行うべき?
生活オリエンテーションを行うタイミングは決まっています。
原則として、特定技能外国人が日本に入国した後、または日本国内で他の在留資格から特定技能1号へ変更許可を受けた後、「遅滞なく」実施することになっています。これはつまり、新しい在留資格での活動が始まるのとほぼ同時期に、できるだけ速やかに行う必要がある、ということです。
日本での新しい生活をスムーズに始めるためには、入国や資格変更から時間を空けずに実施することが理想的です。
実施時間:どれくらいの時間が必要?
生活オリエンテーションにかけるべき時間についても、はっきりとした基準があります。
原則として、全体で「8時間以上」の時間を確保して行うことが求められています。前章で見たように、伝えるべき内容は非常に多岐にわたるため、外国人本人がしっかり理解するには、それだけの時間が必要だということですね。ただし、一部例外も認められています。例えば、技能実習2号を優秀に修了し、同じ会社で特定技能1号として働き続ける場合や、日本の大学などを卒業した元留学生を雇用する場合など、日本での生活にすでにある程度慣れていると判断されるケースでは、実施時間を「4時間以上」と短縮することが可能です。ですが、この場合でも4時間未満にすることはできません。
何よりも大切なのは、単に時間を満たすことではなく、伝えるべき情報を確実に伝え、本人が内容をきちんと理解できたかを確認しながら進めることです。
実施形式:対面?オンライン?動画でもOK?
オリエンテーションをどのように行うか、その形式については、比較的柔軟な方法が認められています。
昔ながらの対面形式での説明はもちろん有効ですが、ZoomやTeamsといったWeb会議システムを使ったオンライン形式での実施も可能です。遠方に住む外国人を受け入れる場合などに便利でしょう。さらに、出入国在留管理庁が多言語で作成・公開している「生活オリエンテーション動画」などを活用し、動画視聴をメインに進める方法も認められています。ただし、どの形式を選ぶにしても、絶対に守らなければならない重要なポイントがあります。それは、実施中に特定技能外国人から質問が出た場合に、きちんとそれに答えられる体制を整えておく必要がある、という点です。
動画を見せて終わり、ではなく、内容について分からない点はないか確認したり、必要に応じて補足説明を加えたりするなど、双方向のやり取りができるようにしておくことが求められます。
使用言語:何語で説明する?
生活オリエンテーションを何語で行うか、使用言語にも明確なルールがあります。
それは、特定技能外国人が「十分に理解できる言語」で実施しなければならない、ということです。多くの場合、これは外国人本人の「母国語」を指すことになります。たとえ日本語でのコミュニケーションがある程度とれる外国人であっても、法律や行政手続きに関する専門的な事柄や、日本の文化・習慣に関する微妙なニュアンスなどは、母国語で説明を受けた方がはるかに正確に理解できるものです。
ですから、受け入れ企業としては、必要に応じて通訳を手配したり、出入国在留管理庁が提供する多言語版の「生活・就労ガイドブック」などを活用したりする必要があります。日本語だけで説明して、本人が内容を十分に理解できていないと判断された場合、義務を果たしたと見なされない可能性もありますので、言語への配慮は非常に重要です。
実施後の手続き:確認書の作成と保管
生活オリエンテーションをルールに沿って実施した後は、その証拠となる記録を残す手続きが必要です。
具体的には「生活オリエンテーションの確認書」という書類(参考様式第5-8号という雛形があります)を作成します。この確認書には、いつ、誰が、どんな内容のオリエンテーションを行ったかを記録します。そして最後に、オリエンテーションを受けた特定技能外国人本人に内容をよく確認してもらい、理解した旨の署名(サイン)をもらう必要があります。
作成した確認書は、受け入れ企業(または支援を委託している登録支援機関)が大切に保管します。保管期間は、その外国人の雇用期間中と、雇用契約が終了してから1年間です。この確認書をすぐに出入国在留管理庁へ提出する必要はありませんが、将来的に入管による調査などがあった際には提示を求められることがありますので、必ず作成し、きちんと保管しておくようにしましょう。
生活オリエンテーションの実施方法や守るべきルール、お分かりいただけましたでしょうか。
実施時間や言語の配慮、実施後の書類保管など、確実に実行すべき点がいくつかありますね。特に、母国語での説明や質問対応の体制を自社だけで整えるのは、なかなか大変だと感じるかもしれません。
効果的なオリエンテーションにするためのポイントと注意点

さて、生活オリエンテーションで何を伝え、どのように実施するかのルールをご理解いただけたかと思います。
しかし、ただルール通りに実施するだけでなく、せっかくなら外国人従業員の心に響き、日本での生活を本当にサポートできるような、より効果的なオリエンテーションにしたいですよね。この章では、そのための具体的な工夫や、実施する上で気をつけておきたい大切なポイントをいくつかご紹介します。ちょっとした配慮が、彼らの安心感と日本への適応を大きく後押しするはずです。
一方的な説明にならない工夫:双方向のコミュニケーションを意識する
オリエンテーションを成功させる秘訣の一つは、決して一方的な情報伝達で終わらせないことです。
ただ話を聞いているだけでは、なかなか内容は定着しませんし「質問ありますか?」と聞かれても、遠慮して手を挙げにくい雰囲気になりがちです。説明の合間には意識的に質疑応答の時間を設け、外国人従業員が「これはどういう意味ですか?」と気軽に尋ねられるような、温かい雰囲気作りを心がけましょう。
時には「ここまでの内容で、特に分かりにくい点はありましたか?」と具体的に問いかけたり、簡単な確認クイズを取り入れたりして、理解度を確かめながら進めるのも効果的です。専門用語や難しい言葉遣いを避け、できるだけシンプルで分かりやすい言葉を選ぶことも、スムーズな双方向コミュニケーションのためには欠かせません。
情報は「具体的に」「地域に合わせて」提供する
伝える情報は、できる限り具体的であることが大切です。「スーパーは近くにあります」だけでなく、「会社の角を曲がったところに〇〇スーパーがあって、夜10時まで営業しています。お惣菜も豊富ですよ」といった情報の方が、ずっと実用的です。
銀行の支店の場所、評判の良い近所のクリニック、利用するであろうバスの路線図なども、実際に生活するエリアのものを示してあげましょう。特に注意したいのが、ゴミの分別方法や収集日、地域の自治会のルールなどです。これらは市区町村によってルールが大きく異なるため、必ず外国人従業員が住むことになる自治体の最新情報を調べ、それに沿った正確な情報を提供する必要があります。地域に根差した具体的な生活情報こそが、彼らのスムーズな日常のスタートを力強くサポートします。
公的資料やツールの活用:効率化と正確性の向上
オリエンテーションでカバーすべき内容は広範囲にわたるため、関連資料を全て自社で準備するのはかなりの負担になります。
そこで活用したいのが、公的な資料やツールです。出入国在留管理庁は、特定技能外国人向けに詳細な「生活・就労ガイドブック」や、分かりやすい「生活オリエンテーション動画」を、なんと17もの言語で作成し、ウェブサイトで公開しています。これらを積極的に活用すれば、情報収集や資料作成にかかる時間を大幅に短縮でき、オリエンテーションの準備をぐっと効率化できます。
公的機関が作成しているため、情報の正確性や信頼性も高く安心です。多言語対応の資料は、言葉の壁を乗り越えるための強力な味方にもなるでしょう。自社のオリエンテーション内容に合わせて、これらの公的ツールを上手に組み合わせて活用することをお勧めします。
登録支援機関への委託も有効な選択肢
これまでにも触れてきましたが、もし「自社だけでは質の高いオリエンテーションを行うのが難しい」「多言語対応や専門知識に不安がある」と感じる場合は、専門家である登録支援機関に支援業務を委託することも、非常に有効な選択肢です。
彼らは特定技能外国人の支援に関するプロフェッショナルであり、豊富な経験とノウハウを持っています。委託することで、人事担当者様の負担を大幅に軽減し、法令を遵守した適切な支援の実施を確実にすることができます。
ただし、ここで注意したいのは、委託した場合でも全てを「丸投げ」にしてはいけない、ということです。委託先としっかりコミュニケーションを取り、どのような内容でオリエンテーションが進められているのかを把握し、企業としても外国人従業員の状況に常に関心を持ち続ける姿勢が大切です。あくまで企業と登録支援機関が連携し、二人三脚で外国人従業員をサポートしていくという意識を持つことが重要と言えるでしょう。
オリエンテーションは一度きりではない?継続的なサポートの視点
法律で定められた8時間(または4時間)以上の生活オリエンテーションですが、たった一度の説明で、日本の複雑な生活ルールや文化の全てを完璧に理解し、記憶するのは、正直なところ誰にとっても至難の業です。
特に、来日直後は新しい環境に慣れるだけで精一杯で、頭がいっぱいになっていることも考えられます。だからこそ、オリエンテーションは「一回やったら終わり」ではなく、「継続的なサポートのスタート地点」と捉える視点が非常に重要になります。入社後に行う定期的な面談などの機会を利用して「最近、何か困っていることはありませんか?」「日本の生活には慣れてきましたか?」など、気軽に声をかけ、必要であればオリエンテーションで説明した内容を改めて伝えたり、その時々で必要な新しい情報を提供したりすることが望ましいのです。
このような地道で継続的なフォローアップこそが、外国人従業員の不安を解消し、日本での長期的な定着と仕事での活躍を力強く支える基盤となるはずです。
効果的な生活オリエンテーションを実現するための工夫や注意点、参考になりましたでしょうか。双方向性を大切にし、具体的で地域に合った情報を提供し、便利なツールも活用する。そして何より、一度きりではない継続的なサポートを心がけること。
これらの点を意識すれば、オリエンテーションは単なる義務ではなく、外国人従業員との素晴らしい関係を築くためのかけがえのない第一歩となるでしょう。
まとめ:丁寧な生活オリエンテーションで円滑な受け入れを
この記事を通じて、特定技能外国人を受け入れる際の義務的支援である「生活オリエンテーション」について、その目的、具体的な内容、実施方法、そして成功させるためのポイントをご理解いただけたことと思います。最後に、本記事の要点を改めて確認し、円滑な受け入れ実現に向けたメッセージをお伝えして締めくくりといたします。
生活オリエンテーションは、特定技能1号の外国人にとって、日本での安定した生活と仕事をスタートさせるための、法律で定められた非常に重要な支援です。
金融機関の利用からゴミ出しのルール、緊急時の対応まで、伝えるべき内容は多岐にわたります。公的資料などを上手に活用しつつ、外国人本人がしっかりと理解できる言葉で、具体的に、そして分かりやすく説明する工夫が求められます。
実施時間(原則8時間以上)や実施形式、使用言語のルールを守り、実施後には確認書を作成して保管することも必須です。これらの支援体制を自社で構築するか、専門知識を持つ登録支援機関に委託するかは、会社の状況に合わせて慎重に検討すべき点となります。
何よりも大切なのは、この生活オリエンテーションを単なる「義務」と捉えるのではなく、「新しい仲間を温かく迎え入れ、彼らが安心して日本でのキャリアを築くための第一歩をサポートする貴重な機会」と考えることです。企業が示す丁寧で親身な姿勢は、外国人従業員の不安を確実に和らげ、日本社会や会社に対する信頼感を育てます。そして、その信頼関係こそが、早期の戦力化、高い定着率、ひいては企業の持続的な成長へと繋がっていくと考えます。
私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
関連するオススメ記事はこちら
- 登録支援機関の義務的支援その⑤「公的手続きへの同行」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その④「生活オリエンテーション」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その③「住居の確保・契約支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その②「出入国時の送迎」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その①「事前ガイダンス」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援・任意的支援とは?人事担当者が知るべき違い・費用・選び方を徹底解説
- 特定技能1号で家族の帯同ができる?要件・必要書類について徹底解説
- 特定技能外国人の転職について|要件・手続き・注意点を解説
- 特定技能ビザから技人国ビザへの変更方法について|要件・方法・注意点を解説
- 特定技能ビザで働く【外国人】のメリット・デメリットについて

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート