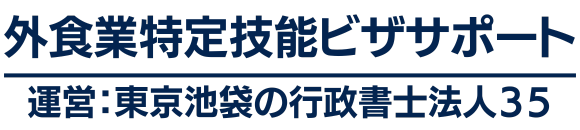登録支援機関の義務的支援その⑤「公的手続きへの同行」とは?|特定技能外国人
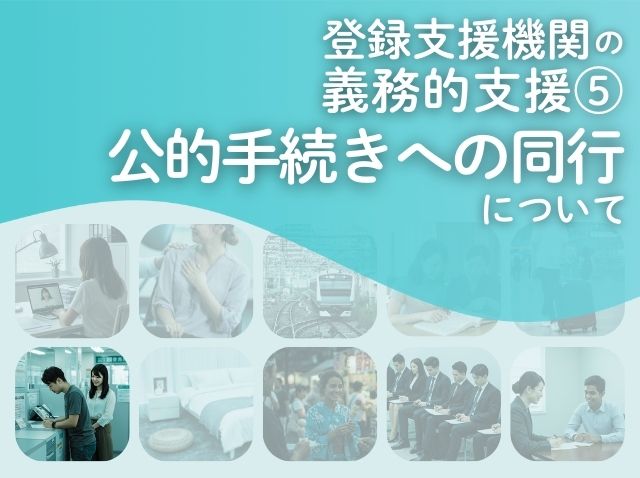
特定技能外国人材の受け入れ準備、本当にお疲れ様です。
様々な手続きや支援が必要となる中で「義務的支援」の一つである「公的手続きへの同行」について、
「具体的にどの手続きに付き添う必要があるのだろうか?」
「単に役所に一緒に行けば良いというわけではない?」
など、具体的な進め方に疑問やご不安を感じていらっしゃる人事担当者の方も少なくないでしょう。日本の行政手続きは複雑な面もありますから、ご心配になるお気持ち、よく分かります。
この記事は、まさにそのような人事ご担当者様の疑問を解消するために作成しました。
特定技能制度における義務的支援「公的手続きへの同行」が具体的に何を意味するのか、同行が求められる手続きの種類は何か、受け入れ企業としてどこまでの範囲のサポートをすべきなのか、そして実施にあたっての注意点について、一つひとつ分かりやすく解説を進めてまいります。
特定技能ビザ申請の専門家である行政書士が、最新の法令や運用指針に基づき丁寧に説明しますので、この記事をお読みいただければ、自信を持って外国人従業員の公的手続きサポートに取り組めるようになるはずです。
目次
- まずは基本から!特定技能外国人の「公的手続きへの同行」とは?
- 同行支援の対象となる主な「公的手続き」
- 「同行支援」の具体的な中身:ただ付き添うだけじゃない
- 同行支援を実施する上での注意点
- 自社で行う?登録支援機関に委託する?
- まとめ
まずは基本から!特定技能外国人の「公的手続きへの同行」とは?
特定技能外国人の方を迎え入れるにあたり「公的手続きへの同行」という支援項目について、具体的にどのようなことを指すのか、気になっている人事担当者様もいらっしゃるでしょう。
この章では、この「公的手続きへの同行」が特定技能制度の中でどのような役割を持つのか、そしてなぜ企業がこの支援を提供することが義務付けられているのか、基本的な定義と目的をわかりやすく解説します。
義務的支援としての位置づけ
特定技能1号の在留資格を持つ外国人材を受け入れる企業には、法律で定められた10項目の支援を提供する義務があります。
これらは総称して「義務的支援」と呼ばれており、「公的手続きへの同行」もその大切な一つです。事前に生活オリエンテーションなどで説明した様々な行政手続き、例えば住所の登録や社会保険の手続きなどを、実際に外国人ご本人が役所の窓口などで行う際に、企業が付き添い、必要なサポートを提供するのがこの支援段階にあたります。日本での生活を公式にスタートさせ、社会的な基盤を整えるための、避けては通れない重要なプロセスと言えるでしょう。
なぜ「同行支援」が必要なのか?その目的
では、なぜ企業がわざわざ役所の手続きなどに付き添う必要があるのでしょうか。
その主な目的は、特定技能外国人が、慣れない日本での複雑な行政手続きを、間違いなく、そして法律で定められた期限内に完了できるよう、しっかりとサポートすることにあります。日本語の難解な申請書類を読み解き、正確に記入することや、窓口での専門用語が飛び交う説明を理解することは、外国人にとって非常に高いハードルとなり得ます。
また、日本の行政手続きは多岐にわたり「いつまでに、どの窓口で、どんな手続きをすべきか」を正確に把握するのも簡単ではありません。例えば、住所に関する届出は転入から14日以内という期限があり、これを怠ると罰金が科されたり、場合によっては在留資格が取り消されたりする重大なリスクも伴います。
企業による同行支援は、このような言語や制度理解の壁から生じる手続きの遅れやミスを防ぎ、外国人従業員が不利益を被ることなく、安心して日本での生活基盤を速やかに確立できるようにするために、欠かすことのできない重要な役割を担っているのです。企業にとっては、法令遵守はもちろんのこと、従業員の不安を取り除き、仕事に集中できる環境を整えることで、結果的に定着率の向上にも繋がる大切な取り組みと言えます。
公的手続きへの同行支援が、単に付き添うだけでなく、外国人従業員の安定した日本でのスタートを支える重要な義務であることがお分かりいただけたでしょうか。その重要性を理解した上で、次に気になるのは「具体的にどんな手続きが対象になるのか?」という点ですよね。
同行支援の対象となる主な「公的手続き」

それでは、受け入れ企業が「公的手続きへの同行」としてサポートすべき手続きには、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
特定技能外国人が日本で安定した生活を送り、適切に就労するためには、いくつかの重要な公的手続きを完了させる必要があります。この章では、義務的支援として企業によるサポートが特に求められる主な手続きをご紹介します。
① 住所に関する手続き(市区町村役場)
まず基本中の基本であり、非常に重要なのが、住居地を管轄する市区町村役場で行う住所に関する手続きです。
日本に入国した後や、国内で引っ越しをした際には、新しい住所に住み始めてから法律により14日以内に「転入届」または「転居届」を提出しなければなりません。この手続きによって在留カードの裏面に新しい住所が記載され、これが日本での公的な住所証明となります。この14日という期限は厳守する必要があり、もし正当な理由なく届け出を怠ると、20万円以下の罰金が科せられるだけでなく、最悪の場合、在留資格が取り消される可能性すらあります。
このように重要な手続きを確実に、かつ期限内に行えるよう、窓口への同行や書類記入のサポートを行うことが求められます。
② 社会保障・税に関する手続き(役場・年金事務所・税務署など)
次に、健康保険や年金といった社会保障、そして税金に関する手続きもサポートの対象です。
日本で働く以上、特定技能外国人も原則としてこれらの制度に加入し、保険料や税金を納める義務があります。多くの場合、会社の社会保険に加入しますが、状況によっては国民健康保険や国民年金への加入手続きが別途必要になることもあります。
その際は、市区町村役場や年金事務所での手続きが必要になります。また、住民税に関しては、入国した初年度や年度の途中で転職した場合など、給与からの天引き(特別徴収)ではなく、本人が直接納付書で納める「普通徴収」となるケースがあります。
この場合、金融機関やコンビニでの納付手続きが必要となるため、その方法を教えたり、必要に応じて同行したり、納付がきちんと行われているか確認したりすることも、安定した生活を支える上で大切な支援となります。
③ 在留資格に関する手続き(出入国在留管理局)
在留資格そのものに関連する手続きも忘れてはなりません。
例えば、受け入れ企業(所属機関)の名称や所在地が変わった場合、あるいは雇用契約が終了したり、本人が(同一分野内で)転職したりした際には、14日以内に出入国在留管理局へ届け出る義務があります。これらの届出自体は外国人本人が主体となって行うものですが、手続きに関する正確な情報提供や、必要書類(例:新しい雇用契約書の写しなど)の準備を補助することは、義務的支援の一環です。
手続きが複雑であったり、本人が強い不安を感じていたりする場合には、任意ではありますが、入管への届出に同行することも、円滑な手続き完了のための有効なサポートと言えるでしょう。
④ マイナンバーに関する手続き(市区町村役場)
日本に中長期滞在する外国人には、一人ひとり固有のマイナンバー(個人番号)が割り当てられます。
このマイナンバーは、社会保障や税金の手続きなどで必要となる非常に重要な番号です。マイナンバーカードの申請や、発行されたカードの受け取りは市区町村役場で行います。カードの申請方法を説明したり、受け取りのために窓口へ同行したりするなど、スムーズな取得と適切な管理ができるようサポートすることが望まれます。
⑤ その他(必要に応じて)
上記のほかにも、地域での日常生活を送る上で必要となる細かな手続きが出てくることがあります。
一例として、通勤や買い物で自転車を利用する際に推奨される防犯登録の手続きなどが考えられます。これらは厳密には義務的支援の必須項目ではないかもしれませんが、外国人従業員が地域社会に早くなじみ、安心して生活できるよう、必要に応じて情報提供や簡単なサポートを行うことは、企業と従業員の良好な関係を築く上できっと役立つはずです。
住所登録、社会保障、税金、在留資格、マイナンバー…特定技能外国人のためにサポートすべき公的手続きは、このように多岐にわたることがお分かりいただけたかと思います。
「同行支援」の具体的な中身:ただ付き添うだけじゃない!

「公的手続きへの同行」と聞くと言葉通り、役所などの窓口へただ一緒に行ってあげる、そんなイメージを持たれるかもしれません。
しかし、特定技能の義務的支援として求められているのは、もっと踏み込んだ、きめ細やかなサポートです。この章では、「同行支援」が具体的にどのような内容を含むのか、その中身を「事前準備」「窓口当日」「手続き後」の3つのステップに分けて詳しく解説していきます。
事前準備のサポート
実は、窓口へ行く前の「事前準備」の段階からサポートは始まっています。
多くの行政手続きでは、申請書以外にも様々な書類の提出が求められます。例えば、在留カードやパスポートといった身分証明書はもちろん、手続きによっては雇用契約書、住民票、収入証明などが必要になることも。
どの手続きにいつまでに、どんな書類が必要なのかを事前に正確に把握し、外国人本人に分かりやすく伝え、書類の収集や準備を手伝うことが非常に重要です。申請書類の記入についても同様です。どこに何を書くのか、記入例を示しながら丁寧に説明したり、記入漏れや間違いがないか一緒に確認したりといった補助を行います。
ただし、ここで大切なのは、あくまで本人が主体的に手続きを進められるように「補助」する、というスタンスです。企業担当者が代わりにすべて記入してしまう「代筆」は認められていませんので、注意しましょう。本人が内容を理解し、自らの手で記入できるようサポートすることが基本です。
窓口でのサポート
事前準備がしっかりとできたら、いよいよ手続きを行う窓口へ「同行」します。
ここでも単に付き添うだけでなく、外国人従業員が安心して手続きに臨めるよう、積極的なサポートが求められます。まず、広い庁舎などで迷わないよう、目的の窓口まで案内し、受付番号を取って待つといった一連の流れを説明します。
そして、窓口での職員とのやり取りが最も重要なサポート場面です。職員からの説明や質問の内容を、外国人本人が正確に理解できるよう、必要に応じて通訳をしたり、難しい専門用語を簡単な言葉に言い換えたりして、丁寧に補足説明を加えます。手続きが複数の窓口にまたがるような場合は、次にどこへ行けばよいかを示し、スムーズに移動できるよう案内することも大切です。
ここでも「代わりにやってあげる」のではなく、本人が状況を理解し、主体的に関われるよう、あくまで「サポート役」に徹する意識が重要になります。
手続き後のフォロー
無事に手続きが完了しても、まだ終わりではありません。
丁寧な「手続き後のフォロー」も、同行支援の大切な一部です。まずは、申請がきちんと受理され、手続きが間違いなく完了したことを、本人と一緒に確認しましょう。その結果として、新しい在留カードや住民票、健康保険証といった公的な書類が交付された場合には、それらの書類が持つ意味、どのような場面で必要になるのか、そして紛失しないようにどのように保管・管理すべきかを、改めて丁寧に説明します。
特に在留カードは常時携帯が義務付けられているなど、重要書類の取り扱いに関する注意喚起も必要です。手続きによっては、後日改めて決定通知書や新しいカードなどが郵送されてくるケースもありますので、その旨を伝え、受け取りについても気にかけてあげると、より安心感が増すでしょう。
このように、「同行支援」は事前準備から事後のフォローまで、一連の流れの中で継続的に行われる、想像以上に手厚いサポート内容を含んでいるのです。
ただ付き添うだけではない、外国人従業員が安心して手続きを終えられるためのきめ細やかな配慮が求められます。
同行支援を実施する上での注意点
特定技能外国人に対する公的手続きの同行支援は、事前準備から事後フォローまで、丁寧さが求められる重要な業務です。
この支援を実際に進めるにあたっては、いくつか特に注意しておきたい大切なポイントがあります。これらの点を事前にしっかりと理解し、準備しておくことで、思わぬトラブルを防ぎ、外国人従業員にとって本当に役立つサポートを提供することにつながります。
期限厳守!特に重要な「14日ルール」
まず何よりも注意すべきは、各種手続きに設けられている「期限」です。
日本の行政手続きは、期限に厳しいものが少なくありません。中でも特に注意が必要なのが、住所変更に関する届出です。新しい住所に住み始めてから「14日以内」に市区町村役場へ届け出ることは法律上の義務であり、この期限を守らないと、最悪の場合20万円以下の罰金が科せられることもあります。
さらに、正当な理由なく90日以上届け出を怠ると、在留資格そのものが取り消されるという、非常に深刻な事態を招くリスクも存在します。受け入れ企業としては、外国人従業員がうっかり期限を過ぎてしまうことがないよう、手続きのスケジュール管理を徹底し、早めの対応を促すとともに、確実な同行サポートを行う責任があります。
「本人が理解できる言語」でのサポート
次に、コミュニケーションの基本となる「言語」への配慮も欠かせません。
義務的支援の大原則として、提供する情報は外国人本人が内容を「十分に理解できる言語」、つまり多くの場合、母国語で伝える必要があります。公的な手続きに関する説明や申請書類には、普段使わないような難しい言葉や専門用語が多く登場します。たとえ日常会話レベルの日本語が話せる方であっても、これらの内容を正確に理解するのは容易ではありません。
そのため、原則として本人の母国語で説明を加えるか、それが難しい状況であれば、信頼できる通訳を手配する、あるいは出入国在留管理庁が提供している多言語対応の資料を積極的に活用するといった工夫が不可欠です。言語の壁による誤解や理解不足は、手続きのミスや後々の大きなトラブルに繋がりかねません。根気強く、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
費用負担の原則
同行支援を行う際の費用負担についても、誤解のないようにルールを正しく理解しておく必要があります。
手続きのために役所などへ移動する際の交通費や、必要に応じて外部の通訳者を依頼した場合の費用など、この義務的支援を実施するために直接かかった経費は、法律により、全て受け入れ企業(または支援委託先の登録支援機関)が負担しなければならないと定められています。
これらの費用を、理由の如何を問わず特定技能外国人本人に負担させることは認められていません。費用負担のルールを遵守し、適切な会計処理を行うことが求められます。
あくまで「補助」。本人の主体性を尊重
最後に、支援を行う際の心構えとして非常に大切なのが、同行支援はあくまで「補助」であるという基本スタンスです。
手続きを実行する主体は、特定技能外国人本人である、ということを常に忘れてはいけません。受け入れ企業や支援担当者の役割は、本人がスムーズかつ正確に手続きを完了できるようお手伝いをすることであり、全てを代わりにやってあげることではありません。
本人の意思を無視して勝手に話を進めたり、必要以上に介入してしまったりすることは避けましょう。
むしろ、手続きを通じて本人が日本の社会システムやルールを学び、少しずつ自立して生活していけるようになることを応援する、という視点を持つことが大切です。本人が自分でできること、助けが必要なことを見極め、適切な距離感を保ちながらサポートすることが、信頼関係を築く上でも重要になるでしょう。
期限の管理、言語への配慮、正しい費用負担、そして支援の基本スタンス。これらの注意点をしっかりと守ることが、法令を遵守し、かつ外国人従業員の心に寄り添った適切な同行支援を実現する鍵となります。
自社で行う?登録支援機関に委託する?
特定技能外国人に対する公的手続きの同行支援は、その内容の広さや専門性から、受け入れ企業にとって大きな課題となることがあります。
そこで重要になるのが「これらの支援を自社で直接行うのか、それとも専門の登録支援機関に業務を委託するのか」という選択です。
この章では、それぞれの方法が持つメリットとデメリットを比較し、貴社にとってより良い選択をするための判断ポイントを探っていきましょう。
自社対応のメリット・デメリット
まず、全ての義務的支援を自社の担当者が中心となって行う場合です。
このアプローチの大きなメリットは、外部への委託費用がかからないため、コストを直接的に抑えられる点にあります。また、支援を通じて外国人従業員と日々接することで、コミュニケーションが密になり、より強固な信頼関係を築きやすいという利点も考えられます。さらに、受け入れや支援に関する実務経験を重ねることで、貴重なノウハウが社内に蓄積され、将来的な受け入れ体制の強化につながる可能性も秘めています。しかし、その一方でデメリットも無視できません。最も大きいのは、担当者の業務負担が大幅に増加してしまうことです。通常業務に加えて、複雑な行政手続きの調査、書類作成の補助、頻繁な窓口への同行、そして多言語での対応などが求められ、特にリソースが限られがちな中小企業にとっては、担当者が疲弊してしまう懸念があります。
加えて、担当者に特定技能制度や関連法規に関する正確な知識が不足している場合、意図せず法令違反を犯してしまったり、必要なサポートを十分に提供できなかったりするリスクも考慮に入れるべきでしょう。
登録支援機関への委託のメリット・デメリット
次に、出入国在留管理庁に正式に登録された専門機関である「登録支援機関」に支援業務を委託する場合を見てみましょう。
最大のメリットは、やはり専門的な知識と豊富な経験を持つプロフェッショナルによる、質の高い、安定した支援が期待できることです。登録支援機関は、常に最新の法令情報に基づいて業務を行っており、多言語対応が可能なスタッフを配置している場合も多いため、企業は安心して支援業務を任せられます。結果として、自社の人事・総務担当者の負担は大幅に軽減され、採用や育成といった本来注力すべき業務に集中できる環境が生まれます。コンプライアンス遵守という観点からも、専門機関への委託は大きな安心材料となるでしょう。ただし、当然ながらデメリットも存在します。
それは、委託費用が発生することです。支援内容や委託する機関によって費用は様々ですが、毎月継続的に発生するコストとなるため、事前に複数の機関から見積もりを取り、提供されるサービス内容と費用が見合っているかを慎重に検討する必要があります。また、登録支援機関の質にはばらつきがある可能性も指摘されているため、実績や評判をよく確認することも大切です。
判断のポイント
では最終的に自社対応と委託のどちらを選ぶべきか、どのように判断すれば良いのでしょうか。
残念ながら「絶対にこちらが良い」という唯一の正解はありません。重要なのは、自社の状況を客観的に分析し、総合的に判断することです。具体的には、今後受け入れる特定技能外国人の予定人数、担当部署の人的リソースや業務の余裕度、社内での外国語対応能力の有無、特定技能制度に関する知識や経験の蓄積度などを冷静に評価する必要があります。また、手続きの複雑さや頻度、そして「外国人従業員に対してどこまで手厚いサポートを提供したいか」という会社としての方針も、重要な判断材料となるでしょう。
コスト面だけにとらわれず、支援の質、担当者の負担、法令遵守のリスク、そして将来的な体制なども含めて多角的に比較検討し、自社にとって最も合理的で持続可能な方法を選択することが求められます。場合によっては、まずは自社で一部の支援を試してみて、難しければ委託に切り替える、あるいは特定の支援項目だけを委託するといった柔軟な対応も考えられます。
自社での支援と登録支援機関への委託、それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらを選ぶかは簡単な決断ではないかもしれません。
まとめ:確実な手続きサポートで、安心のスタートを
この記事では、特定技能外国人を受け入れる際の重要な義務的支援の一つ「公的手続きへの同行」に焦点を当て、その目的、対象となる手続き、具体的なサポート内容、注意点、そして実施体制について詳しく解説してきました。
最後に、本記事のポイントを振り返り、この支援がいかに外国人従業員の円滑な受け入れと活躍に不可欠であるかを確認しましょう。
公的手続きへの同行支援は、特定技能1号の外国人従業員が、日本での生活と就労に必要な様々な行政手続きを、確実に、そして期限内に完了させるための、法律で定められた重要なサポートです。
住所登録から社会保障、税金、在留資格関連まで、サポートすべき手続きは多岐にわたります。企業には、単に窓口へ一緒に行くだけでなく、事前の書類準備の補助、当日のコミュニケーションサポート、手続き後のフォローアップまで、一貫した丁寧な支援が求められます。
その際には、手続きの期限を守ること、本人が理解できる言語で説明すること、支援にかかる費用は企業が負担すること、そして手続きの主体はあくまで本人であるという原則を尊重することが極めて重要です。これらの支援を自社で行うか、専門の登録支援機関に委託するかは、自社のリソースや方針を踏まえて慎重に選択する必要があります。
こうした確実な手続きサポートは、法令遵守という側面はもちろんですが、それ以上に大きな意味を持ちます。慣れない異国での複雑な手続きに対する外国人従業員の不安を直接取り除き「この会社は頼りになる」という安心感と深い信頼関係を築くための、またとない機会なのです。スムーズに行政手続きを終え、生活基盤が早期に安定することは、彼らが仕事に集中し、持てる能力を存分に発揮するための大前提となります。
結果として、従業員の定着率向上にも繋がり、企業にとってかけがえのない人材として長く活躍してくれる基盤が築かれるでしょう。
私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
関連するオススメ記事はこちら
- 登録支援機関の義務的支援その⑤「公的手続きへの同行」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その④「生活オリエンテーション」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その③「住居の確保・契約支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その②「出入国時の送迎」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その①「事前ガイダンス」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援・任意的支援とは?人事担当者が知るべき違い・費用・選び方を徹底解説
- 特定技能1号で家族の帯同ができる?要件・必要書類について徹底解説
- 特定技能外国人の転職について|要件・手続き・注意点を解説
- 特定技能ビザから技人国ビザへの変更方法について|要件・方法・注意点を解説
- 特定技能ビザで働く【外国人】のメリット・デメリットについて

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート