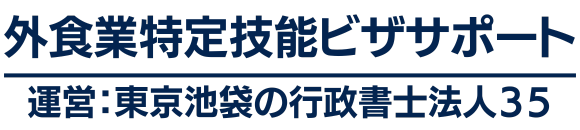登録支援機関の義務的支援その⑥「日本語学習の機会の提供」とは?|特定技能外国人
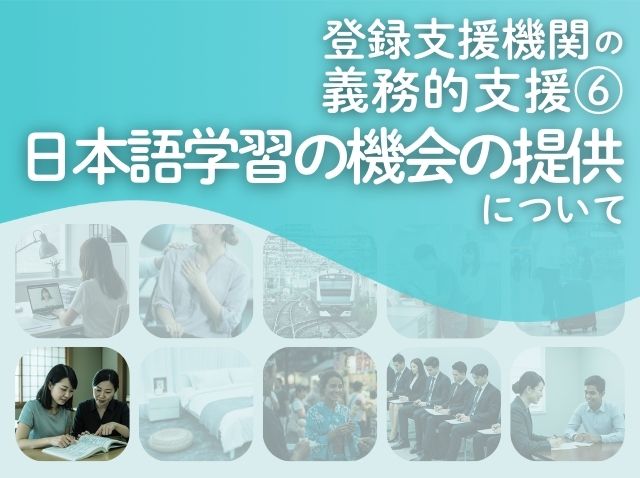
特定技能外国人材の受け入れ準備、本当にお疲れ様です。
様々な義務的支援項目を確認する中で
「日本語学習の機会の提供」という項目について
「具体的にどんなサポートを指すのだろう?」
「会社で日本語の授業を開く必要があるのか?」
「関連する費用はどこまで会社負担?」
など、具体的な実施方法や企業の責任範囲について、疑問を感じていらっしゃる人事担当者様も少なくないでしょう。
この記事は、まさにそうした疑問にお応えするために作成しました。
特定技能制度における義務的支援の一つ「日本語学習の機会の提供」が具体的に何を意味するのかを明確にし、企業として実施すべき主な3つの支援方法、費用負担に関する大切なルール、そして支援を行う上で注意すべき点について、順を追って分かりやすく解説いたします。
目次
特定技能外国人の義務的支援「日本語学習の機会の提供」とは?
それでは、「日本語学習の機会の提供」という支援が、特定技能制度の中でどのような役割を担っているのか、基本的な内容から確認していきましょう。
なぜ受け入れ企業がこのサポートを提供することが「義務」とされているのか、その目的と重要性について、具体的に解説します。
なぜ日本語学習のサポートが必要なのか?その目的
特定技能外国人が日本でその能力を発揮し、充実した生活を送る上で、日本語能力は欠かせないスキルとなります。
生活オリエンテーションで基礎知識を得たとしても、日々の業務指示の理解、同僚との円滑なコミュニケーション、さらには日常生活での様々な場面に対応するためには、継続的な日本語学習が不可欠です。
この支援の主な目的は、外国人従業員が職場でのコミュニケーション能力を高め、安全に業務を遂行できるようにすること、そして日本の社会習慣やルールへの理解を深め、地域社会にスムーズに適応できるよう手助けすることにあります。言葉の壁が低くなることは、誤解やトラブルを未然に防ぐだけでなく、外国人従業員自身の自信や仕事への意欲を高め、結果的に長く会社に貢献してくれる人材へと成長する大きな要因となります。
実際に、来日する特定技能外国人の多くが、自身の日本語能力向上に高い関心を持っています。
義務的支援としての位置づけ
この「日本語学習の機会の提供」は、特定技能1号の外国人を受け入れる全ての企業に法律で義務付けられている10項目の支援(義務的支援)の一つです。
企業は、外国人従業員から日本語学習に関する希望を聞き取り、その希望に応じて、例えば日本語教室の情報を提供する、自主学習教材を紹介する、あるいは企業自身が講習を企画するなど、何らかの形で学習機会を提供することが求められます。
ここで注意すべき点は、この支援義務は特定技能「1号」の外国人が対象であるということです。より熟練した技能を持つ特定技能「2号」の外国人に対しては、日本語学習機会の提供は法的な義務とはされていません。受け入れ企業としては、この対象者の違いを正確に理解しておくことが大切です。
日本語学習の機会提供が、単に語学力を伸ばす手伝いというだけでなく、特定技能外国人の活躍と定着を支える基盤となる重要な法的義務であることが、お分かりいただけたでしょうか。
この重要性を踏まえ、次の章では、企業が具体的にどのような方法でこの「機会」を提供できるのか、その選択肢について詳しく見ていきます。
受入れ機関が提供すべき日本語学習機会の「3つの方法」

特定技能外国人に対する日本語学習支援の重要性をご理解いただけたところで、いよいよ「具体的に、企業として何をすれば良いのか?」という実践的な内容に入っていきましょう。出入国在留管理庁が示しているガイドラインによれば、企業が提供すべき日本語学習の機会には、主に3つのアプローチがあります。
どの方法を選ぶにしても、最も大切なのは、一方的に押し付けるのではなく、外国人従業員ご本人の希望や日本語のレベル、生活スタイルなどをしっかりと聞いた上で、最適な支援を提供することです。
方法①:地域の日本語教室や学校の情報提供と手続き補助
一つ目のアプローチは、外国人従業員が通える範囲にある日本語学習の場についての情報を提供し、入学をサポートする方法です。
具体的には、従業員が住んでいる地域や会社の近くにある日本語教室、民間の日本語学校、あるいは大学などが社会人向けに開講している日本語講座などの情報を集めて、分かりやすく伝えます。情報の探し方としては、インターネット検索のほか、地域の自治体のウェブサイトや国際交流協会などに問い合わせるのも良いでしょう。
そして、もし外国人従業員が「この教室に通いたい」と希望した場合には、入学願書の取り寄せを手伝ったり、記入方法を教えたり、申し込み手続きに必要であれば同行したりといったサポートを行うことが求められます。特に、自治体が運営している比較的費用負担の少ない日本語教室や、地域のNPOなどが運営するボランティア日本語教室も存在しますので、そうした情報も併せて提供できれば、本人にとって選択肢が広がり、より親切な支援となるでしょう。
方法②:自主学習教材やオンライン講座の情報提供と利用補助
二つ目のアプローチは、外国人従業員が自分のペースで日本語を学習したい場合に、その自主学習をサポートする方法です。
具体的には、市販されている日本語の教科書、単語帳、問題集、あるいはスマートフォンで手軽に使える日本語学習アプリといった教材に関する情報を提供します。また、近年ますます充実してきているオンライン日本語レッスンやeラーニングのプラットフォームに関する情報提供も、非常に有効な支援策です。情報提供だけでなく、もし本人が「この教材を買いたい」「このオンライン講座に申し込みたい」と希望した際には、購入場所(書店やオンラインストアなど)を教えたり、ウェブサイトでの契約手続きを手伝ったりすることも支援内容に含まれます。
この方法を選ぶ際は、本人の現在の日本語レベル(初級・中級・上級など)や学習したい内容(日常会話なのか、仕事で使う専門用語なのか、JLPTなどの資格取得を目指すのかなど)に合わせて、適切な教材や講座を選ぶ手助けをしてあげることが大切です。
文化庁のウェブサイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」のような、国が提供している無料のオンライン学習コンテンツを紹介するのも、費用負担を抑えたい本人にとっては大変役立ちます。
方法③:企業による日本語講習の実施(講師との契約)
三つ目のアプローチは、受け入れ企業がより積極的に関与し、自ら日本語学習の場を設ける方法です。
例えば、企業が日本語教育の専門家(日本語教師など)や語学学校と直接契約を結び、会社の会議室などを利用して、外国人従業員向けの日本語講習を定期的に開催します。あるいは、社内に日本語教育の経験や資格を持つ従業員がいれば、その方に講師をお願いすることも考えられます。この方法のメリットは、従業員のレベルや業務内容に合わせたカリキュラムを組みやすく、学習進捗を把握しやすい点です。
ただし、実施にあたっては、必ず事前に外国人本人との間で、講習を行う時間帯(業務時間内なのか、それとも業務時間外なのか)、頻度、場所、学習内容などについて、しっかりと話し合い、双方合意の上で進める必要があります。一方的に参加を義務付けることはできません。また、講師への報酬や教材費などのコスト、講習の企画・運営の手間がかかる点はデメリットと言えるでしょう。業務とのバランスや本人の意欲なども考慮し、無理なく続けられる計画を立てることが成功の鍵となります。
このように、日本語学習の機会を提供する義務的支援には、情報提供が中心となるものから、企業が主体的に学習環境を整えるものまで、いくつかの選択肢が存在します。
日本語学習支援における費用負担のルール
特定技能外国人に日本語学習の機会を提供する際、人事ご担当者様にとって、費用の問題は避けて通れません。「日本語学校の授業料まで会社が負担する必要があるの?」「教材費は本人持ちで良いのだろうか?」など、どこまでが企業の責任範囲なのか、気になるところでしょう。この章では、日本語学習支援に関する費用について、誰が何を負担すべきか、そのルールを分かりやすく整理して解説します。
企業が負担すべき費用(義務)
まず、法律上の義務的支援として、受け入れ企業が必ず負担しなければならない費用から見ていきましょう。
これは、前の章で説明した「日本語学習の機会を提供する」という行為そのものに直接かかるコストを指します。具体例を挙げると、地域の日本語教室や学校に関する情報を集めて提供するための費用、外国人本人が入学を希望した場合にその手続きを手伝う担当者の人件費や窓口までの交通費、自主学習用の教材やオンライン講座の情報を探し、利用契約の手続きを補助するための費用などです。
もし企業が主体となって日本語教師と契約し、社内で日本語講習を行うのであれば、その講師に支払う謝礼や教材準備費、会場費なども、当然ながら企業の負担となります。ポイントは、「学習の『機会』を作る、または案内するための費用」は企業が負担する、と覚えておくと良いでしょう。これらの費用を、名目に関わらず特定技能外国人本人に支払わせることは、法律で禁止されています。
本人負担としても良い費用(任意)
一方で、外国人ご本人に負担をお願いしても問題ない費用もあります。
それは、実際に日本語学習のサービスを受けること自体にかかる費用、つまり「学習そのものにかかる実費」です。例えば、日本語学校や日本語教室に通う場合の入学金や月々の授業料、自分で書店やオンラインで購入する教科書、単語帳、問題集といった教材の代金、有料のオンライン日本語講座の受講料などが、これに該当します。
これらの費用について、法律上、企業が必ず負担しなければならないという義務はありません。ただし、企業がこれらの費用を負担しない場合でも、その金額が外国人従業員の給与水準から見て過度な負担にならないよう、配慮することが望ましいと言えます。
任意支援としての費用負担
上記のように、授業料や教材費などの実費は、企業が負担する義務はありません。
しかし、企業が「任意的支援」として、これらの費用の一部または全部を補助することは、もちろん可能ですし、多くのメリットが期待できます。これは福利厚生の一環として、従業員の自己啓発を積極的に支援する姿勢を示すことにも繋がります。例えば、日本語能力試験(JLPT)の受験料を会社が負担したり、目標レベルに合格した際に報奨金を支給したり、日本語学校の授業料の一部を補助したりする制度を設ける企業もあります。
こうした積極的な支援は、外国人従業員の日本語学習へのモチベーションを大きく高め、結果として職場でのコミュニケーション円滑化や、企業へのエンゲージメント向上、ひいては長期的な定着にも良い影響を与える可能性があります。
ただし、任意支援であっても、一度支援計画書に「費用を補助する」と記載した場合は、それを実行する義務が発生しますので注意が必要です。
また、あくまで本人の学習意欲を尊重し、高価な教材やコースへの加入を無理強いしたり、費用負担を強要したりすることがないよう、十分な配慮が求められます。
日本語学習支援に関する費用負担のルール、整理できましたでしょうか。
「機会提供」に関する費用は企業が負担し、「学習サービスそのもの」の費用は原則として本人が負担する、ただし企業が任意で補助することも可能、という点がポイントです。この線引きを正しく理解し、外国人従業員にも誤解のないように丁寧に説明しておくことが、後々の不要なトラブルを避けるために非常に重要です。
日本語学習支援を実施する上での注意点

特定技能外国人への日本語学習機会の提供は、単に場を設ければ良いというわけではありません。
その支援が本当に外国人従業員の力となり、かつ法令を遵守した適切なものとなるよう、実施する上でいくつか心に留めておくべき大切な注意点があります。これらのポイントを意識することで、よりスムーズで効果的なサポートが実現できるでしょう。
外国人本人の希望を尊重する
まず何よりも大切なのは、日本語学習の進め方について、外国人従業員ご本人の意向をしっかりと尊重することです。
「会社が決めたから」と一方的に特定の日本語学校や教材、学習時間を押し付けても、本人のやる気が伴わなければ効果は上がりませんし、かえってストレスを与えてしまうことにもなりかねません。
支援を始める前には、本人が「どんな方法で学びたいか(教室?独学?オンライン?)」「どんなレベルを目指したいか」「どんな時間帯なら学習しやすいか」などを丁寧にヒアリングしましょう。その上で、本人の希望や状況に最も合った支援方法を一緒に考え、選択していく姿勢が重要です。学習の主役はあくまで外国人本人である、ということを忘れないようにしたいですね。
継続的な関与と学習環境への配慮
日本語の習得には時間がかかります。
したがって、最初のオリエンテーションや情報提供だけで終わらせず、継続的に関心を持ち、サポートを続けていく視点が不可欠です。
定期的に実施する面談の機会などを利用して「日本語の勉強は順調ですか?」「何か学習で困っていることはありませんか?」といった声かけをし、学習状況を把握しましょう。
本人のレベルアップに応じて新しい教材やステップアップできる教室の情報を提供したり、学習方法に関する相談に乗ったりすることも、モチベーション維持に繋がる有効なサポートです。また、学習に集中できる環境への配慮も大切です。
自主学習を支援する場合は、静かに勉強できる社内のスペースや地域の図書館を紹介する、社内講習の場合は業務との兼ね合いを考慮して無理のないスケジュールを組むなど、学習しやすい環境を整えることも、支援の質を高める上で重要な要素となります。
費用負担のルールを遵守する
前の章で詳しく説明しましたが、費用負担のルールを正しく理解し、遵守することも極めて重要です。
日本語学習の「機会を提供する」ために必要な費用(情報収集費、手続き補助の人件費・交通費、企業が契約する講師料など)は、受け入れ企業が負担しなければなりません。これらの費用を外国人本人に請求することは法律で禁じられています。一方で、日本語学校の授業料や教材費といった「学習サービスそのもの」の費用は、本人負担とすることが原則可能です。この線引きを明確に理解し、誤った費用請求を行わないよう注意が必要です。
義務の不履行は重大なリスクに繋がる可能性も
最後に、繰り返しになりますが「日本語学習の機会の提供」は法律で定められた企業の「義務」であることを再認識してください。
もし、必要な支援を怠っていると判断されれば、出入国在留管理庁から指導を受けたり、最悪の場合、特定技能外国人の受け入れ自体ができなくなったりする可能性があります。さらに、適切な支援を受けられずに在留資格の維持が困難になった外国人を知りながら雇用を続けることは、企業が「不法就労助長罪」に問われるリスクも伴います。
この罪は非常に重く、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。法令を遵守し、定められた支援を誠実に実施することが、企業自身を守ることにも繋がるのです。
本人の意思尊重、継続的な関わりと環境整備、正しい費用負担、そして法令遵守。これらの注意点を守り、丁寧な日本語学習支援を行うことが、特定技能外国人の円滑な受け入れと活躍、そして定着に繋がります。
まとめ:日本語能力向上は、本人と企業の双方にメリット
今回は、特定技能1号外国人を受け入れる際の重要な義務的支援「日本語学習の機会の提供」について、その目的から具体的な支援方法、費用負担の考え方、そして実施にあたっての注意点までを詳しく解説いたしました。
最後に、この記事の要点を振り返り、この支援が持つ大切な意味合いを再確認しましょう。
「日本語学習の機会の提供」は、法律で定められた受け入れ企業の義務であり、特定技能外国人が日本での仕事と生活の基盤を築く上で欠かせないサポートです。
企業には
①地域の日本語教室等の情報提供・手続き補助
②自主学習教材等の情報提供・利用補助
③企業自身による日本語講習の実施
という3つの方法の中から、本人の希望を尊重しつつ適切な機会を提供することが求められます。
「機会提供」の費用は企業負担、「学習実費」は原則本人負担というルールを理解し、本人の希望尊重、継続的な関与、学習しやすい環境への配慮、そして法令遵守を心がけることが大切です。
この日本語学習支援は、単に義務だから行うという以上に、受け入れる企業にとっても、働く外国人従業員にとっても、多くのメリットをもたらします。
日本語が上達すれば、職場でのコミュニケーションはずっとスムーズになり、業務指示の理解も深まるため、仕事の効率や安全性が高まります。日常生活での不安が減り、地域社会との関わりも持ちやすくなることで、本人のモチベーション向上や日本での生活満足度アップにも繋がるでしょう。
企業側から見れば、法令遵守はもちろんのこと、従業員のスキルアップを後押しし、働きがいのある環境を提供することは、優秀な人材に長く活躍してもらうための有効な手段であり、企業の成長を支える力にもなり得るのです。
私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
関連するオススメ記事はこちら
- 登録支援機関の義務的支援その⑩「定期面談・行政機関への通報」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑨「転職支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑧「日本人との交流促進」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑦「相談・苦情への対応」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑥「日本語学習の機会の提供」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑤「公的手続きへの同行」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その④「生活オリエンテーション」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その③「住居の確保・契約支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その②「出入国時の送迎」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その①「事前ガイダンス」とは?|特定技能外国人

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート