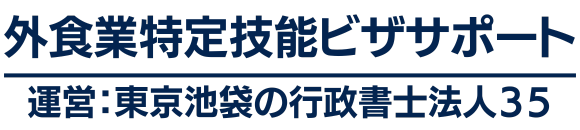登録支援機関の義務的支援その⑩「定期面談・行政機関への通報」とは?|特定技能外国人

特定技能外国人の方の受け入れ、そして日々のサポート、本当にお疲れ様です。
義務付けられた支援項目の中でも「定期的な面談」や、それに伴う可能性のある「行政機関への通報」については、「面談では、具体的にどんなことを確認すべきなのだろうか?」「どのような状況になったら、どこへ通報しなければならないのか?」「面談の記録って、どの程度詳しく残す必要があるの?」など、具体的な運用方法や責任の所在について、戸惑いやご不安を感じていらっしゃる人事担当者の方も少なくないでしょう。
この記事は、まさにそうした人事ご担当者様の疑問や心配事を解消するために書かれました。特定技能制度における義務的支援である「定期的な面談」と「行政機関への通報」が、それぞれ何を意味し、どのような目的を持つのか。
そして、具体的な実施方法、面談で必ず確認すべきポイント、通報義務が発生する具体的なケース、関連する記録の適切な管理方法、さらには注意すべき点まで、全体像を掴めるように分かりやすく解説いたします。特定技能ビザ申請と支援実務のエキスパートである行政書士が、最新の法令や出入国在留管理庁の指針に基づいて丁寧に説明しますので、この記事を最後までお読みいただければ、面談と通報に関する企業の役割と責任を正確に理解し、自信を持って適切な対応を進めることができるようになります。
目次
特定技能の義務的支援「定期面談・行政機関への通報」とは?
特定技能外国人の方を雇用する上で知っておくべき「義務的支援」
その中でも、継続的な関わりと、時には重大な判断が求められるのが「定期的な面談」と「行政機関への通報」です。
初めて対応される人事担当者様にとっては、その内容や目的が分かりにくい部分もあるかもしれません。この章では、まずこの二つの支援がどのようなもので、なぜ企業にとって大切な義務なのか、基本的な考え方から解説していきます。
義務的支援としての位置づけ
特定技能1号の外国人材を受け入れる企業は、10項目からなる「義務的支援」を確実に実施しなければなりません。
「定期的な面談の実施、及び行政機関への通報」は、この支援リストの最後に挙げられることが多いですが、その重要性は決して低くありません。これは、入国後の生活オリエンテーションや日々の相談対応だけではカバーしきれない、外国人従業員の就労状況や生活状況の変化を継続的に把握し、問題があれば適切に対処するための、いわば「定期健診」のような役割を担う支援です。支援計画が適切に実行されているかを確認し、必要に応じてサポート内容を見直すための、重要なプロセスと位置づけられています。
なぜ「定期面談」と「通報」が必要なのか?その目的
では、なぜ最低でも3ヶ月に1回という頻度で面談を行い、場合によっては行政機関への通報まで行うことが義務付けられているのでしょうか。
まず「定期面談」の主な目的は、外国人従業員ご本人、そしてその仕事を直接監督する立場の方(上司など)それぞれから、定期的に直接話を聞くことで、労働条件が守られているか、生活環境に問題はないか、健康状態や職場での人間関係は良好か、といった実情を正確に把握することにあります。
言葉や文化の違いから、普段は言い出しにくい悩みや困り事を抱えている可能性もあります。面談は、そうした潜在的な問題を早期に発見し、深刻化する前に対処するための大切な機会となります。同時に、定期的に顔を合わせて話を聞くことは、外国人従業員との信頼関係を築き、維持していく上でも非常に有効です。
一方、「行政機関への通報」が義務付けられている目的は、より深刻な事態への対応です。
面談などを通じて、賃金不払いや長時間労働といった労働基準法違反、あるいは暴行・脅迫といった人権侵害にあたるような、看過できない重大な法令違反の事実を知った場合、企業にはそれを隠蔽せず、労働基準監督署や出入国在留管理庁などの適切な行政機関に報告する責任があります。これは、個々の企業だけでは解決が難しい問題に対して、公的な権限を持つ機関による調査や是正措置を促し、外国人労働者の権利を実効的に保護するための重要な仕組みです。
企業にとっては、自社のコンプライアンス体制を健全に保ち、特定技能制度の適正な運用に協力するという、社会的な責任を果たすためのプロセスでもあるのです。このように、定期面談は問題を発見する「入口」であり、通報はその後の重大な問題への「対応策」として、密接に関連している支援と言えます。
「定期的な面談」の具体的な実施方法

特定技能外国人に対する義務的支援として欠かせない「定期的な面談」
その重要性は理解できても、「実際にどう進めればいいの?」という疑問は残りますよね。ここでは、面談を行う頻度や誰が誰と行うのか、実施する際の方法や言語、そして面談で確認すべき具体的な内容や記録の残し方について、一つひとつ丁寧に解説していきます。
面談の頻度と担当者
まず、面談はどのくらいの頻度で行う必要があるのでしょうか。
法律では「少なくとも3ヶ月に1回以上」の実施が義務付けられています。つまり、最低でも年に4回は必ず面談の機会を設ける必要があるということです。もちろん、必要に応じてこれより短い間隔で、例えば毎月実施するなど、より頻繁に行うことは全く問題ありません。面談を行うのは、受け入れ企業が選任した「支援責任者」または「支援担当者」となります。もし義務的支援の実施を登録支援機関に委託している場合は、その登録支援機関の担当者が責任を持って実施します。ここで重要なポイントは、面談の対象者は外国人従業員ご本人だけではない、という点です。
その外国人従業員の仕事を直接監督する立場にある方、例えば直属の上司などとも、同じく3ヶ月に1回以上の頻度で面談を行う必要があります。これは、外国人本人からの視点と、現場で一緒に働く監督者からの視点の両方から話を聞くことで、状況をより客観的かつ多角的に把握するためです。なお、面談は、外国人本人と監督者を同席させるのではなく、プライバシーにも配慮し、それぞれ個別に実施することが求められます。
面談の実施方法(対面?オンライン?)
面談をどのように実施するか、その方法についてもルールがあります。
2024年1月からは、原則として「対面」で、直接顔を合わせて実施することが義務付けられました。これは、やはり直接会って話すことで、相手の表情や様子から言葉だけでは伝わらない細かなニュアンスを汲み取ったり、より深い信頼関係を築いたりすることが重視されているためと考えられます。ただし、全ての場合に対面が必須というわけではありません。例えば、船員として遠洋漁業に従事していて長期間陸に戻れない場合など、物理的に対面での実施が著しく難しいケースでは、例外的に無線や船舶電話などでの連絡も認められています。
さらに、今後の動きとして、2025年4月からは、特定技能外国人ご本人が同意すれば、「オンライン形式」、例えばZoomやTeamsといったお互いの顔が見えるビデオ通話システムを使った面談も可能となりました。どの方法を選ぶにしても、最も大切なのは、外国人従業員がリラックスして、安心して本音を話せるような環境を整えることです。
使用言語
面談を実りあるものにするためには、使用する「言語」への配慮が不可欠です。
ルールとして、外国人従業員本人が面談内容を「十分に理解できる言語」、つまり原則としてその方の母国語で実施することが求められています。日常会話が流暢な方であっても、仕事上の細かいニュアンスや待遇に関する話、あるいは法律が関わるような難しい内容になると、日本語だけでは正確な意思疎通が難しい場合があります。
そのため、企業としては、必要に応じて通訳者を同席させる体制を整えるか、多言語対応が可能な支援担当者を置く、あるいは登録支援機関に委託するなどの対応が必要です。言葉の壁が原因で、本人が本当に伝えたいことを話せなかったり、企業側からの説明を誤解してしまったりすることがないよう、最大限の配慮をしましょう。
面談で確認すべき主な内容
では、3ヶ月に1度の定期面談で、具体的にどのような点を確認すれば良いのでしょうか。
確認すべき内容は多岐にわたりますが、主に以下の点を中心にヒアリングを進めると良いでしょう。
- まず、労働条件や待遇について、雇用契約書に書かれている通りの給与がきちんと支払われているか、不当な天引きなどがないか、労働時間や休憩、休日は適切に取得できているか、残業代は正しく計算され支払われているかなどを確認します。
- 次に、業務内容について、現在担当している仕事が、特定技能の在留資格で認められている業務範囲内であるか、入社前に説明された内容と大きく異なっていないかを確認します。
- さらに、職場の安全衛生管理は十分か、パワハラやセクハラ、いじめ、差別といった不当な扱いを受けていないかも重要な確認項目です。
- 加えて、生活面についても、住んでいる部屋の広さや設備に問題はないか、最近の健康状態はどうか、職場や地域での人間関係で悩んでいることはないかなどを尋ね、プライベートな側面にも配慮します。
- 最後に、公的な手続き、例えば住所変更の届出などがきちんと行われているか、社会保険料や税金の納付状況はどうか、その他、出入国管理法や労働関連法令に違反するような状況に陥っていないかなども確認の対象となります。
これらの項目について、外国人本人と監督者の双方から丁寧に話を聞き、状況を正確に把握することが面談の目的です。
面談記録の作成と報告
面談を実施した後は、その内容をきちんと記録に残すことが義務付けられています。
出入国在留管理庁は「定期面談報告書」という様式(外国人本人との面談用は参考様式第5-5号、監督者との面談用は参考様式第5-6号)を用意しており、通常はこの様式を用いて記録を作成します。面談を行った日付、面談を実施した担当者、確認した項目ごとの具体的な内容、本人の回答、そして何か問題点や特筆すべき事項があればその詳細などを、具体的に記載する必要があります。この報告書は、企業が適切な支援を行っていることの重要な証拠となりますし、後々問題が発生した場合に経緯を確認する上でも役立ちます。
以前は、この面談報告書を四半期ごとに行う定期届出の際に、必ず出入国在留管理庁へ提出する必要がありました。しかし、制度が変更され、令和6年(2024年)4月1日以降は、面談の結果、特に問題点が認められなかった場合には、報告書の提出は不要となりました。
ただし、提出が不要になっただけで、面談記録書を作成し、社内(または委託先の登録支援機関)で適切に保管する義務は依然としてありますので、この点は注意が必要です。もし面談で何らかの問題点、特に法令違反の疑いなどが確認された場合には、後述する行政機関への通報義務と関連し、定期届出とは別に対応や報告が必要になる場合があります。
面談の頻度、対象者、実施方法、確認すべき項目、そして記録の作成と保管。定期面談を適切に実施・管理するためには、これら一連のルールを正確に把握し、社内で運用体制を整える必要があります。
「行政機関への通報」が必要になるケースと対応

定期的な面談などを通じて特定技能外国人の状況を把握する中で、もし看過できないような問題点が見つかった場合、受け入れ企業にはそれを適切な「行政機関へ通報する」という、もう一つの重要な義務が課せられています。
これは決して軽いことではありませんが、制度の適正な運用と外国人従業員の保護のために必要な措置です。この章では、どのような場合にこの通報義務が生じるのか、そして実際に通報が必要となった際の具体的な対応について解説します。
通報義務が発生する主なケース
行政機関への通報が必要となるのは、特定技能雇用契約がきちんと守られていない、あるいは出入国や労働に関する日本の法律が守られていないといった、重大な問題が判明した場合です。
具体的にどのような状況が該当するのか、例を挙げてみましょう。
- まず、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法といった労働関係の法律に違反する事実が確認された場合です。例えば、契約内容と異なる低賃金での労働、違法な長時間労働の強制、安全配慮が欠けた危険な作業環境の放置などがこれにあたります。
- 次に、住居に関して法外な家賃を徴収していたり、給与から不明瞭な名目で不当な天引きを行っていたりするなどの金銭的な不正行為が発覚した場合も、通報の対象となり得ます。
- さらに深刻な事態として、外国人従業員に対して暴行や脅迫、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントといった人権侵害行為が行われている場合や、本人の意に反して在留カードやパスポートを取り上げている場合なども、直ちに通報が必要です。
これらはあくまで例ですが、このように外国人労働者の権利を著しく侵害し、法令に違反する重大な事実を企業(または支援担当者)が知った場合には、それを隠さずに通報する法的義務があると理解してください。
どこへ通報するのか?
通報義務が生じた際には、問題の内容に応じて、管轄する適切な行政機関を選んで通報することが重要になります。
どの機関に連絡すべきかは、問題の種類によって異なります。
- 例えば、賃金未払いや違法な残業、解雇に関する問題など、労働基準法に関連する違反であれば、事業所の所在地を管轄する「労働基準監督署」が主な通報先です。
- 暴行や脅迫といった犯罪行為が疑われる場合は、迷わず「警察」に相談・通報しましょう。
- 職場でのいじめや差別など、人権に関わる問題については、「法務局の人権擁護機関」が相談窓口となります。
- 在留資格に関する不正行為(例:許可されていない業務に従事させている)や、受け入れ企業自身の基準違反など、出入国管理及び難民認定法(入管法)に関連する問題は、「地方出入国在留管理官署」が担当です。
もし、どの機関に通報すべきか判断に迷う場合は、消費者庁のウェブサイトで提供されている「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」システムを利用すると、事案に応じた適切な窓口を探す手助けになります。
通報後の対応
適切な行政機関へ通報を行った後も、企業としての対応は終わりではありません。
まず、通報した日付、通報先の機関名、通報した内容の概要などを、相談記録書や面談報告書といった関連書類に正確に記録として残しておくことが大切です。これにより、企業として適切な対応を取ったことを後から証明できます。また、通報後に行政機関から事実確認のための事情聴取や、関連資料の提出を求められる場合があります。その際には、調査に誠実に協力する義務があります。企業としては、問題を隠蔽しようとするのではなく、行政機関と連携し、問題の根本的な解決と再発防止に向けて真摯に取り組む姿勢を示すことが求められます。
行政機関への通報は、決して望ましい事態ではありませんが、特定技能外国人の人権を守り、制度の健全性を保つためには不可欠な措置です。
まとめ:継続的な見守りと適切な対応が鍵
本記事では、特定技能外国人を受け入れる企業に課せられた義務的支援のうち「定期的な面談」と「行政機関への通報」という、継続的な注意と責任ある判断が求められる二つの項目について、その目的、具体的な実施方法、そして注意点を詳しく解説いたしました。
最後に、これらの支援が持つ本質的な重要性を再確認し、本記事のポイントをまとめたいと思います。
特定技能1号外国人に対する「定期的な面談」は、最低でも3ヶ月に1回以上、本人及びその監督者と個別に行うことが義務付けられています。
これは、労働環境や生活状況を継続的に把握し、問題や悩みを早期に発見・解決するための重要なコミュニケーション手段です。面談は原則対面で、本人が十分に理解できる言語で行い、その結果は「定期面談報告書」として正確に記録・保管する必要があります。そして、この面談などを通じて、労働法令違反や人権侵害といった看過できない重大な問題が明らかになった場合には、企業にはそれを適切な「行政機関へ通報する」という重い義務が課せられます。これは、外国人労働者の権利を守り、制度の適正な運用を担保するための最終的なセーフティネットとして機能します。
これらの「定期面談」と「行政機関への通報」は、単に法律で決められたルールを守るという以上に、企業と外国人従業員との信頼関係を築き、維持していく上で決定的な意味を持ちます。定期的な対話を通じて従業員の状況に真摯に関心を寄せ、問題があれば隠さずに適切な対応を取るという企業の姿勢は、従業員に大きな安心感を与え、エンゲージメントを高めます。結果として、これは従業員の定着率向上に繋がり、企業全体の健全な発展にも寄与するでしょう。コンプライアンスを遵守し、従業員一人ひとりを大切にする企業文化を育む上で、これらの支援は欠かすことのできないプロセスなのです。
私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
関連するオススメ記事はこちら
- 登録支援機関の義務的支援その⑩「定期面談・行政機関への通報」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑨「転職支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑧「日本人との交流促進」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑦「相談・苦情への対応」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑥「日本語学習の機会の提供」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑤「公的手続きへの同行」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その④「生活オリエンテーション」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その③「住居の確保・契約支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その②「出入国時の送迎」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その①「事前ガイダンス」とは?|特定技能外国人

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート