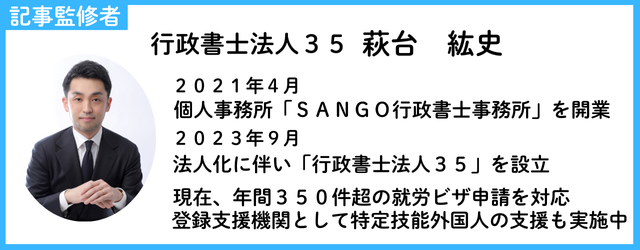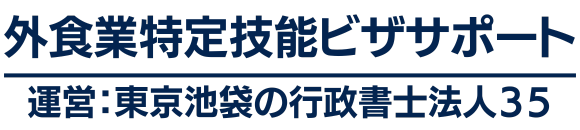特定技能「外食業 」制度概要・採用・取得方法・注意点を解説!

日本の外食産業は、深刻な人手不足に直面しています。
その解決策として注目されているのが、2019年に導入された在留資格「特定技能」です。
特定技能「外食業」は、一定の専門性・技能を持つ外国人が、日本の飲食店で働くことを可能にする制度です。
「外国人材の採用を検討しているが、特定技能制度について詳しく知りたい」
「特定技能ビザで日本で働きたいけど、どうすればいいか分からない」
このような、企業の人事担当者様、そして日本での就労を目指す外国人の方々の疑問や不安を解消するため、この記事では、特定技能「外食業」について、制度の概要から、採用・取得方法、注意点まで、徹底的に解説します。
特定技能制度は、企業にとっては人手不足解消の手段となり、外国人にとっては日本で働く機会を得られる、双方にとってメリットのある制度です。
しかし、制度を適切に活用するためには、正しい知識と理解が不可欠です。
ここでは、企業向けには、特定技能外国人の採用方法、受け入れ体制の整備、登録支援機関の活用などについて、外国人向けには、特定技能ビザの取得要件、申請手続き、日本での生活などについて、それぞれ詳しく解説します。
最後までお読みいただければ、特定技能「外食業」に関する理解が深まり、企業様は外国人材の採用・定着に、外国人の方は日本での就労実現に、それぞれ大きく近づくことができるはずです。ぜひ、ご一読ください。
特定技能「外食業」は、人手不足が特に深刻な外食産業において、即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。
この制度を利用することで、企業は、調理、接客、店舗管理など、幅広い業務に従事できる外国人材を雇用することができます。外国人材にとっては、日本の外食産業で働くための新たな道が開かれ、専門的なスキルを活かし、キャリアアップを目指すことができます。
目次
- 特定技能「外食業」とは?
- 【企業向け】特定技能「外食業」外国人を採用するには?
- 【外国人向け】特定技能「外食業」ビザを取得するには?
- 特定技能「外食業」の現状と課題
- 特定技能「外食業」の今後の展望
- よくある質問(Q&A)
- まとめ
特定技能「外食業」とは?

ここでは、特定技能「外食業」の制度について、基本的な情報を解説します。
特定技能制度全体の概要と、外食業分野に特化した情報を、企業と外国人の両方の視点から整理します。
1. 特定技能制度全体の概要
特定技能制度は、2019年4月に導入された、比較的新しい在留資格制度です。
この制度は、日本の深刻な人手不足に対応するため、特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れることを目的としています。
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
- 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は通算で上限5年まで、家族の帯同は基本的に認められていません。
- 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間の更新に上限はなく、要件を満たせば家族の帯同も可能です。
特定技能「外食業」は、当初は特定技能1号のみでしたが、2024年から特定技能2号も受け入れ可能となりました。
特定技能2号の受け入れより、外食業分野での外国人材の長期雇用、キャリアアップの道が開かれました。
2. 特定技能「外食業」の対象業種・業務内容

特定技能「外食業」の在留資格で働くことができるのは、以下の業種です。
- 食堂、レストラン、カフェ、居酒屋などの飲食店
- 持ち帰り専門店(テイクアウト専門店)
- 宅配専門店(デリバリー専門店)
- 仕出し料理店 など
これらの業種において、具体的に以下のような業務に従事することができます。
- 飲食物調理:和食、洋食、中華料理など、様々なジャンルの料理の調理を行います。
- 接客:お客様の案内、注文取り、料理の提供、レジ打ちなど、接客サービス全般を行います。
- 店舗管理:食材の発注、在庫管理、売上管理、スタッフのシフト管理など、店舗運営に関わる業務を行います。
- デリバリー: 飲食店で作った料理を、お客様に配達します。(※ただし、デリバリー業務のみを専門に行うことはできません。店舗での調理や接客業務と兼務する必要があります。)
ただし、風俗営業法で規制されている「接待飲食等営業」や「性風俗関連特殊営業」に該当する業務は、特定技能「外食業」では行うことができません。
3. 特定技能「外食業」で働くメリット
特定技能 外食業のメリットは下記の通りです
- 企業側
- 人手不足の解消に繋がる
- 専門的な知識と意欲のある人材を確保できる
- 多言語対応ができる
- 外国人側
- 日本で働く機会を得ることができる
- 専門的な知識やスキルを向上できる
- 日本人と同等以上の給料をもらえる
4. 外食業の特定技能1号と2号の違い
外食業における特定技能1号と2号の主な違いは、以下の通りです。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 従事できる業務 | 調理、接客、店舗管理など | 1号の業務に加え、店舗運営、スタッフの指導・育成など |
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし(更新が必要) |
| 家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 |
| 必要な技能レベル | 外食業特定技能1号技能測定試験に合格 | 外食業特定技能2号技能測定試験に合格、実務経験 |
特定技能1号と2号の違い(外食業) 特定技能2号は、より高度な技能と経験を持つ外国人材を対象としており、より長期的な就労が可能となります。次章以降では、企業向け、外国人向けに、それぞれ特定技能「外食業」に関する詳細な情報を解説していきます。
【企業向け】特定技能「外食業」外国人を採用するには?

ここでは、特定技能「外食業」の外国人材を採用したいと考えている企業向けに、具体的な採用方法、手続き、注意点などを解説します。
1. 特定技能所属機関(受け入れ企業)になるための要件
特定技能外国人を受け入れる企業は、「特定技能所属機関」となる必要があります。特定技能所属機関には、いくつかの要件が求められます。
まず、農林水産省が設置した「食品産業特定技能協議会」に加入することが義務付けられています。
この協議会は、特定技能制度の適切な運用をサポートするための組織で、情報提供や相談支援などを行っています。
次に、特定技能1号外国人に対しては、義務的支援と呼ばれる支援を行う必要があります。具体的には、事前ガイダンスの実施、生活オリエンテーションの開催、日本語学習の機会の提供など、多岐にわたるサポートが求められます。
これらの支援は、企業が自ら行うことも可能ですが、専門的な知識やノウハウが必要となるため、多くの企業は登録支援機関に委託しています。
さらに、特定技能外国人と締結する雇用契約は、日本人と同等以上の報酬を支払うこと、労働時間や休日などの労働条件が適切であることなど、労働関係法令を遵守した内容でなければなりません。
また、特定技能雇用契約は、直接雇用に限られ、派遣形態での雇用は認められていません。 加えて、出入国管理法や労働基準法などの関係法令を遵守することも、当然ながら求められます。
2. 採用の流れ
特定技能「外食業」の外国人材を採用するまでの一般的な流れは、以下のようになります。
- まず、特定技能外国人を対象とした求人募集を行うことから始めます。
求人募集の方法としては、ハローワーク、民間の職業紹介事業者などを利用することが一般的です。 - 次に、応募があった外国人の中から、自社が求める人材を選考します。特定技能「外食業」の場合、選考の際には、技能測定試験と日本語能力試験の合格証を確認することが必須となります。
- 採用が決まったら、特定技能雇用契約を締結します。雇用契約書には、業務内容、賃金、労働時間、休日、社会保険の加入など、労働条件を明確に記載する必要があります。
- 特定技能外国人が海外にいる場合は、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。この申請は、企業が行うことも可能ですが、専門家である行政書士に依頼するのが一般的です。
- 在留資格認定証明書が交付されたら、外国人は自国の日本大使館または総領事館でビザを申請します。ビザが発給され、外国人が入国したら、晴れて就労を開始することができます。
3. 登録支援機関の利用
特定技能1号外国人に対する支援は、企業が自ら行うこともできますが、多くの企業は登録支援機関に委託しています。
登録支援機関を利用することで、企業は専門的な知識と経験に基づいたサポートを受けることができます。また、支援計画の作成、各種手続きの代行、外国人材への生活支援など、企業が行うべき煩雑な業務を登録支援機関に任せることができ、業務負担を大幅に軽減できます。さらに、外国人材とのトラブルが発生した場合、登録支援機関が間に入って解決を支援してくれるため、企業は安心して外国人材を受け入れることができます。
登録支援機関を選ぶ際には、支援内容、費用、実績などを比較検討し、自社に合った機関を選ぶことが重要です。
なお、登録支援機関は単独では入管へ提出する書類の作成をおこなうことができません。そのため、行政書士と連携している機関や登録支援機関を兼ねている行政書士事務所を選ぶことをオススメいたします。
4. 費用
特定技能「外食業」の外国人材を採用する際には、様々な費用が発生します。
登録支援機関に支援を委託する場合は、初期費用や月額の委託費などがかかります。また、現在、別の就労ビザをもっている外国人を雇用する場合には、ビザの変更申請に伴う費用が発生します。(行政書士又は弁護士に依頼する申請代行費用や手数料等)その他、外国人材の渡航費用や健康診断費用、日本語教育費用など、企業が負担する費用もあります(企業が負担する場合)
5. 注意点
特定技能「外食業」の外国人材を採用する際には、いくつかの注意点があります。
まず、雇用契約や労働条件に関する法令を遵守し、外国人材に不当な差別をしないことが重要です。また、外国人材が理解できる言語で情報提供やコミュニケーションを行うことも、円滑な労使関係を築く上で不可欠です。自社で支援を行う場合は、支援体制をしっかりと整備し、外国人材が安心して働ける環境を整える必要があります。
これらの注意点を守り、外国人材が安心して働ける環境を整えることが、外国人材の定着と活躍に繋がり、ひいては企業の発展に貢献します。

【外国人向け】特定技能「外食業」ビザを取得するには?

ここでは、特定技能「外食業」のビザを取得して、日本で働きたいと考えている外国人向けに、ビザの取得要件、申請手続き、日本での生活などについて解説します。
1. 特定技能「外食業」ビザの取得要件
特定技能「外食業」のビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 年齢:18歳以上であること
- 技能水準:外食業特定技能1号技能測定試験に合格すること。この試験は、外食業で働くために必要な知識や技能を測るための試験です。試験は、学科試験と実技試験で構成されており、「飲食物調理」「接客」「店舗管理」の3つの分野から出題されます。試験は、日本国内だけでなく、海外でも実施されています
- 日本語能力:日本語能力試験(JLPT)のN4以上に合格していること、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格していること。これは、日本で生活し、働く上で必要となる、基本的な日本語能力があるかどうかを測るための試験です
- 健康状態:健康状態が良好であること。これは、日本で働く上で支障がないかどうかを確認するためのものです。指定された医療機関で健康診断を受け、健康診断書を提出する必要があります。
2. 特定技能「外食業」ビザの申請手続き
特定技能「外食業」のビザを申請するまでの一般的な流れは、以下の通りです。
- 技能測定試験と日本語能力試験に合格する:まずは、上記の試験に合格する必要があります。試験の詳細は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のウェブサイトで確認できます
- 日本の飲食店と雇用契約を結ぶ:試験に合格したら、日本の飲食店を探し、雇用契約を結びます。求人情報は、ハローワークや民間の職業紹介事業者、登録支援機関などで探すことができます
- 在留資格諸申請を行う:雇用契約を結んだら、日本の入国管理局に在留資格諸申請を行います。(海外から招へいする場合には在留資格認定証明書交付申請、すでに国内にいる外国人のビザを変更する場合には在留資格変更許可申請を)この申請は、通常、行政書士等の専門家に依頼するのが一般的です。
- ビザを申請する:在留資格認定証明書が交付されたら、自国の日本大使館または総領事館でビザを申請します
- 日本に入国し、就労を開始する:ビザが発給されたら、日本に入国し、就労を開始することができます。
3. 日本での生活について
特定技能「外食業」のビザで日本に滞在する場合、最長で5年間働くことができます(特定技能1号の場合)
日本での生活を始めるにあたっては、住居の確保、銀行口座の開設、携帯電話の契約など、様々な準備が必要です。
また、日本の生活ルールやマナー、文化、習慣などを理解することも大切です。日本の物価は、あなたの国と比べて高いかもしれません。事前に、生活費や税金、社会保険料などについて、調べておくことをおすすめします。
特定技能1号外国人は、受け入れ企業または登録支援機関から、生活に関する様々なサポートを受けることができます。
困ったことや分からないことがあれば、遠慮せずに相談しましょう。
日本での生活は、最初は慣れないことも多いかもしれませんが、新しい経験や出会いがたくさんあります。特定技能「外食業」の仕事を通じて、日本の文化に触れ、スキルアップを目指しましょう。次章では、特定技能「外食業」の現状と課題について解説します。
特定技能「外食業」の現状と課題

特定技能「外食業」は、日本の外食産業における人手不足を解消するための重要な制度として導入されました。ここでは、制度導入後の現状と、現在抱えている課題について解説します。
1. 在留者数の推移と今後の見通し
特定技能「外食業」の在留者数は、制度開始以来、着実に増加しています。
出入国在留管理庁の発表によると、2024年6月末時点での在留者数は20,317人に達しました。これは、2019年末時点の1,985人と比較すると、約4年半で10倍以上に増加したことになります。
特に、新型コロナウイルスの影響で一時的に減少した時期もありましたが、その後は急速に回復し、増加傾向が続いています。 この増加傾向は今後も続くと予測されており、特定技能「外食業」は、日本の外食産業を支える重要な労働力として、ますますその存在感を増していくでしょう。
2. 成功事例と失敗事例
特定技能「外食業」の導入により、人手不足が解消され、経営が安定したという成功事例が数多く報告されています。
外国人材の積極的な採用と、彼らが働きやすい環境を整備することで、従業員の定着率が向上し、サービスの質が向上したという企業もあります。
また、外国人材の持つ多様なスキルやアイデアが、新メニューの開発やインバウンド対応に活かされているという事例も見られます。
一方で、失敗事例も存在します。
例えば、外国人材とのコミュニケーション不足により、業務上のトラブルが発生したり、早期離職につながったりするケースがあります。
また、文化や習慣の違いから、日本人従業員との間に摩擦が生じることもあります。これらの失敗事例の多くは、企業側の受け入れ体制の不備や、外国人材への理解不足が原因となっています。
3. 特定技能「外食業」が抱える課題
特定技能「外食業」は、多くの可能性を秘めた制度ですが、いくつかの課題も抱えています。
まず、登録支援機関の支援の質にばらつきがあるという問題があります。
特定技能1号外国人に対する支援は、登録支援機関に委託することができますが、登録支援機関の質は様々です。
中には、十分な支援を提供できない登録支援機関や、不当に高額な費用を請求する登録支援機関も存在します。企業は、登録支援機関を選ぶ際に、その実績や評判をしっかりと確認する必要があります。
次に、言語や文化の壁という問題があります。
特定技能外国人には、一定の日本語能力が求められていますが、実際の職場では、より高度なコミュニケーション能力が必要となる場面も少なくありません。
また、日本の文化や習慣に馴染めず、孤立してしまう外国人材もいます。
企業は、外国人材に対する日本語教育の機会を提供したり、異文化理解を深めるための研修を実施したりするなど、言語や文化の壁を乗り越えるための取り組みを行う必要があります。
さらに、特定技能2号への移行の難しさも課題として挙げられます。
特定技能2号は、在留期間の制限がなく、家族の帯同も可能となるため、外国人材にとって非常に魅力的な資格です。
しかし、特定技能2号を取得するためには、より高度な技能試験に合格し、実務経験を積む必要があります。
これらの課題を克服し、特定技能「外食業」の制度をより効果的に活用するためには、企業、登録支援機関、行政機関などが連携し、外国人材が安心して働き、活躍できる環境を整備していくことが重要です。
特定技能「外食業」の今後の展望

特定技能「外食業」は、日本の外食産業における人手不足解消の切り札として、今後ますますその重要性を増していくと予想されます。
ここでは、特定技能「外食業」の今後の展望について、いくつかの視点から解説します。
1. 特定技能2号の拡大と外国人材の長期雇用
2024年から、外食業においても特定技能2号の受け入れが開始されました。
特定技能2号は、在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同も可能となるため、外国人材の長期雇用に繋がる可能性を秘めています。
特定技能2号を取得するためには、より高度な技能試験に合格し、実務経験を積む必要がありますが、外食業でのキャリアアップを目指す外国人材にとっては、大きな目標となるでしょう。企業にとっても、優秀な外国人材を長期間雇用できるメリットは大きく、特定技能2号の活用は、今後の人材戦略の重要な柱となる可能性があります。
2. 制度改正の可能性と企業の対応
特定技能制度は、比較的新しい制度であり、今後も社会情勢や経済状況の変化に合わせて、改正される可能性があります。
例えば、特定技能の対象分野の見直し、技能試験の内容の変更、受け入れ要件の緩和または厳格化などが考えられます。
企業は、常に最新の情報を収集し、制度改正に柔軟に対応していく必要があります。また、特定技能制度に関する情報提供や相談支援を行う、行政機関や業界団体との連携も重要となります。
3. 外食業界における外国人材の役割の変化
特定技能「外食業」の導入により、外食業界における外国人材の役割は、単なる労働力不足の穴埋めから、より重要な役割へと変化していくでしょう。
外国人材の持つ多様なスキルや経験、母国語の能力などは、インバウンド対応の強化、新メニューの開発、海外進出など、企業の成長戦略に貢献する可能性があります。また、外国人材が店舗運営やマネジメントに関わることで、新たな視点やアイデアが生まれ、企業の活性化に繋がることも期待されます。
今後、外食業界では、特定技能外国人を含めた多様な人材が活躍できる職場環境づくりが、ますます重要になっていくでしょう。
具体的には、多言語対応の強化、異文化理解を深めるための研修の実施、外国人材のキャリアアップ支援、日本人従業員とのコミュニケーション促進など、様々な取り組みが求められます。特定技能制度は、日本の外食産業が持続的に発展していくための、重要な鍵を握っていると言えるでしょう。

よくある質問(Q&A)
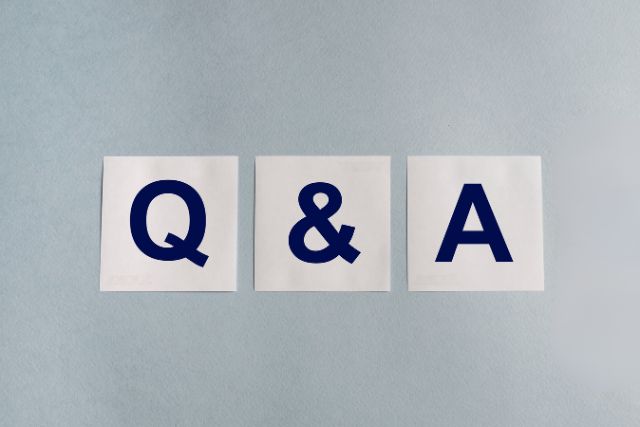
ここでは、特定技能「外食業」に関して、企業と外国人材からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- Q1. 登録支援機関は必ず利用しなければならないのですか?
- A1. いいえ、必ずしも利用する必要はありません。
特定技能1号外国人に対する支援は、企業(特定技能所属機関)が自ら行うことも可能です。ただし、自社で支援を行うためには、支援責任者および支援担当者の選任、外国人材への適切な情報提供体制の整備など、一定の要件を満たす必要があります。これらの要件を満たすことが難しい場合や、より専門的なサポートを受けたい場合は、登録支援機関の利用を検討すると良いでしょう。 - Q2. 登録支援機関の費用は誰が負担するのですか?
- A2. 登録支援機関への費用は、特定技能所属機関(受け入れ企業)が負担します。特定技能外国人に費用を負担させることは、法律で禁止されています。
- Q3. 特定技能外国人の採用にかかる費用はどのくらいですか?
- A3. 採用にかかる費用は、人材紹介会社を利用するか、登録支援機関を利用するかどうか、外国人材の日本語能力や技能レベル、採用方法などによって異なります。
一般的には、初期費用(求人広告費、登録支援機関への委託費用、行政書士へのビザ申請費用など)と、月額費用(登録支援機関への委託費用、給与、社会保険料など)がかかります。具体的な費用については、登録支援機関や行政書士に見積もりを依頼することをおすすめします。 - Q4. 企業での特定技能外国人の受け入れ人数に制限はありますか?
- A4. 外食業分野では、特定技能1号外国人の受け入れ人数に上限は設けられていません。
- Q5. 特定技能「外食業」では、どんな仕事ができますか?
- A5. 特定技能「外食業」では、調理、接客、店舗管理など、外食業全般に関わる業務に従事することができます。具体的には、料理の調理、お客様への料理の提供、レジ打ち、食材の発注、在庫管理、スタッフのシフト管理など、様々な業務があります。
ただし、風俗営業法で規制されている「接待飲食等営業」や「性風俗関連特殊営業」に該当する業務は行うことができません。 - Q6. 特定技能「外食業」の給料はどのくらいですか?
- A6. 特定技能外国人の給料は、日本人と同等以上でなければなりません。具体的な給料は、勤務先の企業や、あなたの経験、スキル、勤務地などによって異なります。
雇用契約を結ぶ前に、必ず給与や労働条件を確認しましょう。 - Q7. 特定技能「外食業」のビザで、家族を日本に呼ぶことはできますか?
- A7. 特定技能1号のビザでは、原則として家族の帯同は認められていません。
しかし、特定技能2号のビザを取得すれば、要件を満たすことで家族(配偶者および子)の帯同が可能になります。特定技能2号を取得するためには、より高度な技能試験に合格し、実務経験を積む必要があります。 - Q8. 日本での生活で困ったことがあったら、どこに相談すればいいですか?
- A8. 勤務先の企業や登録支援機関に相談することができます。
また、各都道府県には、外国人向けの相談窓口が設置されています。これらの相談窓口では、生活に関する様々な相談に、多言語で対応しています。
まとめ

本記事では、特定技能「外食業」について、制度の概要から、企業向けの採用情報、外国人向けのビザ取得情報、現状と課題、今後の展望まで、幅広く解説しました。最後に、記事の重要なポイントをまとめます。
- 特定技能「外食業」は、日本の外食産業における人手不足を解消するための制度であり、一定の専門性・技能を持つ外国人が、日本の飲食店で働くことを可能にする。
- 特定技能には「1号」と「2号」があり、外食業では、調理、接客、店舗管理など幅広い業務に従事できる。
- 特定技能「外食業」のビザを取得するためには、技能測定試験と日本語能力試験に合格する必要がある。
- 企業が特定技能外国人を受け入れるためには、特定技能所属機関となり、食品産業特定技能協議会への加入や支援体制の整備などの要件を満たす必要がある。
- 特定技能外国人に対する支援は、企業が自ら行うことも、登録支援機関に委託することもできる。
- 特定技能「外食業」の在留者数は増加傾向にあり、今後も外食業界における重要な労働力として期待されている。
- 特定技能「外食業」には、支援の質のばらつき、言語・文化の壁、特定技能2号への移行の難しさなどの課題もある。
- 2024年からは外食業でも特定技能2号の受け入れが開始され、外国人材の長期雇用、キャリアアップの道が開かれた。
特定技能「外食業」は、企業にとっては人手不足解消の有効な手段であり、外国人材にとっては日本で働く機会を得られる、双方にとってメリットのある制度です。
しかし、制度を適切に活用するためには、企業、外国人材双方が、制度の内容を正しく理解し、必要な準備を行うことが重要です。
行政書士法人35は、特定技能制度に関する豊富な知識と経験を持つ行政書士が、企業の外国人材採用・特定技能ビザ申請を全面的にサポートしています。また、登録支援機関も兼ねているためワンストップで対応が可能です。。
「特定技能外国人材の採用を検討しているが、何から始めれば良いか分からない」
「登録支援機関について詳しく知りたい」
「特定技能制度についてもっと詳しく知りたい」など、
どんなことでもお気軽にご相談ください。専門家が、貴社の状況に合わせて、最適なアドバイスをさせていただきます。
メールでの無料相談はこちら
関連するおすすめ記事
- 【特定技能】外食業協議会への加入申請について|手続き・必要書類・注意点を解説
- 登録支援機関の義務的支援その⑩「定期面談・行政機関への通報」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑨「転職支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑧「日本人との交流促進」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑦「相談・苦情への対応」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑥「日本語学習の機会の提供」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑤「公的手続きへの同行」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その④「生活オリエンテーション」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その③「住居の確保・契約支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その②「出入国時の送迎」とは?|特定技能外国人