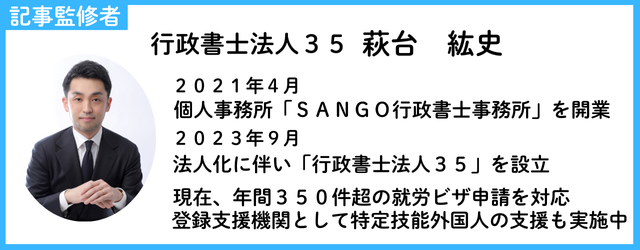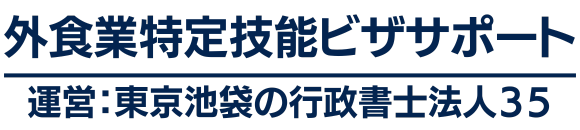【JLPT】特定技能ビザ取得に必要な日本語能力試験の種類・レベル・対策・合格のコツとは?
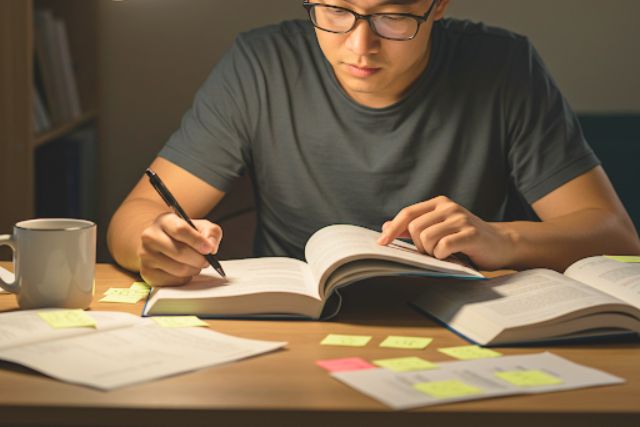
「特定技能ビザを取るには、どの日本語試験を受ければいいの?」
「試験の種類が多くて、どれが自分に合っているかわからない…」
「試験のレベルは?難易度は?」
「どんな勉強をすれば合格できるの?」
「不合格になったらどうすればいいの?」
「2025年の最新情報が知りたい!」
初めて日本語試験を受ける方や、特定技能制度について詳しくない方は、特にそう感じるかもしれません。
この記事では、特定技能ビザの取得に必要な日本語試験について、試験の種類、レベル、難易度、効果的な対策、合格後の手続き、不合格時の対応策、そして2025年の最新情報まで、皆さんが知りたい情報をわかりやすく解説します。
特定技能ビザの取得では、日本語試験の合格が最初のステップです。
最後までお読みいただき、自分に合った試験を選び、計画的に学習を進めて、夢の実現に近づいてください。
目次
- 特定技能制度と日本語試験の概要
- 特定技能の日本語試験の種類と詳細
- 特定技能の日本語試験対策
- 特定技能の日本語試験に不合格だった場合
- 特定技能の日本語試験に関する最新情報と注意点
- 特定技能の日本語試験に関するFAQ
- まとめ
特定技能制度と日本語能力試験の概要

特定技能制度は、日本国内で人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人が働くことを認める制度です。この制度を利用して日本で働くためには、「特定技能」という在留資格を取得する必要があります。
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。
特定技能1号は、特定の産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
一方、特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、1号よりも高いレベルの技能が求められます。多くの場合、まずは特定技能1号を取得し、その後、試験に合格するなどして2号に移行します。
特定技能1号の在留資格を取得するためには、原則として、「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。つまり、日本で働くために必要な技能を持っていることに加えて、仕事や日常生活で使う日本語の能力も求められるということです。
なぜ、特定技能制度で日本語能力が重視されるのでしょうか?
それは、皆さんが日本で安全に、そして安心して働き、生活するためには、日本語でのコミュニケーションが欠かせないからです。日本語が理解できれば、仕事の指示を正しく理解したり、同僚と協力して仕事を進めたりすることができます。また、日常生活においても、買い物をしたり、役所での手続きをしたり、近所の人と交流したりする際に、日本語が必要になります。
特定技能制度では、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」が日本語能力の基準とされています。具体的にどの試験を受ければいいのか、どのくらいのレベルが必要なのかについては、次の章で詳しく説明します。
特定技能の日本語能力試験の種類と詳細
特定技能1号の取得を目指す皆さんが受験する可能性のある日本語試験は、主に3種類あります。それぞれの試験の特徴を詳しく見ていきましょう。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、主に就労のために来日する外国人が、生活や仕事の場面で必要となる日本語コミュニケーション能力を測定するテストです。コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式で実施され、試験結果はその場ですぐにわかります。
試験内容は、「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4つのセクションで構成され、問題数は合計で約50問、試験時間は60分です。
日常生活や職場での基本的なコミュニケーションに必要な日本語が出題されます。例えば、「お店で『これはいくらですか?』と値段を尋ねる」「『すみません、トイレはどこですか?』と道を聞く」「『〇〇さん、電話です』と伝言を受ける」「『〇〇に注意してください』という掲示を読む」といった場面が想定されます。
JFT-Basicでは、A1からC2までの6段階のレベルで日本語能力が評価されますが、特定技能1号の取得にはA2レベル以上が必要です。
A2レベルとは、「『私は〇〇です』『これは〇〇円です』『〇〇へ行きたいです』といった簡単な文を理解し、使うことができる」程度の能力です。自分の名前や出身地、家族のこと、好きな食べ物など、身近な話題について簡単な質問に答えたり、短い文章で表現したりできることが求められます。
JFT-Basicは、原則として毎月のように、日本国内および海外の複数の国で実施されています。詳しい試験日程や会場、申し込み方法については、国際交流基金のウェブサイトで確認してください。受験料は国によって異なりますが、日本国内の場合は7,000円程度です。
JFT-Basicは、比較的短い準備期間で受験できること、試験結果がすぐにわかること、受験機会が多いことなどがメリットです。
「日本語の勉強を始めて間もない」「できるだけ早く特定技能ビザを取得したい」という方におすすめの試験です。
日本語能力試験(JLPT)
日本語能力試験(JLPT)は、日本語を母語としない人を対象に、日本語能力を測定し認定する、世界最大規模の日本語の試験です。日本語を勉強している外国人の方にはもっとも馴染みのある試験かと思います。N1からN5までの5つのレベルがあり、N1が最も難しく、N5が最も易しいレベルです。特定技能1号の取得には、N4レベル以上が必要です。
JLPTのN4レベルは、「基本的な日本語を理解することができる」レベルとされています。「『図書館で本を借りる』『病院で症状を説明する』『電車やバスの時刻表を見る』など、日常生活でよくある場面で使われる日本語を理解し、使うことができる」程度の能力です。基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な話題の文章を読んで理解でき、日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できることが求められます。
試験内容は、「言語知識(文字・語彙・文法)」「読解」「聴解」の3つのセクションで構成されています。試験はマークシート形式で、N4レベルの試験時間は、言語知識(文字・語彙)が30分、言語知識(文法)・読解が60分、聴解が35分です。
JLPTは、年2回(7月と12月)に、日本国内および海外の多くの国や地域で実施されます。詳しい試験日程や会場、申し込み方法については、日本語能力試験のウェブサイトで確認してください。受験料は、日本国内の場合は7,500円(2025年から)です。
JLPTは、国際的に広く認知されている試験であり、日本語能力の証明として信頼性が高いというメリットがあります。「日本語をある程度勉強したことがある」「自分の日本語能力を客観的に評価したい」という方におすすめの試験です。
分野別試験(介護など)
特定技能の分野によっては、JFT-BasicやJLPTに加えて、分野別の日本語試験が課される場合があります。例えば、介護分野では「介護日本語評価試験」が実施されています。
これらの分野別試験は、それぞれの分野の業務で必要となる専門的な用語や表現、コミュニケーション能力を評価するためのものです。
例えば、介護日本語評価試験では、「『おむつ交換』『体位変換』『食事介助』などの介護用語を理解しているか」「『〇〇さん、お風呂に入りましょう』『痛みはありますか?』など、利用者とのコミュニケーションで使う日本語を理解し、使うことができるか」「介護記録を読んで、利用者の状態を把握できるか」といった点が問われます。
分野別試験の試験内容、レベル、合格基準、受験資格、受験料、試験日程、試験会場などは、分野によって異なります。自分が希望する分野の試験については、各分野の試験実施団体のウェブサイトで詳細を確認してください。
なお、技能実習2号を良好に修了した方は、これらの日本語試験が免除される場合があります。ただし、技能実習の分野と異なる分野の特定技能1号を取得する場合は、分野別試験の合格が必要です。
特定技能の日本語試験対策
この章では、特定技能の日本語試験に合格するための具体的な勉強方法をご紹介します。試験に合格するためには、やみくもに勉強するのではなく、自分に合った方法で、計画的に学習を進めることが大切です。
自分に合った試験を選ぶ
まずは、どの試験を受けるかを決めましょう。
前の章で説明したように、特定技能1号の取得には、JFT-Basic、JLPT(N4以上)、いずれかに合格する必要があります。それぞれの試験の特徴を比較検討し、自分に合った試験を選びましょう。
例えば、「日本語の勉強を始めて間もない」「できるだけ早く特定技能ビザを取得したい」という方は、比較的難易度が低く、受験機会が多いJFT-Basicがおすすめです。
「日本語をある程度勉強したことがある」「自分の日本語能力を客観的に評価したい」という方は、JLPTがおすすめです。
目標と計画を立てる
どの試験を受けるか決めたら、次は目標と計画を立てましょう。
「いつまでに、どのレベルに合格するか」という具体的な目標を設定し、その目標を達成するための学習計画を立てます。毎日コツコツ勉強するのか、週末にまとめて勉強するのか、自分のライフスタイルに合わせて無理のない計画を立てることが大切です。
自分に合った教材を選ぶ
試験対策には、自分に合った教材を選ぶことが重要です。書店やインターネット通販では、特定技能の日本語試験対策用の教材がたくさん販売されています。自分のレベルや目的に合った教材を選びましょう。
例えば、JFT-Basic対策には、「いろどり 生活の日本語」などの教材がおすすめです。JLPT対策には、「日本語総まとめ」「新完全マスター」などのシリーズが人気です。分野別試験対策には、各試験実施団体が提供している教材や、過去問を活用しましょう。
また、最近では、スマートフォンアプリやオンライン教材も充実しています。これらの教材を活用すれば、通勤時間や休憩時間などのスキマ時間を有効活用して勉強することができます。自分に合った教材を見つけて、楽しく学習を続けましょう。
効果的な勉強方法

教材を選んだら、いよいよ勉強開始です。効果的な勉強方法のポイントは、以下の3つです。
- インプットとアウトプットのバランス:単語や文法を覚える(インプット)だけでなく、実際に使ってみる(アウトプット)ことが大切です。覚えた単語や文法を使って、自分で文を作ってみたり、会話の練習をしたりしましょう。
- 繰り返し学習:一度覚えたことでも、時間が経つと忘れてしまうものです。繰り返し学習することで、記憶を定着させましょう。
- 実践的な練習:試験本番を想定した実践的な練習も重要です。過去問を解いたり、模擬試験を受けたりして、時間配分や問題の解き方に慣れておきましょう。
また、可能であれば、日本語学校に通ったり、オンラインレッスンを受けたりするのもおすすめです。専門の先生から指導を受けることで、効率的に学習を進めることができます。日本人の友達を作って会話の練習をするのも良い方法です。
日本で生活している方は日本語に触れる機会が多いので積極的に活用しましょう。お店の看板やメニュー、電車の案内表示、テレビのニュースなど、身の回りにある日本語に注意を向けてみましょう。わからない単語や表現があれば、すぐに調べて意味を確認する習慣をつけましょう。
日本語能力がまだ低い方へ
「日本語の勉強を始めたばかりで、試験に合格できるか不安…」
という方もいるかもしれません。
この章では、日本語能力がまだ低い方が、どのように学習を進めていけばよいか、そのヒントをお伝えします。
まずは基礎をしっかり固める
日本語の勉強を始めたばかりの頃は、覚えることがたくさんあって大変かもしれません。しかし、焦らずに、まずは基礎をしっかりと固めることが大切です。ひらがな、カタカナ、基本的な挨拶、簡単な自己紹介など、日常生活でよく使う言葉から覚えていきましょう。
教材としては、「みんなの日本語」や「げんき」などの初級者向けの教科書がおすすめです。これらの教科書には、日常生活でよく使う単語や文法が、イラストや会話例とともにわかりやすく解説されています。
CDや音声教材を活用して、発音の練習も忘れずに行いましょう。
日本語に触れる機会を増やす
日本語能力を伸ばすためには、できるだけ多くの日本語に触れることが重要です。
教科書での勉強だけでなく、日本のテレビ番組やアニメ、映画、ドラマ、音楽などを楽しむのも良い方法です。最初は字幕付きで見て、慣れてきたら字幕なしで挑戦してみましょう。
また、日本人の友達を作って会話の練習をするのもおすすめです。
最初は簡単な挨拶や自己紹介から始めて、徐々に会話のレベルを上げていきましょう。間違えることを恐れずに、積極的に話すことが大切です。
日本語の先生を見つける
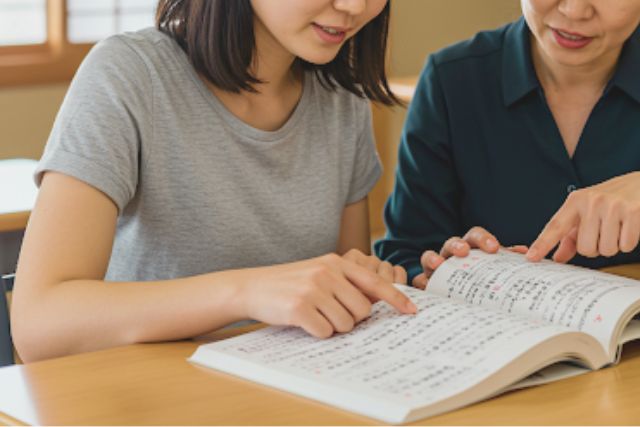
独学で日本語を勉強することもできますが、日本語の先生を見つけて指導を受けることを強くおすすめします。
先生がいれば、わからないことをすぐに質問できますし、発音や文法の誤りを直してもらえます。また、自分に合った学習方法や教材についてアドバイスをもらうこともできます。
日本語学校に通うのが難しい場合は、オンラインレッスンを利用するのも良い方法です。最近では、SkypeやZoomなどのビデオ通話ツールを使って、自宅にいながら日本語のレッスンを受けられるサービスが増えています。費用や時間、レッスンの内容などを比較検討して、自分に合ったサービスを選びましょう。
先生には、特定技能の日本語試験対策をお願いすることもできます。試験の傾向や対策について専門的な知識を持っているので、効率的に試験対策を進めることができます。
諦めずに、コツコツと続ける
日本語の勉強は、一朝一夕には成果が出ないものです。
しかし、諦めずに、毎日コツコツと学習を続けることが大切です。少しずつでも良いので、毎日日本語に触れる時間を作りましょう。1日10分でも15分でも構いません。継続は力なり、です。
そして、「日本で働きたい!」という強い気持ちを持ち続けることが、何よりも大切です。目標に向かって努力を続ければ、必ず日本語能力は向上し、特定技能の日本語試験にも合格できるはずです。頑張ってください!
特定技能の日本語試験に不合格だった場合

もし日本語試験に不合格だったとしても、諦める必要はありません。この章では、不合格だった場合の対応策について解説します。
再受験を検討する
最も一般的な対応策は、再受験です。JFT-Basicは、ほぼ毎月のように実施されていますし、JLPTも年に2回(7月と12月)実施されます。分野別試験の実施頻度はそれぞれ異なりますが、多くの場合、年に複数回実施されています。
再受験までの間は、前回の試験結果を分析し、自分の弱点を克服するための学習計画を立てましょう。間違えた問題や理解が不十分だった部分を重点的に復習し、同じミスを繰り返さないようにすることが大切です。必要に応じて、日本語学校に通ったり、オンラインレッスンを受けたりするのも良い方法です。
再受験の際には、試験の申し込み手続きを忘れずに行いましょう。
申し込み期間や方法は、試験によって異なりますので、各試験の公式サイトで確認してください。また、受験料も必要になりますので、準備しておきましょう。
他の在留資格への変更を検討する
特定技能の日本語試験に不合格だった場合でも、他の在留資格で日本に滞在できる可能性があります。例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 他の就労ビザへの変更:日本語能力以外の要件を満たしている場合は、他の就労ビザ(例えば、「技術・人文知識・国際業務」など)への変更を検討することもできます。
- 留学ビザへの変更:日本語学校や専門学校、大学などに進学する場合は、留学ビザへの変更を検討することができます。留学ビザで日本に滞在しながら、日本語能力を向上させ、再度特定技能の日本語試験に挑戦することも可能です。
どの在留資格に変更できるかは、個人の状況によって異なります。入国管理局や行政書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
帰国を検討する
残念ながら、再受験しても合格の見込みがない場合や、他の在留資格への変更が難しい場合は、帰国を検討する必要があるかもしれません。
しかし、日本で学んだ日本語や経験は、決して無駄にはなりません。帰国後も、日本語能力を活かして仕事を見つけたり、日本と関わる活動をしたりすることができるでしょう。
帰国前に、特定技能制度や日本語試験に関する情報を整理し、今後の計画を立てておきましょう。もし、将来的に再び日本で働くことを希望する場合は、帰国後も日本語の勉強を続け、特定技能制度の最新情報をチェックしておくことをおすすめします。
いずれの選択をするにしても、一人で悩まずに、周りの人に相談することが大切です。家族、友人、先生、会社の担当者など、信頼できる人に相談し、アドバイスをもらいましょう。そして、自分にとって最善の道を選び、前向きに進んでいきましょう。
特定技能の日本語試験に関する最新情報と注意点
この章では、特定技能の日本語試験に関する最新情報、制度改正、そして受験する上での注意点について解説します。特定技能制度は比較的新しい制度であり、頻繁に情報が更新されるため、常に最新の情報を把握しておくことが重要です。
試験日程、試験会場、受験料などの変更
日本語試験の日程、試験会場、受験料などは、変更される可能性があります。
特に、新型コロナウイルス感染症の影響で、試験が延期や中止になったり、オンラインでの実施に変更されたりするケースもありました。受験を予定している試験については、必ず公式サイトで最新情報を確認しましょう。
例えば、日本語能力試験(JLPT)は、2025年から受験料が値上げされることが発表されています。また、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式で実施されており、ほぼ毎月のように受験機会がありますが、国や地域によっては、実施状況が異なる場合があります。
制度改正情報
特定技能制度は、導入以来、何度か改正されています。
例えば、対象分野が拡大されたり、在留資格の要件が変更されたりすることがあります。これらの制度改正は、日本語試験の要件にも影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
2024年には、特定技能制度の見直しが行われ、対象分野が拡大されるなどの変更がありました。また、技能実習制度に代わる新たな制度「育成就労制度」が導入される予定であり、これに伴い、特定技能への移行要件や日本語試験の扱いが変わる可能性があります。
情報収集の方法

特定技能の日本語試験に関する最新情報を得るためには、以下の情報源を活用しましょう。
- 各試験の公式サイト:JFT-Basic、JLPT、分野別試験など、各試験の公式サイトには、試験日程、試験会場、受験料、申し込み方法、試験内容、合否判定基準など、詳細な情報が掲載されています。
- 特定技能制度に関する政府機関のウェブサイト:出入国在留管理庁や厚生労働省などのウェブサイトには、特定技能制度に関する最新情報や、関連する法令、通知などが掲載されています。
- ニュースサイトや専門メディア:外国人雇用に関するニュースサイトや専門メディアでは、特定技能制度の動向や、日本語試験に関する情報が提供されています。
- 行政書士などの専門家:特定技能制度や在留資格に詳しい行政書士などの専門家に相談するのも、正確な情報を得るための有効な手段です。
試験に関する注意点
最後に、特定技能の日本語試験を受験する上での注意点をいくつか挙げておきます。
- 試験によっては年に数回しか実施していないものもあります。早めに計画を立てて準備しましょう
- 申し込み期間や方法、必要書類などは、試験によって異なります。
- 試験当日は、時間に余裕を持って試験会場に到着するようにしましょう。
- 本人確認書類や受験票など、必要な持ち物を忘れないようにしましょう。
- 試験中は、監督員の指示に従い、不正行為は絶対にしないようにしましょう。
特定技能の日本語試験に関するFAQ

この章では、特定技能の日本語試験に関してよくある質問とその回答をまとめました。試験に関する疑問や不安を解消し、自信を持って試験に臨みましょう。
- Q1. 日本語が母国語ではない場合、どのくらい勉強すれば合格できますか?
A1. 合格に必要な勉強時間は、個人の日本語レベルや学習ペース、受験する試験の種類によって異なります。
一般的に、JFT-BasicのA2レベルであれば、初級レベルの日本語学習を終えた方が、1〜3ヶ月程度集中的に対策をすれば合格できる可能性があります。
JLPTのN4レベルであれば、初級レベルの日本語学習を終えた方が、3〜6ヶ月程度かけて対策をするのが一般的です。ただし、これらはあくまで目安であり、個人差が大きいことを理解しておきましょう。 - Q2. 日本に住んでいなくても受験できますか?
A2. はい、受験できます。JFT-BasicとJLPTは、日本国内だけでなく、海外の多くの国や地域で実施されています。
分野別試験については、実施国が限られている場合がありますので、各試験の公式サイトで確認してください。また、最近では、オンラインで受験できる試験も増えています。 - Q3. 日本語の先生を見つけるにはどうすればよいですか。
A3. 日本語の先生を見つける方法はいくつかあります。- 日本語学校に通う
- オンラインの日本語レッスンサービスを利用する
- 地域の国際交流協会や日本語ボランティア団体に相談する
- 大学や専門学校の留学生センターに相談してみる
- SNSや掲示板などで個人的に日本語教師を探す
自分に合った方法で、信頼できる先生を見つけましょう。
- Q4. どの試験が自分に合っているか、どうすればわかりますか?
A4. まずは、各試験の公式サイトで、試験内容、レベル、サンプル問題などを確認しましょう。そして、自分の現在の日本語レベル、学習ペース、受験可能な時期、費用などを考慮して、総合的に判断しましょう。もし迷う場合は、日本語学校の先生や、特定技能制度に詳しい専門家(行政書士など)に相談してみるのも良い方法です。 - Q5. 試験に落ちたら、もう特定技能ビザは取れませんか?
A5. いいえ、そんなことはありません。何度でも再受験できます。
JFT-Basicは、ほぼ毎月のように実施されていますし、JLPTも年に2回実施されます。分野別試験の実施頻度はそれぞれ異なりますが、多くの場合、年に複数回実施されています。諦めずに、再挑戦しましょう。 - Q6. 試験の申し込み方法を教えてください。
A6. 試験の申し込み方法は、試験によって異なります。
JFT-Basicは、オンラインで申し込みます。JLPTは、オンラインまたは郵送で申し込みます。分野別試験の申し込み方法は、各試験の公式サイトで確認してください。申し込み期間や必要書類、受験料の支払い方法などを、事前に確認しておきましょう。 - Q7. 試験当日に必要なものは何ですか?
A7. 試験当日に必要なものは、試験によって異なりますが、一般的には以下のものが必要です。- 受験票
- 本人確認書類(パスポート、在留カードなど)
- 筆記用具(鉛筆、消しゴムなど)
- その他、時計や飲み物など、必要に応じて持参しましょう。持ち物については、各試験の公式サイトで必ず確認してください。
このFAQが、皆さんの疑問や不安を少しでも解消できれば幸いです。もし、他にわからないことがあれば、遠慮なく質問してください。特定技能制度や日本語試験に関する情報は、頻繁に更新されます。常に最新の情報を確認し、万全の準備をして試験に臨んでください。
まとめ
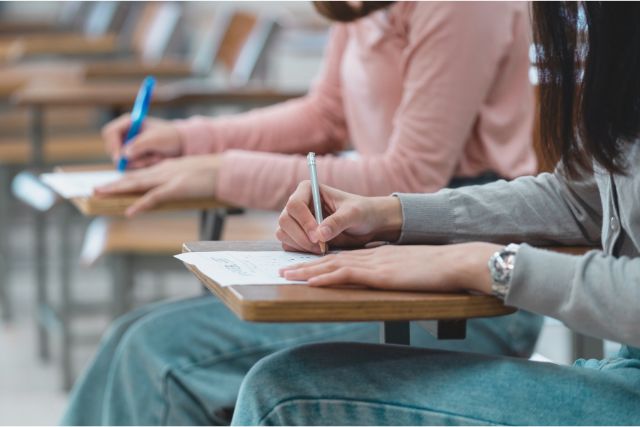
この記事では、特定技能ビザの取得を目指す皆さんに向けて、日本語試験の種類、レベル、難易度、効果的な対策、合格後の手続き、不合格時の対応策、そして2025年の最新情報まで、詳しく解説してきました。
特定技能ビザの取得には、日本語試験の合格が最初のステップとなります。
しかし、試験に合格することだけが目的ではありません。大切なのは、日本で働き、生活するために必要な日本語能力を身につけることです。日本語でのコミュニケーション能力を高めれば、仕事の幅が広がり、より多くのチャンスを掴むことができます。
また、日本での生活もより豊かになり、充実したものになるでしょう。
この記事で紹介した情報を参考に、ぜひ、自分に合った日本語試験を選び、計画的に学習を進めてください。そして、諦めずに努力を続ければ、必ず目標を達成できるはずです!
具体的な行動としては、まず、JFT-Basic、JLPT、分野別試験など、各試験の公式サイトで最新情報を確認しましょう。
そして、試験日程や申し込み方法、受験料などを確認し、受験計画を立てましょう。次に、自分に合った教材を選び、学習計画を立て、毎日コツコツと勉強を続けましょう。
もし、独学での学習に不安がある場合は、日本語学校に通ったり、オンラインレッスンを受けたりすることも検討しましょう。
そして、もし試験に不合格だったとしても、決して諦めないでください。再受験する、他の在留資格を検討するなど、様々な選択肢があります。
周りの人に相談したり、専門家のアドバイスを受けたりしながら、自分にとって最善の道を選びましょう。
特定技能ビザを取得し、日本で働くことは、皆さんにとって大きなチャンスです。そのチャンスを掴むために、今すぐ行動を開始しましょう!
メールでの無料相談はこちら関連するおすすめ記事
- 【特定技能】外食業協議会への加入申請について|手続き・必要書類・注意点を解説
- 登録支援機関の義務的支援その⑩「定期面談・行政機関への通報」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑨「転職支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑧「日本人との交流促進」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑦「相談・苦情への対応」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑥「日本語学習の機会の提供」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その⑤「公的手続きへの同行」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その④「生活オリエンテーション」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その③「住居の確保・契約支援」とは?|特定技能外国人
- 登録支援機関の義務的支援その②「出入国時の送迎」とは?|特定技能外国人